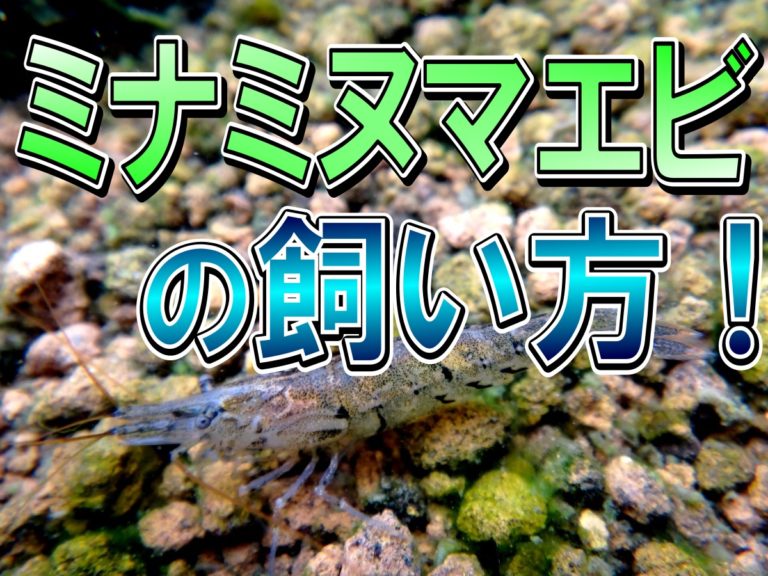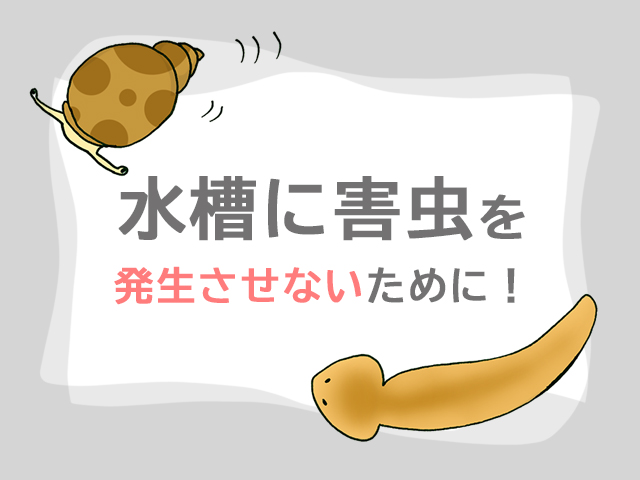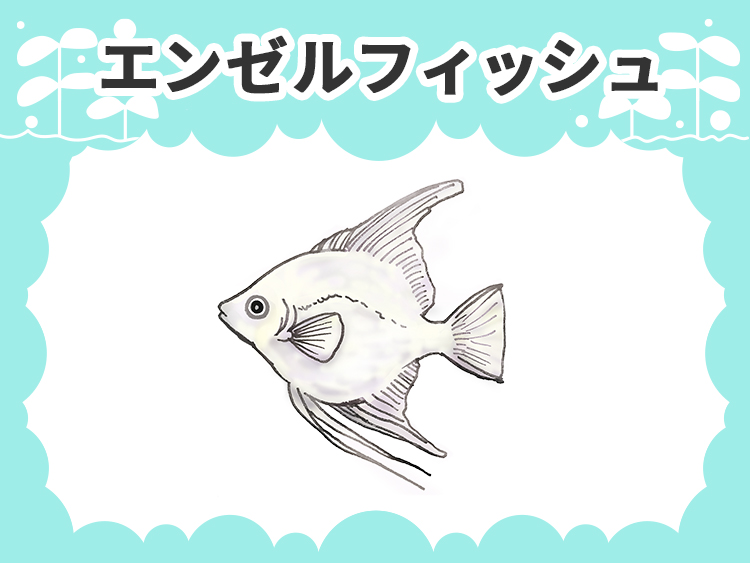混泳水槽のエビはどちらがおすすめ?ヤマトヌマエビとミナミヌマエビの比較と飼育方法
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
アクアリウムにおいて、コケ取りを目的とした『お掃除生体』として代表的な存在の、ヤマトヌマエビとミナミヌマエビ。
これらのヌマエビは体長や繁殖方法、コケ取り能力などが異なるため、導入予定の水槽にはどちらが適しているのかわかりづらく、悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで、このコラムではヤマトヌマエビとミナミヌマエビの両者を比較し、どちらのヌマエビがどのような水槽に適しているのかをわかりやすく解説していきます。
今後クリーナー生体としてヌマエビを導入予定の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとにご紹介

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
ヤマトミナミとミナミヌマエビは、どちらもクリーナーフィッシュの代表種で、東京アクアガーデンでも取り扱うことの多い生体です。
今回は両者の違いや特徴、導入するのに向いている水槽について解説していきますので、クリーナー生体としてヌマエビの飼育を検討中の方はぜひご覧になってみてください。
ヤマトヌマエビとミナミヌマエビのことを動画で知る!
この記事の内容は、YouTube動画でもご覧いただけます!
ヌマエビの特徴やコケ取りの比較などを音声付きで解説しています。
トロピカでは人気の記事動画をYouTubeチャンネル「トロピカチャンネル」で随時配信しています。
エビや魚を飼育するうえでの疑問や悩み(コケ対策、病気など)の解決法から水槽のレイアウトポイントまで、続々アップしていきます。
ぜひチャンネル登録をお願いいたします!
ヤマトヌマエビとミナミヌマエビの特徴

ヤマトヌマエビとミナミヌマエビは両者ともヌマエビの仲間ではあるものの、サイズやコケ取り能力、繁殖の仕方に大きな差があります。
それぞれの飼育環境に適したヌマエビを選択できるように、まずはヤマトヌマエビとミナミヌマエビの生態や特徴などを確認しておきましょう。
ヤマトヌマエビとは
ヤマトヌマエビは西日本の渓流域や台湾、インド洋~西太平洋沿岸部に分布し、全長はオスで4cm、メスは6cm程度にもなる比較的大型なヌマエビの仲間です。
餌として口にするコケの量が多く、1匹あたりのコケ取り能力が高い傾向にあります。
頑固な黒髭コケも食べてくれることから、クリーナー生体としてはかなり重宝される存在で、中型水槽など面積の広い容器にも向いているヌマエビです。
ただし先述したように比較的大きなエビのため、小さな水槽内では結構な存在感があります。
魚をメインとした水槽ではクリーナー生体の存在感がデメリットとなる場合もあるため、その点には注意しておきましょう。
ヤマトヌマエビは元々汽水域に生息しており、卵から孵った幼生期には海水を必要とします。
普通の淡水水槽では飼育下で繁殖させるのが難しいため、寿命(約2~3年)を迎えたら新しい生体を買い足すのがおすすめです。
ミナミヌマエビとは
ミナミヌマエビは西日本から朝鮮半島、中国や台湾などに分布し、最大体長は3cmの小型なヌマエビの仲間です。
ヤマトヌマエビと比較すると口にするコケの量が少なく、固いコケは苦手なため、1匹あたりのコケ取り能力はヤマトヌマエビより劣る傾向にあります。
一定のコケ取り効果を実感するためには数を多く入れる必要がありますが、ミナミヌマエビは小型ゆえに水槽内であまり目立たないので、それほど目立つことはありません。
繁殖は容易で、環境が整った淡水水槽であれば簡単に殖やすことができます。
ただしミナミヌマエビの稚エビはかなり小さく、ろ過フィルターの吸水口から吸い込まれてしまうことが多いため、繁殖させるならばストレーナー部にスポンジを取り付けるなどの対策を取りましょう。
ヤマトヌマエビとミナミヌマエビのどちらを選ぶ?
ヤマトヌマエビとミナミヌマエビのどちらを選ぶか迷った時には、次の基準で考えてみると良いでしょう。
■ヤマトヌマエビが向いた水槽

まずはヤマトヌマエビの導入が向いている水槽について。
当てはまる条件としては、
- コケ取り能力を期待したい
- 比較的大きな魚と混泳させたい
- 大型水槽に導入したい
といったポイントが挙げられます。
すでにコケの繁茂が酷い状態であったり、たくさんのコケが生えることが予想される場合は、コケ取り能力が高いヤマトヌマエビを導入するのがおすすめです。
そして、比較的大きな魚と混泳させる場合は、ミナミヌマエビでは小さすぎて食べられてしまう可能性が考えられます。
大きめの魚種と同じ水槽に入れるのであれば、サイズが大きなヤマトヌマエビを選んでおいた方が無難です。
また、ヤマトヌマエビは食べ物が足りなくなると、柔らかい水草の新芽をかじってしまうことがあります。
小型水槽ではすぐにコケを食べ尽くし水草を食害してしまうことがあるため、ヤマトヌマエビを導入する場合は、コケの生える範囲が広い大型水槽の方が良いでしょう。
■ミナミヌマエビが向いた水槽

続いてはミナミヌマエビの導入が向いている水槽について。
当てはまる条件としては、
- 水槽内で繁殖させたい
- あまり目立ってほしくない
- 小型~中型水槽に導入したい
といったポイントが挙げられます。
ヌマエビを水槽内で繁殖させつつ世代交代していきたい場合は、通常の淡水水槽でも繁殖が容易なミナミヌマエビを導入するのがおすすめです。
また、クリーナー生体をあまり目立たせたくない場合も、サイズが小さいミナミヌマエビを選ぶのが良いでしょう。
導入予定の水槽が小型~中型であれば、コケが生えるスピードとミナミヌマエビがコケを食べる能力がバランス良く釣り合います。
大型水槽のクリーナー生体としてミナミヌマエビを導入するとなるとかなりの数が必要ですし、大型魚と混泳させる場合は食べられてしまう可能性があるため注意しましょう。
どうしても大型魚のいる水槽にミナミヌマエビを入れる場合は、水草を密生させるなどして身を隠すことができるように工夫をすれば、混泳が成功する可能性はありますが、食べられてしまう事を覚悟したうえで行ってください。
ヌマエビの餌は何をあげるの?
他の生体と一緒にヌマエビを飼育する場合、ヌマエビにも餌やりをする必要があるのか悩んでしまう事があります。
結論から言うと、コケの豊富な環境であったり、他の魚の残り餌があったりなど、食べ物が豊富な環境では、あえてヌマエビに餌を与える必要はありません。
しかし、コケは食べれば減っていきますので、水槽内がきれいになって餌が不足していると感じられる場合は、ヌマエビにも餌やりをしましょう。
ヌマエビ用の餌は専用のものが販売されていますし、コリドラス用やザリガニ用のものでも代用が可能です。底にいるヌマエビに届きやすい沈下性のものを与えましょう。
ただし、他の魚と同じくヌマエビに餌を与える場合も、餌の与え過ぎには注意してください。
餌の食べ残しは水質悪化の原因となります。ヌマエビをクリーナー生体として導入したにも関わらずヌマエビの餌の食べ残しで水質が悪くなってしまっては、本末転倒です。
ヌマエビに餌やりをする場合は、
- 水槽内にヌマエビの餌となるもの(コケや食べ残しなど)がないか
- ヌマエビが餌を食べ残していないか
をよく確認しながら、必要な分だけを与えるようにすることが重要です。
また、ヌマエビは臆病な性格の個体が多いため、水槽に導入して数日~数週間は、混泳魚の存在に驚いて水草の影から出て来ないことがあります。
そのまま、餌を食べられずに餓死してしまう可能性があるため、水槽に導入したヌマエビがきちんと餌を食べられているかよく観察し、問題があるようならば原因を解消してあげましょう。
ヌマエビに最適な水草
ヌマエビを導入する水槽には、水草を入れてやるのがおすすめです。
水草はヌマエビにとって、隠れ家や万が一のときの非常食にもなります。
基本的にはどのような水草でも良いのですが、ヌマエビと特に相性が良いのは以下の6種類の水草です。
■ヌマエビと相性の良い水草
- アヌビアスナナ
- ウィローモス
- アナカリス
- ヘアーグラス
- リシア
- パールグラス
アヌビアスナナは丈夫で育てやすい水草ですが、成長が遅くてコケが付着しやすいので、ヌマエビにコケを食べてもらうことで、健全な成長が期待できます。葉や茎が硬いので、ヌマエビにかじられてしまう心配がないのもおすすめのポイントです。また、アヌビアスナナが順調に育てばヌマエビの隠れ家にもなるため、相性はかなり良いと言えるでしょう。
ウィローモス、アナカリス、ヘアーグラス、リシア、パールグラスに関しても、ヌマエビの隠れ家になるうえに、餌が不足している場合はこれらの水草を食べることで飢えをしのぐことが可能です。
上記に挙げた水草の中でも特にアナカリスは成長が早く、低光量でCO2の添加がない環境でも十分に育てることができます。
ヌマエビに多少食べられてしまっても、環境が整っていればしっかり成長しどんどん増えていくので、初心者でも育てやすくおすすめの水草です。
ヌマエビは水草の新芽を食べてしまうことがありますので、葉が硬く食べられづらい水草や、成長が早く食べられてもどんどん増えるような水草が向いています。食害を抑えるには、ヌマエビの餌が不足しないよう気を配ると良いでしょう。
■無農薬栽培の水草について
ヌマエビがいる水槽に水草を入れる場合は、無農薬栽培された水草を導入しましょう。
実はヌマエビを含む甲殻類は熱帯魚と比較すると薬物耐性が低いため、水草に残った農薬の影響で命を落としてしまう危険性があるのです。
また、無農薬栽培の水草でも、スネールやヒドラ、プラナリアなど、アクアリウムにおける有害生物や有害生物の卵が付着している可能性があります。
水草を水槽に導入する際は必ず『前処理』を行ない、水槽内への有害生物の侵入をしっかりと防ぎましょう。
■水草の前処理方法
水草にはスネールやプラナリアといったアクアリウム界の害虫と呼ばれる生き物が付着している可能性があるため、水槽へ導入する前にきちんと前処理をしておきましょう。
前処理の手順は以下の通りです。
- まずは目視で有害生物やその卵を確認する。
- 害虫をある程度除去したら、水道水で洗浄する。
- 最後に流水で洗い流す。
まずは購入した水草を目視でよく確認し、有害生物やその卵を見つけたら指先やピンセットで除去します。
かなり根気のいる作業ですが、害虫を水槽内へ持ち込まないためにも念入りに確認しましょう。
害虫の除去が完了したら、バケツに汲んだ水道水の中に水草を漬けます。
水道水には塩素が含まれているため殺菌効果が期待できますし、水に浸すことで残留していた農薬を除去することも可能です。
1時間に一度水を替えながら3~5時間ほど浸したり、もしくは1週間程度同じ水に漬けっぱなしにしながら、水草を水道水に浸しておきましょう。
上記の作業が完了したら、仕上げに水草を流水で洗い流してから水槽に導入します。
水草の前処理方法については以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
混泳水槽内でヌマエビだけが死んでしまう原因3つ

「混泳水槽でヌマエビを飼育していると、なぜかヌマエビだけが次々と死んでしまう」
このような現象に悩まれたことはないでしょうか。
ヌマエビ以外の魚は元気にしているのに、なぜかヌマエビだけが死んでしまう。
その原因としては主に、
- 水温差によるショック
- pH差によるショック
- 水の汚れ
といった理由が挙げられます。
以下からは混泳水槽内でヌマエビだけが死んでしまう原因を詳しく解説していきますので、よく確認しておきましょう。
■水温差によるショック
水槽への導入時や水換えのときには、水温を合わせることがとても大切です。
水温が急激に変化するとヌマエビがダメージを受けてしまうことがあるので、特に冬場は気をつけながら水温を合わせてあげてください。
もしヌマエビが水底で動きを止めて固まっている(前脚で食べ物をついばむ動作を停止している)場合は、要注意のサインです。
そのような様子が見られた際は、水温差が生まれないよう十分に時間をかけて慎重に水合わせを行ないましょう。
また、ヌマエビは酸欠に弱い一面があります。
水槽導入前の水合わせ時にはエアレーションを忘れずに行ない、ヌマエビの酸欠を防ぎましょう。
■pH差によるショック
ヌマエビを飼育する際は、水温だけでなくpHの変化にも気をつける必要があります。
水換え時や水槽導入時のpHの急変はヌマエビに大きなダメージを与え、命を落としてしまう原因にもなりますので、十分に時間をかけて丁寧に水換え・水合わせを行ないましょう。
特に水槽導入時には1~2時間程度かけながら、点滴法でゆっくりと水合わせするのがおすすめです。
■水の汚れ(硝酸塩濃度やアンモニア濃度)
「水温やpHに差が出ないように気をつけているのに、ヌマエビが命を落としてしまう」
このような場合は、飼育水が汚れてしまっている可能性が考えられます。
水槽の掃除をさぼっていると、水中の硝酸塩濃度やアンモニア濃度がみるみる上昇していきます。
これらの成分は生き物にとって有害なため、魚よりも水質に敏感なヌマエビにはダイレクトに影響が出て、最悪の場合は命を落としてしまうのです。
また、このように水が汚れた水槽では、ヒーターを入れていてもヌマエビが繁殖しない(急に卵を持たなくなる)といった現象が起こります。
「最近、ヌマエビが抱卵しないな」と思った方は、飼育水や底砂、ろ過フィルターが汚れていないか念入りにチェックしてみてください。
混泳に注意が必要な魚

ヤマトヌマエビとミナミヌマエビは優秀なクリーナー生体ですが、体の小さな甲殻類のため、魚に食べられてしまう可能性があります。
特にミナミヌマエビは小型なので、魚との混泳には注意が必要です。
さらにはミナミヌマエビがヤマトヌマエビに捕食されることもあるので、水槽に入れる際はどちらか片方の種類に統一するようにしましょう。
以下からはヌマエビと混泳させる際に注意が必要な魚種として、
■ヌマエビと混泳注意の魚種
- エンゼルフィッシュやシクリッド
- ベタやグラミー
- フグ類
- 金魚
これらの魚をご紹介していきます。
■エンゼルフィッシュやシクリッド

エンゼルフィッシュをはじめとするシクリッド類の食性は肉食性で、動物食性が強い種類が多いです。
これらの魚種は野生では甲殻類も好んで食べているので、飼育下ではヌマエビたちも食べられてしまう可能性があります。
エンゼルフィッシュをはじめとするシクリッドは気性が荒い場合が多く、口に入る生体であれば何でも捕食してしまう傾向が強いので、基本的には混泳は避けた方が良いでしょう。
■ベタやグラミー

ベタは主に上層を遊泳し、口も小さく、あまり泳ぎが得意でもないため、ヌマエビを捕食することはあまりありません。
しかしベタ自身は甲殻類が好物なので、ヌマエビを見かけると食べようと突っつきに行きます。
この行為がヌマエビにとってストレスとなり体調を崩す原因になりやすいので、基本的には混泳を避けた方が無難です。
また、グラミー類については、ゴールデンハニードワーフグラミーなどの小型の種類であればヌマエビとの混泳は成功しやすいです。
しかし、パールグラミーなどやや大型になる種類はヌマエビを捕食してしまうことがあるので、十分に注意しましょう。
■フグ類

アクアリウムで飼育される淡水フグとしては、ミドリフグやアベニーパファーが人気ですが、これらのフグ類も甲殻類が大好物です。
フグの餌として販売されているクリルは甲殻類の1種であるオキアミを乾燥させて栄養を付加したものですし、乾燥エビも好んで食べます。
そんなフグたちにとって、ヌマエビは美味しいご馳走として映ってしまうので、混泳させると積極的に捕食しようとしてしまうのです。
アベニーパファーは体長3cmほどにしかなりませんが、小型のミナミヌマエビや稚エビは容易に襲われてしまいます。
また、ヤマトヌマエビに関してもフグの存在に怯えてしまい、ストレスで衰弱することもあるので、フグ類との混泳も避けた方が良いでしょう。
■金魚

金魚は意外と大きくなりやすい魚で、15cm程度まで成長します。大きいものでは30cm程の大きさになることも。
そのうえ大食漢で雑食性のため、餌と認識した口に入る大きさのものは何でも食べてしまいます。
ミナミヌマエビはもちろん、やや大きめのヤマトヌマエビでも金魚の口に入れば捕食されてしまうので、混泳は不可能と言えるでしょう。
金魚はヌマエビにかかわらず、小魚やラムズホーンなどの貝類も口に入れば食べてしまいます。
そもそも金魚は草食性があり、水槽内に繁茂したコケを自ら食べることがあります。
しかし、ヌマエビのように細やかに美しくコケを掃除できることはありませんので、お掃除で美しさを保ちましょう。
まとめ:混泳水槽のエビはどちらがおすすめ?ヤマトヌマエビとミナミヌマエビを比較

ヤマトヌマエビとミナミヌマエビはコケ取り用のクリーナー生体として優秀な存在です。
しかし、甲殻類であるがゆえに魚類とは体の構造が異なるため、環境の変化には弱い一面があります。
クリーナー生体としてヌマエビを導入する際は、水温や水質の急変、飼育水の汚れなどに注意しながら飼育をしましょう。
メインで飼育している魚種との相性など、飼育環境で向き不向きがあります。
このコラムを参考にしつつ、ご自身の水槽環境と照らし合わせながら、適したヌマエビを選択してください。
ヌマエビについて良くあるご質問
ヌマエビとはどんな生き物ですか?
ヌマエビに向いている水草とは?
ヌマエビ一緒に飼育できる生き物とは?
ヌマエビは繁殖できますか?
ヤマトヌマエビは稚エビの育成が汽水環境でしかできないため、飼育下で繁殖させることはほとんどできないと言われています。
寿命を迎えた場合は、補充をして管理していきます。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談フォーム
お悩み相談フォーム