お祭りといえば屋台がつきもので、その中でも金魚すくいは子どもたちに人気があります。
しかし一般的に金魚すくいですくってきた金魚は、すぐに死んでしまうといわれていますよね。それにはきちんとした理由がありますが、金魚すくいですくった金魚を長生きさせるコツもあるんです。
今回は金魚すくいですくった金魚の持ち帰り方や、長生きさせるポイントなどについてお話していきます。
金魚すくいですくった金魚がすぐに死にやすい理由とは?
一般的にお祭りの金魚すくいですくった金魚は、弱くてすぐに死んでしまうと昔からよくいわていますよね。でもこれは必ずしもそうとは限りません。実際にお祭りの金魚すくいですくった金魚を40年近く育てたという例も存在します。
金魚すくいについてはこちらの記事も併せて読んでくださいね。
金魚の寿命は意外に長い
一般的に金魚の寿命は10年から15年ですが、この寿命は金魚すくいの金魚も同じです。ではなぜ金魚すくいの金魚が短命なのかというと、「強烈なストレス」が原因で寿命が短くなったり、金魚すくいのときにすでに病気にかかっていて死んでしまうことが多いといわれています。
金魚すくいの金魚はストレスで死にやすくなる!
金魚は産まれた場所からお祭り場所までの移動ですでにストレスを感じています。そして金魚すくいの出店の入れものには隠れる場所がなく、常に人の目にさらされている状態でポイ(金魚すくいの網)で追いかけ回されます。
これだけでも金魚には相当なストレスなのですが、すくい上げたときは空気中にいるのでほんの一瞬でも窒息状態になってしまいます。そして家まで持ち帰るときには袋の中にいるので、揺れが止まらず金魚の目が回ってしまうのです。
魚の飼育に慣れている人なら自宅に持ち帰ってから金魚が落ち着くまで静かにしておいたり、しっかりとトリートメントを行います。
しかし魚の飼育に不慣れな人や子どもたちは、水槽の中にいる金魚が動かなくて水槽を叩くなどしてしまうため金魚は強いストレスを感じて弱ってしまいます。また持ち帰る時点でストレスで弱っているために、寄生虫に寄生されたり病気になってしまっているものもいるのです。
金魚が強いストレスを受け続けるとどうなる?
金魚が長時間強いストレスを受けると、金魚の体の中でコルチゾールというホルモンが増えていきその結果、血糖値が上がったり白血球が激減してしまいます。
そのせいで金魚が弱ってしまい、体の表面についていた寄生虫やバクテリアといったものが急激に増えます。すでに弱っていた金魚なら、この寄生虫やバクテリアによって病気になって死んでしまうことも珍しくありません。
金魚の体は寄生虫やバクテリアに対抗しようと粘液を出しますが、この粘液が大量に出てしまうことで金魚のうろこなどを覆ってしまい、最悪の場合呼吸ができなくなって死んでしまうという結果になることもあるのです。
弱っている金魚をすくわないようにしよう!
健康で元気な金魚は動きが早いので、金魚すくいに慣れていない人はなかなかうまくすくうことができません。体力が落ち弱ってきている金魚は大人しく、動きも緩やかなので狙いやすい状態になっています。
これらのことを考えると金魚すくいのときは、すくうのが大変でも動きの速い元気な金魚を選ぶのがポイントとなります。
元気な金魚の見分け方や病気についてはこちらの記事をどうぞ。
金魚すくいですくった金魚の持ち帰り方は?
金魚すくいですくった金魚は、持ち帰りのときからなるべくストレスを減らすよう注意する必要があります。持ち帰りの時の注意点をいくつかまとめてみました。
金魚すくいについてはこちらの記事も参考にしてくださいね。
水は多めに入れてもらう
金魚すくいですくった金魚をもらうときは、水はなるべく多めに入れてもらいましょう。これはなぜかというと、持ち帰り用の袋の中で金魚がフンをしてしまった場合、水質が悪化してしまうためです。家に着くまでの間とはいえ、水質が悪化してしまうと金魚にストレスがかかってしまいます。
金魚をすくったらすぐに帰る
お祭りの最中に金魚すくいをする人は多いと思いますが、金魚すくいで金魚をもらったときはすぐに帰宅するようにしましょう。
ビニール袋に水を入れた状態では、外気温の影響を受けて水温の変化が激しくなります。そして金魚は水中から酸素を得ているので、長時間少ない水の中にいることで酸欠になってしまうこともあるからです。
帰宅するまでの時間が長くなるようでしたら、事前に携帯用のエアーポンプや、クーラーを用意しておくという対処をすることも考えましょう。
振動をあたえないようにする
金魚をもらってから帰宅までの間の振動は避けて通れないものです。電車や自転車などに乗っているときでも、金魚の入っている袋に振動は大小問わず伝わります。
また子どもが金魚の入っている袋を持っている場合には、前後に揺らしたり、振り回すこともありますよね。
いくら水中に入っていて硬いものにぶつかることがないといっても、水中にいる金魚はきちんと振り回されている状態や振動を認識し、ストレスを感じてしまいます。あまりに大きい揺れや長時間続く振動などは金魚にストレスを与え弱ってしまう原因になります。
すぐに水槽に入れない
前もって自宅にある水槽や、帰宅後にセッティングした水槽に金魚をすぐに入れるのはやめましょう。
金魚が今まで入っていた水の水温や水質が、新しい水槽のものと大きく異なる場合、金魚に大きな負担がかかってしまいます。
飼育する水槽に入れる前に、トリートメントを行うことで金魚の体力の回復やストレスの軽減を行ってあげることが大切です。
水槽に入れる前にしっかりとトリートメントを行おう!
金魚すくいですくった金魚はなるべくなら水槽に移す前に2週間くらいのトリートメントを行ってあげたほうが、死ににくくなりますよ。
トリートメントはとても簡単な方法で、金魚の体力の回復や、寄生虫、病原菌を殺すといった目的があります。
トリートメントのやり方
トリートメントをする際は飼育する水槽とは別の水槽かバケツなどの容器、塩、市販のカルキ抜きか、汲み置きしてカルキを抜いた水が必要になります。
やり方はとても簡単で、バケツにカルキ抜きでカルキを抜いた水か、汲み置きした水を入れます。このときに塩を入れるのですが、塩分濃度は0.5%になるようにします。塩の量は1リットルの牛乳パックに小さじ1(約5グラム)と覚えておくといいですよ。
金魚の入っている袋を20~30分トリートメント用の水槽に浮かべて水温を合わせます。そして少しずつ金魚の袋にトリートメント用の水槽の水を入れ、様子を見て大丈夫そうなら袋の口を水槽内に入れて、金魚が自分から袋から出るまで待ちましょう。
トリートメントの注意点
トリートメントの注意点としては、餌は最初の3日間は与えないという点です。4日目から少しずつ与えるようにしましょう。また水が汚れている場合には、水換えを行いますがこのときも塩水を入れ替えます。
金魚すくいですくった金魚を長生きさせるコツとは?
金魚すくいですくった金魚を長生きさせるコツは、トリートメント後にもいくつかあります。まずは基本的な金魚の飼育方法をきちんと知ることです。金魚を長生きさせるかのポイントをまとめてみましたので参考にしてください。
飼育する水槽はどんなものがいい?
基本的に金魚はとても丈夫な魚で、市販されているガラスの小さな金魚鉢、プラケースでも飼育することが可能です。極端な話でいえばどんぶりで飼育することも可能なんですよ。
しかしどんぶりや市販のガラスの金魚鉢などは水の量が少なく、すぐに水質が悪化してしまうので毎日水換えを行わなければならないというデメリットもあります。
金魚すくいですくった金魚を少しでも長生きさせたいと思うのなら、1~2匹くらいなら最低でも30センチの水槽は必要でしょう。
水槽の選び方やレイアウトについてはこちらの記事を参考にしてください。
金魚のストレスを軽減させる
お祭りですくってきて、自宅で飼育している状況でも金魚はストレスを感じることがあります。
金魚にとっては常に人の目にさらされることがストレスとなることもあるので、水草を入れたり、植木鉢を割ったものや石などで金魚が隠れることのできる場所を作ると、金魚のストレスが軽減されやすくなります。
また水槽を置く場所も人通りが激しい場所や、振動の多い場所だとストレスを感じてしまうことが多いです。そのため水槽は落ち着いた静かな場所に置くことをおすすめします。
金魚水槽におすすめの水草についてはこちらの記事を参考にしてください。
ろ過装置やエアーを使用い、こまめに水槽の掃除をする
金魚はとても大食漢なうえに何でも食べる雑食性の魚で、水槽内に生えたコケを食べることもあります。しかし大食漢ゆえに、そのフンの量も多いんです。フンや餌の食べ残しを放置しておくと水槽内にアンモニアなどの有害な物質が発生し、水質が悪化してしまいます。
おすすめはろ過と水中の酸欠を防ぐためのエアーを兼ね備えた投入式のエアーポンプです。ろ過とエアーの機能を兼ね備えていますし、お手入れも比較的楽に行うことができます。
しかしろ過装置だけに頼るのではなく、ある程度人の手でこまめにフンや餌の食べ残しを取り除いてあげる必要はあります。
金魚水槽のお掃除方法についてはこちらの記事をご覧ください。
金魚すくいですくった金魚は他の生物と一緒に飼える?
金魚はメダカなど口に入るような小さな魚などは食べてしまいますが、一緒に飼うことのできる生き物は存在します。もしも他の生き物と一緒に飼いたいという場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。
金魚すくいでゲットした金魚の扱い方とは?持ち帰りから飼育方法までまとめ
今回は金魚すくいですくった金魚の持ち帰り方や、長生きさせるポイントについてお話しました。意外に持ち帰り方法については全く考えていなかったという人が多いのではないでしょうか。
金魚すくいをするときは、なるべく弱っている金魚は避けるのが一番です。しかし元気な金魚は動きが素早く捕まえにくいためにすくえないといったこともあるかと思いますが、少しでも長生きしてもらいたいのなら弱って動きの遅い金魚ではなく、元気な金魚をゲットする必要があります。
金魚すくいですくった金魚は、縁あって自分の所に来たのだと思って、トリートメントやきちんとした飼育方法で少しでも長生きできるようにしてあげてくださいね。
水槽のプロが所属するサイト運営チームです。
淡水魚・海水魚・水槽設備やレイアウトのことまで、アクアリウムに関する情報を発信していきます!
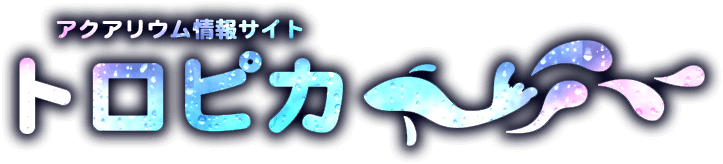
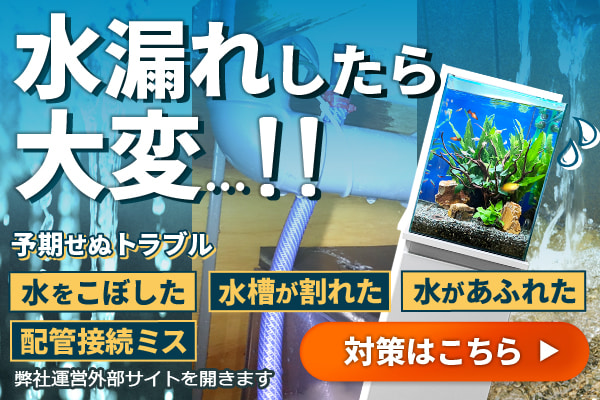




















![【金魚】国産 和金 3~4cm 10匹 [生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51qcjsoKdHL._SL500_.jpg)



コメント
大きい水槽がない、、
コメントありがとうございます。
水槽以外のプラスチック容器でも金魚は飼育可能です。こちらのコラムも是非ご参照ください。
・金魚は水槽以外で飼育できる!飼育容器の種類とメリット・管理ポイント
https://t-aquagarden.com/column/goldfish_breeding_container
※外部サイトが開きます