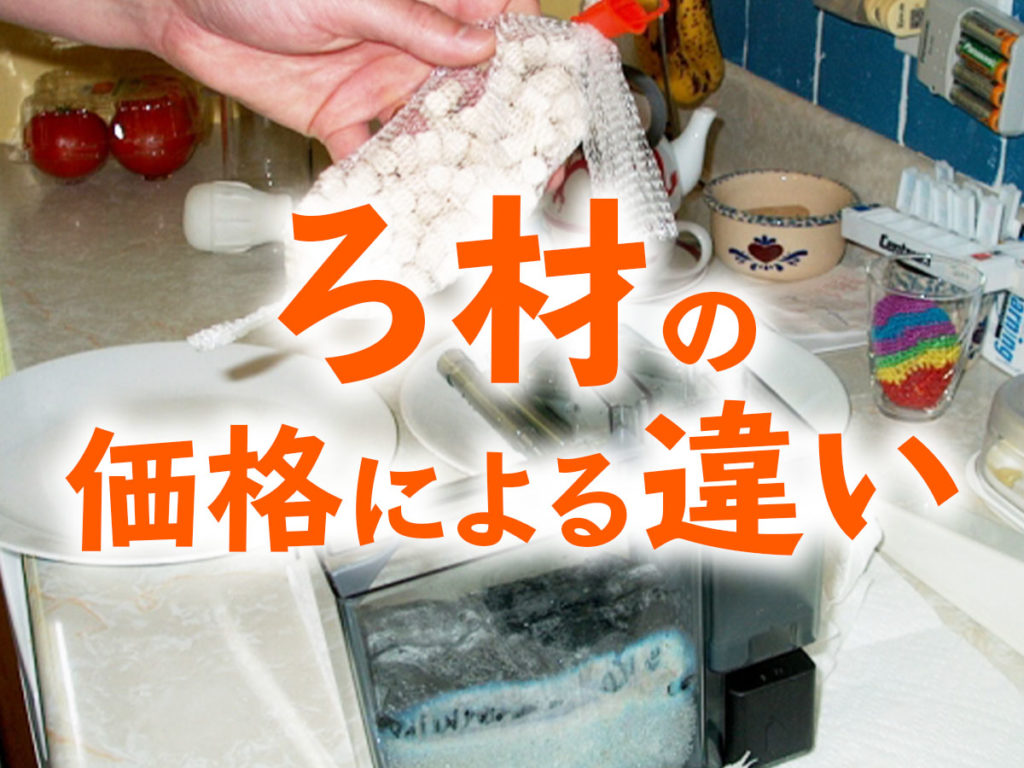水槽用ろ過材の交換や洗浄のタイミング!汚れたろ材のトラブルも解説
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
ろ過フィルターは魚の水槽飼育に欠かせない設備です。フィルター内にはろ過材を入れて水をきれいにします。
ろ過材には、ゴミをこしとるだけでなく、バクテリアの棲家になったり、濁り・臭いの原因となる物質を吸着したりといった様々な役割があり、ろ過材が汚れてしまうと本来の役割が果たせずに、いくらフィルターを稼働させても水の汚れが取れなくなってしまいます。
そればかりか、フィルターの汚れが飼育水に混ざり、不要な養分が水中に残ってしまうことも。それを防ぐために、ろ過材は定期的に洗浄、交換して綺麗な状態を保ちましょう。
ここでは、汚れたろ過材を使用し続けることによる危険性・トラブルや、ろ過材の交換・洗浄のタイミングなどについて解説します。
目次
プロアクアリストによるろ過材の交換や洗浄のタイミングの解説

このコラムは、東京アクアガーデンに在籍するアクアリストたちの経験・意見をもとに作成しています。
水のろ過を行う上でろ過材が果たす役割はとても大きなものです。ろ過フィルターが循環させた水をろ過材に通すことで水が綺麗になりますので、ろ過材は常に良い状態を保つようにしましょう。
東京アクアガーデンでは水槽の設置・メンテナンス業務を行っておりますので、ろ過材を交換したり、洗浄したりした方がよいタイミングを実務経験をもとに解説していきます。ぜひ、ご参考になさってください。
水槽用ろ過材の交換・洗浄のタイミングの見分け方を動画で解説!
このコラムの内容は動画でもご覧いただけます。
東京アクアガーデンではYouTube『トロピカチャンネル』でアクアリウム運用のポイントを随時公開中です。
今回の動画ではろ材を交換したり洗ったりすべき目安とはどんなことなのかを解説しています。
チャンネル登録を鎧くお願いいたします。
水槽用フィルター内で行われているろ過とは?

一口にろ過と言っても水槽用ろ過フィルターの内部では、
- 物理ろ過
- 生物ろ過
- 化学ろ過
この3つの工程が行われています。水質を維持するためにはろ過の種類を把握して、水槽の状況によってバランスよく取り入れることが重要です。
物理ろ過
ウールマットなどのろ材を用いて、食べ残した餌や排せつ物、水草の切れ端など汚れの原因となる大きなゴミを物理的に取り除く工程です。
これらのゴミはバクテリアに分解されると、熱帯魚などの生体にとって有害なアンモニアに変化します。可能な限り取り除くことで長期的に水質を維持しやすくなります。
生物ろ過
3つのろ過の内、最も重要になるのがこの生物ろ過です。
生物ろ過はバクテリアの働きにより、排せつ物などから生じたアンモニアを亜硝酸塩からより無害な硝酸塩へと変換する工程です。
一見きれいな水でも生物ろ過が不十分では、有害物質の濃度が高くなり生体がダメージを受けてしまうことがありますので、バクテリアを増やして健全な水質を維持しましょう。
バクテリアはろ過材の中に棲みつきます。バクテリアを十分に増殖させるには、棲家となる小さな穴がたくさん空いた多孔質なろ過材を使用するのがおすすめです。
化学ろ過
化学ろ過は濁りや臭いの原因となる微細な物質を取り除く工程です。活性炭などの少し特殊なろ過材を使用して、流木のアクなどの濁りや臭いの原因となる物質を吸着して取り除きます。
必須ではありませんが、水槽立ち上げ時などの水質がまだ安定していないときには重宝するろ過の方法です。
生物ろ過が十分に機能するようになれば、原因物質はバクテリアに分解されてアクや臭いも自然と収まるようになります。
ろ過材のメンテナンスを怠った際の危険性

フィルターの内部で行われている3種類のろ過についてご紹介しましたが、それらのろ過を可能にしているのはフィルター内部のろ過材です。
ろ過材は飼育水中のゴミをこし取り除去するため、使いつづけると目詰まりを起こして流量の低下を招き、生体に悪影響を与えることがあります。
ここでは、ろ過材のメンテナンス不足が招く危険性についてご紹介します。
ろ過材のメンテナンス不足が招く危険性1:止水域の発生
ろ過材のメンテナンス不足が招く危険としてまず挙げられるのが、止水域の発生です。
止水域とは、水の流れが悪く水槽の中で水が淀む場所のことを指します。排せつ物や残した餌などのゴミが溜まるだけでなく、溶存酸素濃度(水に溶け込む酸素の濃度)が低下することでバクテリアの活動が鈍くなり有害物質の分解を停滞させてしまうなど、水質を悪化させて病気を引き起こす可能性もある大変厄介な存在です。
止水域は、汚れが溜まって目詰まりを起こしたろ過材を使用し続けることで、ろ過フィルターの流れが悪くなり、フィルターの流量が低下することで発生しやすくなります。
メンテナンスを正しく行い、ろ過材の目詰まりを防ぐことが何よりの対策です。
ろ過材のメンテナンス不足が招く危険性2:飼育水全体の水質悪化
次に挙げらるのが、飼育水全体の水質の悪化です。これは生物ろ過を行うバクテリアの働きが弱まることで起こります。
バクテリアの活動には酸素が必要不可欠なのですが、ろ過材が目詰まりを起こして流量が低下すると酸素の供給が滞ります。ろ過材に大量に棲みついているバクテリアが酸素不足になると、活動が低下し、生物ろ過が十分に機能しなくなってしまうのです。
生物ろ過が十分に行われないと有害物質の分解が進まず、結果的に飼育水全体の水質が悪化してしまう可能性があります。ろ過材をメンテナンスして酸欠を防ぎ、バクテリアの活動を活性化させましょう。
ろ過能力と水流について

ろ過材のメンテナンスを怠ることで止水域が発生したり、水質が悪化したりすると解説しましたが、ろ過フィルター本来の水流にも着目しましょう。
ろ過能力を保つためには、水流が欠かせません。水が汚れるペースが早くろ過能力が足りないと感じる場合は、パワー(水流)がワンランク強い機種のろ過フィルターを選ぶと状況が改善することがあります。
水流が強いろ過フィルターであれば、
- 酸素不足でバクテリアの活性が維持できない
- 淀みによるトラブル(ゴミが溜まる・雑菌が繁殖するなど)
といった問題を防ぎやすくなります。
ろ過材交換のタイミングとは?

ここからは、ろ過材を交換するタイミングについてご紹介します。
基本的な考え方になりますので、細かいタイミングは製品によって異なります。また、使用環境にも左右されるため、商品パッケージなどに記載されている耐用年数なども合わせて参考にしてみてください。
ろ過材交換のタイミング1:ろ過材が崩壊してきたら
ろ過材の経年劣化は避けられない現象です。
ろ過材も使い続けると割れたり欠けたりして形が崩れていき、他のろ過材の目詰まりや、飼育水に破片が混ざる原因になります。ろ過材を掃除する際に目視で確認したり、触ってみたりしてひどく崩れているようであれば交換しましょう。
製品や環境によっても異なりますが、エーハイムのサブストラットプロなどの崩れやすいろ過材は3年が交換の目安です。
ろ過材交換のタイミング2:pHコントロール効果が弱まってきたら
pHを変化させる(維持しやすくする)効果のあるろ過材を使用している場合、時間の経過とともに効果が弱くなっていきます。
pHは試験紙や試薬で簡単に測定できますので、緩衝能力が弱まってきていれば交換の目安です。
ただ、pHを調節する方法は底床材の種類を変更したり、pH調整剤を使ったりなどの方法で対処することが基本です。pHをコントロールする能力の低下だけではなく、ろ過材の崩壊状態もふまえて総合的に交換時期を判断するようにしましょう。
ろ過材の洗浄法
太平洋セメントから発売されているパワーハウスなどの丈夫なろ過材は、洗浄することで繰り返し使用が可能です。
ろ過材を洗浄するタイミングは数週間から3カ月に1度程度の頻度で、水を汚しやすい熱帯魚ほどメンテナンスが必要な間隔は短くなります。
ろ過材は必ず飼育水を使って洗浄します。ろ過材には生物ろ過を行ってくれるバクテリアが定着していますが、水道水で洗ってしまうと、水道水に含まれる塩素(カルキ)によってバクテリアが死滅してしまう可能性があるからです。
ろ過材の洗浄は、バクテリアを保護しながら汚れだけを落とすことが重要となります。
また、バクテリアは酸欠や乾燥などにも強くありませんので、水槽の引っ越しや大掃除を行う場合は、ろ材をバケツに飼育水とともにいれて、エアレーションを行いましょう。
まとめ:水槽用ろ過材の交換や洗浄のタイミング!汚れたろ材のトラブルも解説

ろ過材は、ろ過フィルターの能力を左右する重要な部材です。
メンテナンスを怠ると目詰まりを起こして、本来のろ過能力を発揮できなくなってしまいますので、掃除を欠かさないようにしましょう。ろ過材を洗浄するときは、バクテリアに負担をかけないよう飼育水を使うのがポイントです。
ろ過には水流も重要ですので、ろ過材を目詰まりさせないことはもちろん、水流の強いろ過フィルターを使うのもおすすめです。ろ過材は製品や使用環境に適した頻度で洗浄や交換することで、ろ過能力を保ち水質の維持に貢献してくれます。
正しくろ過材のメンテナンスをして、健全な水質を維持しましょう。
ろ材の交換・洗浄について良くある質問
ろ材の汚れとは?
ろ材は多孔質ですが、それらの成分が蓄積していくと目詰まりをおこし、通水性が悪くなります。
水流が弱まる・バクテリアが酸欠になりやすくなるなどのトラブルにつながるため、定期的なメンテナンスを行いましょう。
ろ材を交換する目安とは?
- 水流が弱まってきた
- 水が濁っている
- ろ材が崩れている
- 水が臭う など
セラミックろ材なら洗浄して繰り返し使えますが、それ以外は交換します。ろ材が割れたり崩れている場合は、新しいものと交換しましょう。
交換時は、使っていたろ材を少量混ぜることで、バクテリアの定着が早まります。
ろ材の最適な洗浄方法とは?
化学ろ材は再利用ができないため、効果が無くなったら交換しましょう。活性炭は約1~2ヵ月、カキガラは約1~3ヶ月です。
ウールマットの交換目安とは?
汚れが蓄積したり、弾力性が無くなったら交換です。
ウールマットは物理的な汚れ(フンや枯れた水草など)を濾しとるためのろ材です。
汚れが溜まると水流を阻害しやすくなるので、汚れたらすぐに交換しましょう。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談フォーム
お悩み相談フォーム