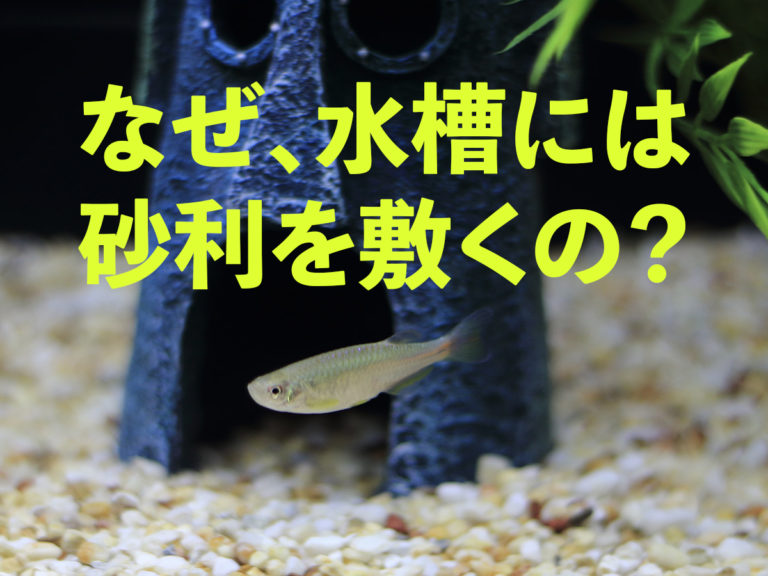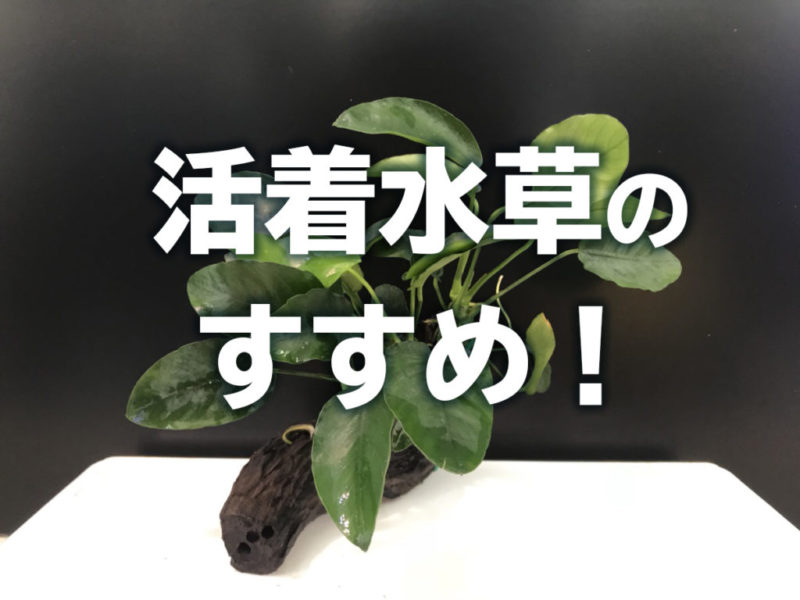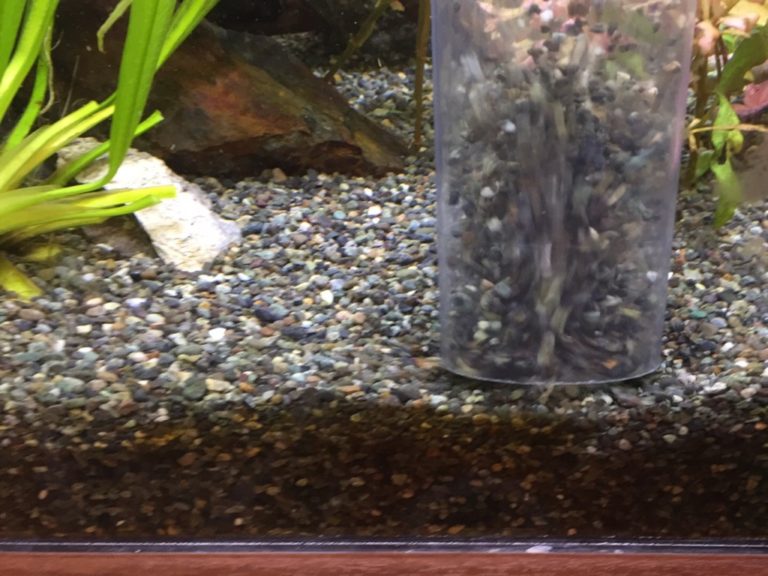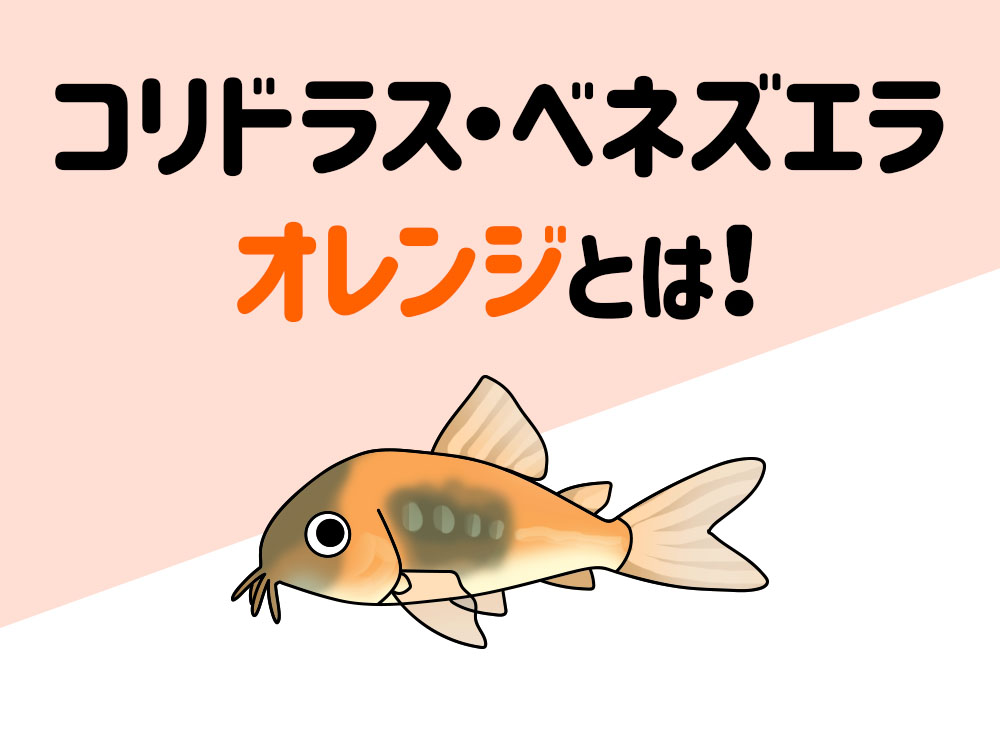クーリーローチの飼育方法!混泳、種類、寿命、底砂についてを解説
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
クーリーローチは東南アジアが原産のドジョウの仲間で、水質の変化に強く丈夫で飼育しやすい初心者にもおすすめの熱帯魚です。
水槽の下層域で生活する魚で、何でも食べる雑食性であることから、お掃除生体としてもよく導入されています。
お掃除生体というと脇役のように感じますが、クーリーローチはオレンジ色のカラフルな体色をしており、個体ごとに異なる模様が十分に目を楽しませてくれます。
ここでは、クーリーローチの飼育法や近縁種、混泳などについてご紹介します。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとにクーリーローチの飼育方法を解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
クーリーローチは非常に大人しい底もの(底棲魚)です。
ヘビのような体型からイメージされるよりも穏やかな性質を持っています。
このコラムでは、クーリーローチの飼育方法を解説します。
クーリーローチとは

長い体と縞模様が特徴で、つぶらな瞳が可愛い熱帯魚です。
まずは、特徴や近縁種などをご紹介します。
他の熱帯魚の飼い方はこちらのページで詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

特徴
クーリーローチはコイ目ドジョウ科に属するローチの1種です。タイやインドネシアなどの東南アジアに分布しており、流れの穏やかな河川や池沼に生息しています。ドジョウ科に分類されているだけあって日本産のドジョウとよく似ており、細長い円筒状の体で口先には数本のヒゲを持ちます。
体長は最大で10cm前後ですが日本のドジョウよりも細長い体型で、体色はオレンジ色を基調に黒色の模様が入ります。
性格は大人しく、やや臆病で夜行性ということもあり、日中は砂の中や物陰に身を隠しています。
食性は何でも食べる雑食性で、生活圏が下層域であることから食べ残しを食べるお掃除生体としても導入されることがある魚種です。寿命は5~10年ほどと長めなので、最後まで面倒を見られるかどうか、よく検討したうえで飼育してください。
近縁種
クーリーローチには近縁種がいくつか確認されており、輸入の段階で混ざることが多く区別されずに販売されることもあります。
ここでは、国内でクーリーローチの仲間として扱われていることがある、主な近縁種をご紹介します。
ブラッククーリー・ローチ
東南アジアに広く分布しているローチの1種です。
体長は最大で8cmほどとクーリーローチと比較するとやや小型で、全身が黒一色の姿をしています。
ジャイアントクーリー・ローチ
タイからカンボジアにかけて分布しているローチの仲間です。
クーリーローチと比較すると体高が高いことが特徴で、「ジャイアント」と名付けられていますが、体長自体はクーリーローチと同等です。
パンギオ・シェルフォルディ
近年になって輸入され始めた品種で、クーリーローチよりも細かな模様が入ることが特徴です。
輸入量自体が少なく、あまり流通していないのでショップなどで見かけることは希です。
クーリーローチの飼育法

水温・水質
クーリーローチを飼育できる水温は20~28℃ですが、低温では白点病が出やすいので、25℃前後に保った方が良いでしょう。
夏と冬はそれぞれ温調機器を用いて保温してください。
水質に関しては適応できる範囲が広く、pH6.0~7.0程度までの弱酸性から中性で飼育が可能です。特に弱酸性の軟水を好み、適した水質で飼育すると発色が良くなることが知られています。
しかし、pH5.5を下回ると他の大部分の熱帯魚にとって良くない水質となるので、混泳させる場合は注意してください。
水槽・ろ過フィルター
底棲魚なので、床面積がそのまま飼育スペースにります。
最適な水槽のサイズは幅が60cm以上のものです。他の生体との混泳を考えないのであれば、高さが低い水槽でも問題ありません。
ろ過フィルターに関しては、60cm水槽ならば、上部式や外部式をおすすめします。
底面フィルターで飼育することもありますが、クーリーローチが好む、潜りこめるような細かい砂を底床材は底面式フィルターには不向きです。
砂がフィルター内部に入り込み、ろ過能力が低下してしまいます。
その点から、水草を育てるのであれば外部フィルター、生体飼育をメインにするなら上部フィルターがおすすめです。
底砂
クーリーローチは砂に潜る性質を持つので、底砂は導入してあげた方がストレスの少ない飼育環境を作れます。砂に潜る様子を観察したいのであれば、砂粒が小さくて軽い『ボトムサンド』や『田砂』などを高さ5cm以上に、厚めに敷くと良いでしょう。
砂が尖ったり角ばっていると、クーリーローチが怪我をしてしまうので注意してください。熱帯魚用に販売されている底砂ならば、角が鋭利な物は無いように選別されているので安心して使用できます。
メンテナンス性を考慮して底砂を厚く敷きたくない場合は、サンドよりも粒が大きい「大磯砂」などの砂利でも問題ありません。
しかし、大磯砂には潜ることができません。シェルターや石組みなどで隠れられる場所を作ってあげると落ち着きます。
一方で、水の硬度を上昇させてアルカリ性に傾けるサンゴ砂や、物理的な力(=クーリーローチが潜る力)で崩れやすいソイルは、クーリーローチの飼育では不向きです。
エサ
クーリーローチは雑食性なので、エサは何でもよく食べてくれます。人工飼料を中心に、たまに冷凍アカムシなどの生餌を与えると、栄養バランスも良くなり大きく育ちます。
人工飼料はコリドラスなどの底棲魚用に配合された沈下性のものを与えましょう。
与え方は1日に1~2回、食べ残さない量を与えます。生餌を与えるときはスポイトで撒くか、底棲魚用のエサ入れを使うと便利です。
また、クーリーローチは夜行性なので、消灯時間の前にエサを水槽に入れておくと良いでしょう。食べ残したエサは水を汚す原因になるので、翌日に限り取り除いてください。
クーリーローチの混泳について

クーリーローチは穏やかな性質から、様々な魚種との混泳に向いています。
ここでは、混泳に向いている生体と水草との相性について解説します。
熱帯魚との混泳
クーリーローチは非常に温和で、なかには臆病な側面を持つ個体もいます。
自ら攻撃を行うことはほとんどないので、クーリーローチを攻撃しない魚種であれば、様々な魚と混泳が可能です。
混泳相性が良い魚種の例としては、プラティやメダカ、カラシンやアカヒレに加え、オトシンクルスやコリドラス、小型のプレコやローチなどが挙げられます。
同種や近縁種との混泳は、数匹のグループで飼育した方が、落ち着くので問題ありません。
ただし、『クラウン・ローチ』などローチの仲間でも大きく気性が荒くなる品種は避けましょう。
テトラなど、上層を遊泳する魚種とは相性良好です。
他に注意する生体としては、遊泳層が重なるプレコも気性が荒く成長する品種が多いです。
混泳させたい場合は、『ブッシープレコ』など小型のプレコに限定するのがおすすめです。
水草との混泳
クーリーローチは底砂を掘る性質があるので、根張りが弱い水草は抜けてしまうことがあります。
また、底砂に直接水草を植えてしまうと、底砂のにコツが必要になりますし、クーリーローチがくつろぐスペースが減ってしまいます。
そのため、水草と混泳させたい場合は流木などに活着させたものや、鉢などに植えた状態で導入すると良いでしょう。特に流木に活着させたものを組み合わせると隠れ家にもなり、流木の効果で水質も弱酸性傾向になるのでおすすめです。
活着させやすい種類としては、アヌビアスナナやウィローモス、ミクロソリウムなどが挙げられます。
レイアウトとメンテナンスについて
クーリーローチは臆病な魚種なので、隠れられる場所がないとストレスを受けてしまいます。砂に潜れる状態であっても、シェルターや石組み、水草などで身を隠せる場所は豊富に作ってあげてください。
また、クーリーローチは日本産のドジョウと同様に、時々水面に呼吸をしに来ます。その際に、水槽から飛び出す事故が起こり得るのでフタは必ずしてください。
そして、クーリーローチの飼育では底砂のメンテナンスは大変重要です。
同種は比較的に丈夫な魚種ですが、汚れた底砂で飼育していると尾ぐされ病などの病気にかかりやすくなります。
底砂の掃除には市販の底砂クリーナーを用いると手間が省けるので、定期的に底砂の掃除を行い、適した飼育環境を保つようにしてください。
まとめ:クーリーローチの飼育方法!混泳、種類、寿命、底砂についてを解説

クーリーローチは丈夫で飼育しやすいため、アクアリウムの入門種としても適しています。
その性質からお掃除生体として導入されることもある魚種ですが、カラフルな色合いと個体ごとに異なる模様から、鑑賞性も高いです。
砂に潜る様子や顔立ちが可愛らしく、性格も穏やかで混泳しやすいです。
これからアクアリウムを始めようとしている方や、下層を彩るタンクメイトをお探しの方は、クーリーローチをぜひ検討してみてください。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談フォーム
お悩み相談フォーム