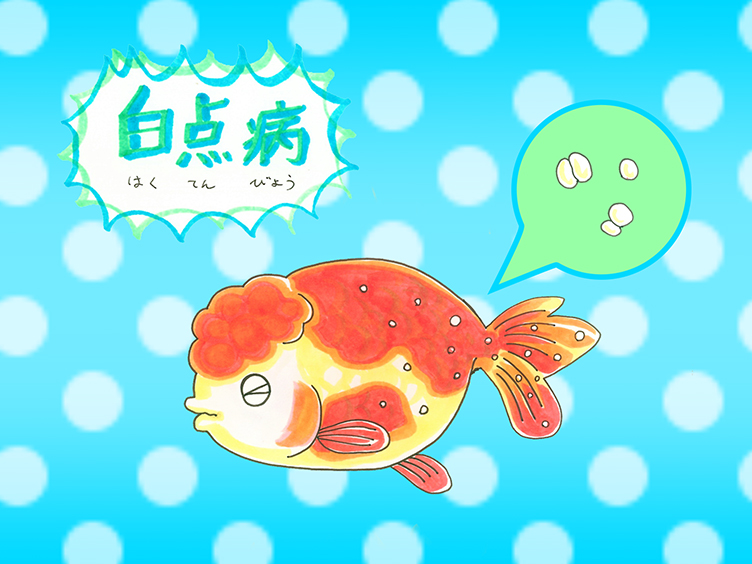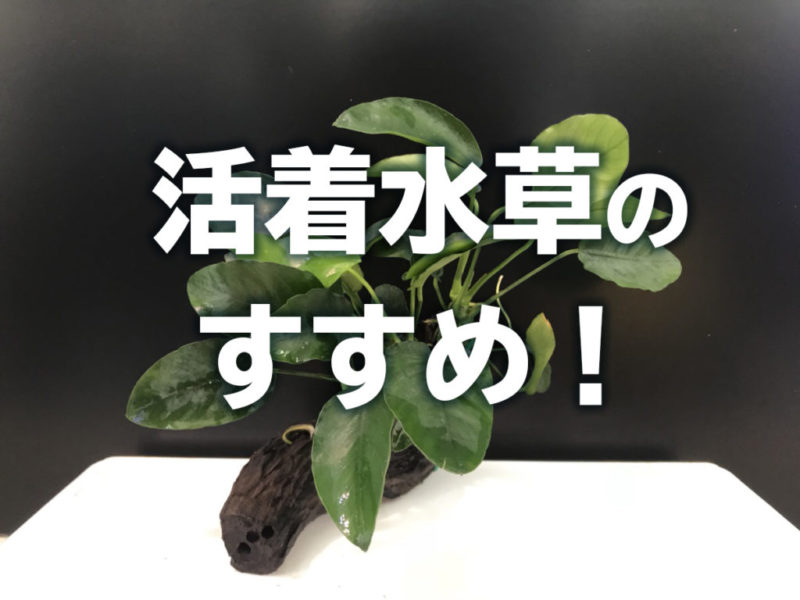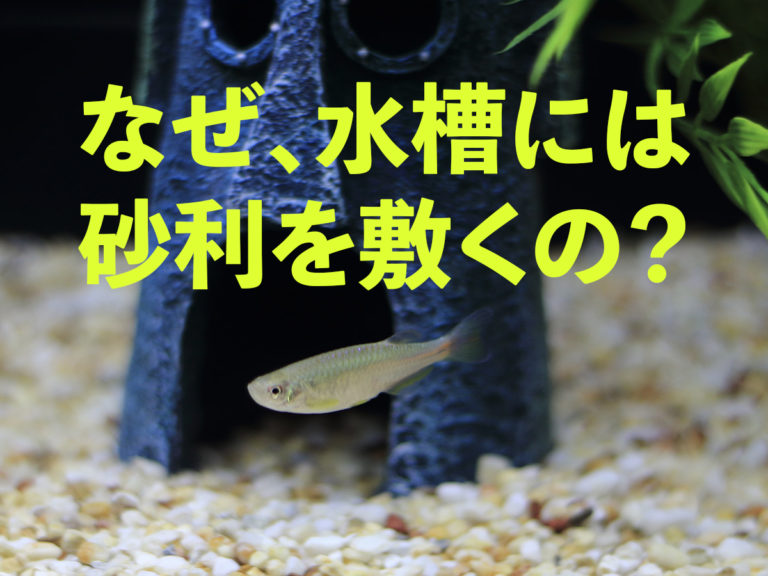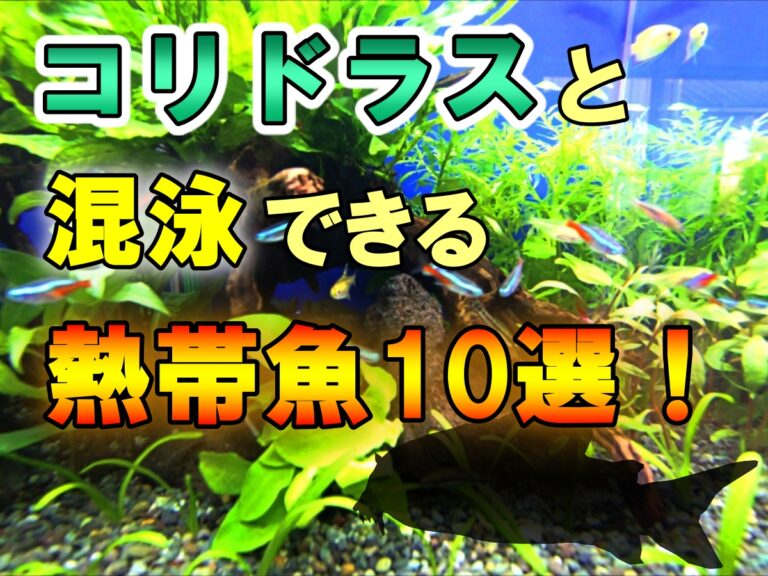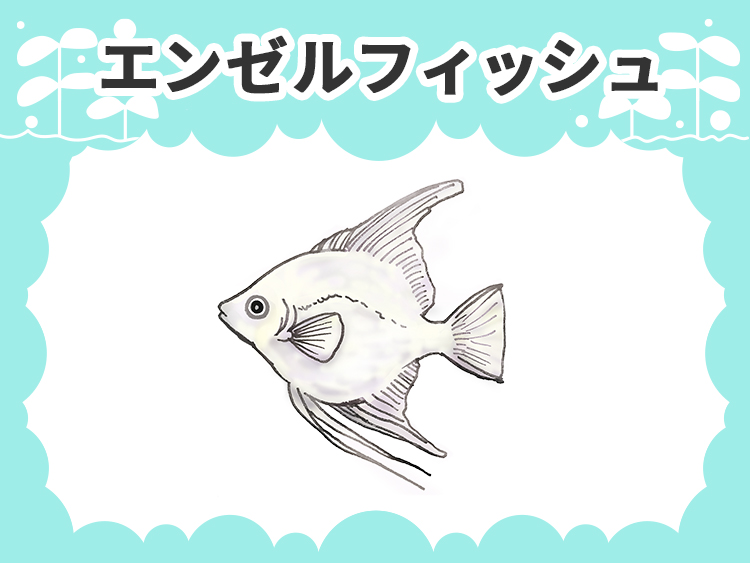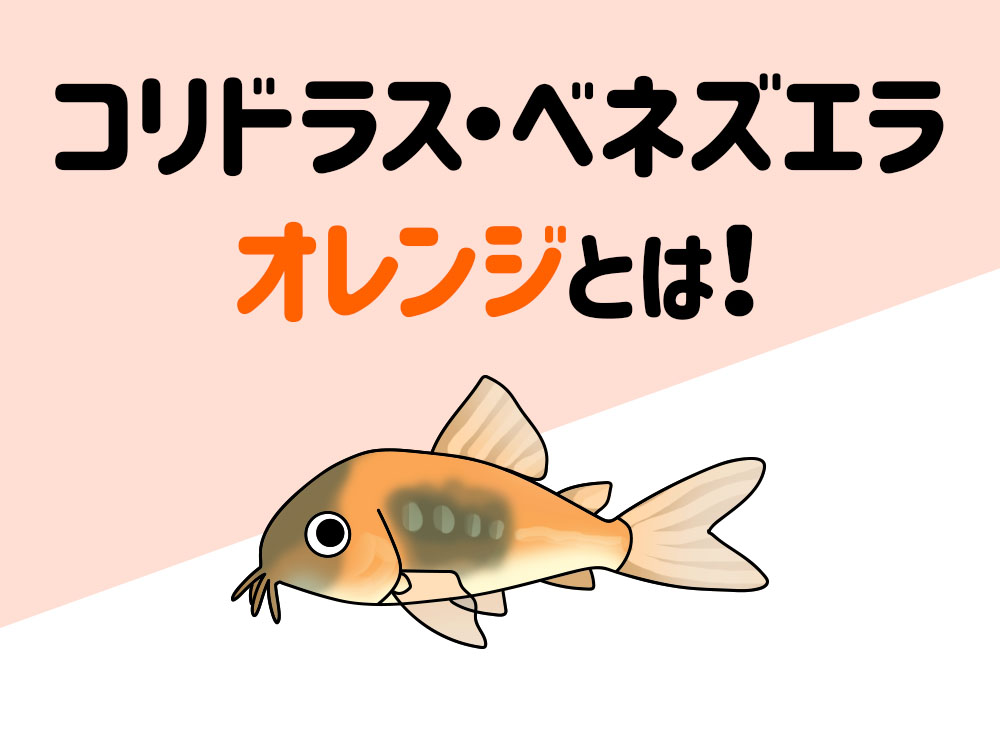エンゼルフィッシュの飼育方法!品種や水槽、餌などから繁殖まで解説
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
エンゼルフィッシュはアクアリウム用品のパッケージに描かれることも多い、熱帯魚の代表種です。
特徴的なフォルムは古くから人々の心を魅了し、現在までに様々な改良品種が作出されています。
改良品種は水質への適応力も高く丈夫なため、飼育しやすい熱帯魚とし親しまれています。
また、専用の水槽は必要になりますが、繁殖も可能です。
エンゼルフィッシュについて飼育法や混泳、繁殖法などをご紹介します。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとにエンゼルフィッシュの飼育方法を解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
エンゼルフィッシュはユニークなプロポーションと優雅な泳ぎで、大型水槽での飼育にも向いている人気魚種です。
東京アクアガーデンの水槽でも飼育を行っており、実際に飼育してみるとツンとした印象とは違う人懐っこさが可愛らしく、愛着がわきます。
ここでは、エンゼルフィッシュの飼育方法を解説します。
エンゼルフィッシュとは

特徴
エンゼルフィッシュはスズキ目シクリッド科に属する淡水魚の1種です。強く側扁した菱形の魚体に、長く伸長した背ビレと腹ビレ、尻ビレを持つ独特のフォルムが特徴です。
体長は最大で15cmほどで、改良品種は色と模様がバリエーションに富みますが、ワイルド種は褐色を帯びた銀白色の体色を基調に黒色の縞模様が入ります。
アマゾン川水系に広く生息しており、ペルーやコロンビアなど南アメリカ大陸の北部を中心に分布しています。水流が穏やかな場所を好み、食性は小魚や甲殻類、昆虫類などを捕食する肉食性です。
寿命
エンゼルフィッシュの寿命は約5~6年ほどです。
最適な飼育環境を作り上げた場合は、10年以上も生きると言われています。
比較的寿命が長い熱帯魚なので、適切な飼育環境を整えてやり、最後まで可愛がりましょう。
エンゼルフィッシュの種類・改良品種
アルタムエンゼル

エンゼルフィッシュの原種の1つで、アマゾン川の支流であるネグロ川やオリノコ川に生息しています。
原種の中では背ビレと腹ビレ、尻ビレが大きく伸長する、美しいプロポーションが特徴です。
同時にアルタムエンゼルは、非常に飼育が難しいことでも有名です。
水質にデリケートで、菌やウイルスに対する抵抗力も弱く、アクアリウム上級者でも手こずることがあるほどの飼育難度です。
繁殖も難しく、飼育下での成功例はほとんど確認できません。
それでも、成長すると体高は30cmにもなり、美しさはエンゼルフィッシュのなかで随一と愛好されています。
アクアリストなら一度は憧れるエンゼルフィッシュです。
スカラレエンゼル
こちらのエンゼルフィッシュも原種の1つで、アマゾン川流域に広く生息しております。
原種ではありますが、飼育難度は容易で繁殖も楽しめます。
ほとんどの改良品種が、もとはスカラレエンゼルから派生したともいわれています。
また、ペルー原産のものはプロポーションが良いことで有名で、ペルーアルタムと呼ばれ、人気の高い種類です。
ワイルド種の中で流通量が最も多い品種がこのスカラレエンゼルです。
ブルーエンゼルフィッシュ
改良品種の1種で、銀白色の体色を基調に光の当たり具合で、青色の発色が強くなる美しい品種です。
一昔前まではかなりの高値がついていましたが、現在では安定してブリードされており、価格も落ち着いています。
この種類は繁殖も楽しむことができます。
こうした、原種にはない体色を持つ改良品種も増えています。
プラチナホワイト・エンゼルフィッシュ
改良品種の1種で、全身が白色でプラチナ色に輝くエンゼルフィッシュです。原種に特徴的だった縞模様は見られません。個体によってはヒレが青色を帯びることもあります。
改良品種ですがやや水質の変化に弱い傾向があります。
しかし、容量のあるろ過フィルターを採用し、こまめな水換えを行えば長期飼育も行うことができます。
ベールテール・エンゼルフィッシュ

改良品種の1種で、ベールテールタイプのエンゼルフィッシュです。ベールテールとは各ヒレが長くなるように改良された品種のことを指します。長いヒレがエンゼルフィッシュのプロポーションを引き立てる華やかな品種です。
このようなロングフィンタイプの熱帯魚は、一般的に泳ぎが苦手です。
さらに、ヒレを傷つけてしまうリスクも大きく上がりますので、導入する際は大きめの水槽を用意しましょう。
エンゼルフィッシュの飼育に必要な器具類

エンゼルフィッシュの飼育には、下記の道具が必要です。
- 水槽
- ろ過フィルター
- 水槽用照明
- エアレーション
- 水槽用ヒーター
- カルキ抜き剤
- 餌
この中で、特に注意が必要なものをご説明します。
水槽
エンゼルフィッシュは成長すると体長10~15cmほどになるので、水槽のサイズは最低でも45cmは必要です。
そして、このサイズで飼育できるのは成魚1匹までです。2匹以上の成魚を飼育する場合は、60cm水槽以上が推奨です。
90cm水槽であれば5匹前後を同時に飼育できます。
また、エンゼルフィッシュは体高が高く、ヒレが上下に伸長します。
その美しいプロポーションを保つためには水深が重要で、推奨される水槽の高さは45cm以上です。
肉食性が強いので水を汚しやすいため水質維持の点からも、大きな水槽での飼育に向いています。
ろ過フィルター
ろ過フィルターは『上部式』と『外部式』がおすすめです。
- 水草を育成したい場合 → CO2を逃がしにくい外部式
- 熱帯魚のみで飼育する場合 → メンテナンスが簡単な上部式
このように、水槽のレイアウトによって、機種を選ぶのが良いです。
エンゼルフィッシュは水を汚しやすい熱帯魚なので、フィルターはろ過能力が高いものを使用しましょう。
ただし、エンゼルフィッシュは水流が苦手ですので、吐出口の向きなどを調整するのが良いです。
エンゼルフィッシュの飼育方法

水温・水質
エンゼルフィッシュを飼育できる水温は22~32℃前後です。
急激な変動でなければ、幅広い水温に適応できますが、低温域では「白点病」のリスクが高くなるので、年間を通じて25℃以上に保つことを推奨します。
エンゼルフィッシュが好む水質は、pH5.5~7.0の弱酸性から中性の軟水です。
成魚は環境の変化に比較的強いですが、幼魚期は水質変化に弱いです。
幼魚を水槽に導入する際は、水合わせをしっかりと行いましょう。
餌
エンゼルフィッシュは肉食魚なので餌も生餌を与えると良く食いつきます。
しかし、生餌は水を汚しやすいので、普段は肉食魚用の人工飼料を与えて、たまに生餌を与える程度にした方が良いでしょう。
生餌は、冷凍保存できるタイプが管理しやすく、おすすめです。
とはいっても、比較的選り好みせず何でも食べてくれます。
与え方は1日に1~2回に分けて、5分程度で食べきれるだけの分量を与えてください。
食べ残しは水質を悪化させます。
給餌量を調節しながら、食べ残した餌はできるだけ排出しましょう。
水槽レイアウト

エンゼルフィッシュは長くたなびく美しいヒレを持っています。
水槽内のレイアウトを複雑にしてしまうと、せっかくのヒレを引っ掛けてしまって傷が付くことがあります。
葉の硬い水草や複雑に伸びる枝流木、角のある石などは要注意です。
レイアウト作りに慣れていない場合は、なるべく柔らかい水草を選び、シンプルなレイアウトにすると良いでしょう。
シンプルなレイアウトでも、エンゼルフィッシュの存在感で、十分きれいな水槽に仕上がります。
アクアガーデンでは、遊泳できるスペースを確保するレイアウトを行っています。
水槽の水流について

エンゼルフィッシュはもともと、川というよりはため池に近いような止水域に生息する熱帯魚です。
そのため、エンゼルフィッシュは水流を嫌います。
ろ過フィルターの排水やエアレーションにより、強い水流が生じないように配置には注意してください。
エンゼルフィッシュの扁平な体は、わずかな水流でも強い影響を受けてしまいます。
水流が強いと、それだけでストレスになるだけでなく、体力を消耗し弱ってしまいますので気を付けましょう。
水槽メンテナンスについて

メンテナンスの内容は他の熱帯魚と同様に、水換えと水槽内部および周辺機器の掃除です。
エンゼルフィッシュはフンの量が多いので、底床材の掃除はしっかり目に行います。
エンゼルフィッシュのみでの飼育や、上層から中層を泳ぐ熱帯魚と混泳させる場合であれば、ベアタンクでの飼育でも問題ありません。
しかし、水槽の下層を泳ぐ底棲魚と混泳させる場合は、底床材があった方が良くなります。
混泳生体によって適宜敷くのがおすすめです。
水草で水槽内をレイアウトする場合、通常はソイルを使用することが多いですが、掃除の度に粒が崩れやすいというデメリットがあります。
そのため、フンの多いエンゼルフィッシュの水槽には、あまり向いていません。
エンゼルフィッシュの水槽には大磯砂など頻繁な底床クリーニングに耐えられる種類を敷きます。
水草を楽しみたい場合は、流木や石などに活着させて配置するのがベストです。
混泳について

エンゼルフィッシュは縄張り意識が強いので、混泳には注意が必要です。
エンゼルフィッシュ同士で小競り合いをすることも珍しくなく、特にオス同士は相性が合わないことが多いのです。
複数匹で飼育する場合は十分に広い水槽を用意するか、いつでも隔離できる準備をしておきましょう。
他種で混泳相性が良い魚種は、エンゼルフィッシュに捕食されない程度の大きさで、エンゼルフィッシュを攻撃しない温厚な種類です。
相性のいい魚種1:ドワーフグラミー
ドワーフグラミーなどの小型グラミーはエンゼルフィッシュのと混泳に向いています。

エンゼルフィッシュに食べられない大きさで、かつ非常に温厚な性格のドワーフグラミーは、相性の良いタンクメイトと言えるでしょう。
相性のいい魚種2:テトラ(カラシン)類
ラミーノーズテトラ、ネオンテトラなどのカラシン類も、エンゼルフィッシュとの混泳が可能です。
これらカラシンの仲間は、エンゼルフィッシュと比べると泳ぎが早いため、エンゼルフィッシュの攻撃から逃れることができます。
ただし、もちろん食べられてしまうことは十分に考えられるので、混泳させるときはエンゼルフィッシュの口に入らないサイズまで成長した個体を選びましょう。
相性のいい魚種3:コリドラス
コリドラスなど、遊泳域が違う魚種もおすすめします。
やや上層寄りの中層を泳ぐエンゼルフィッシュが、底床付近を泳ぐコリドラスと出会うことは、ほとんどありません。
エンゼルフィッシュがちょっかいを出しにくい魚種です。
相性の良くない生き物1:ベタ・グッピー・プレコなど
一方で、ベタやグッピー、プレコなどとは相性が良くありません。
ベタやグッピーは泳ぎが遅いため、エンゼルフィッシュの格好の攻撃の的になります。
グッピーくらいのサイズだと、食べられてしまいます。
また、プレコは岩などに生えたコケを舐めとりますが、エンゼルフィッシュの体表も舐めとってしまうことがあります。
エンゼルフィッシュは皮膚が弱いため、それが原因で死んでしまうこともあります。
「舐めとる」とはいいますが、正確には齧る行為ですので、大変危険です。
これらの魚種とは混泳させないようにしましょう。
相性の良くない生き物2: エビ類
そして、エビ類はエンゼルフィッシュの好物なので混泳は不可です。
すぐに食べられてしまうので、絶対に混泳させないようにしましょう。
また、一般的に相性が良いとされている熱帯魚でも、サイズ差が大きいとエンゼルフィッシュに捕食される場合があるので注意してください。
エンゼルフィッシュの繁殖

一部の原種を除くエンゼルフィッシュの繁殖は容易で、適した飼育環境を維持していれば、特別に水質などを調整しなくとも産卵を行います。
ここでは、エンゼルフィッシュの繁殖法をご紹介します。
産卵まで

産卵させるためには、まずペアを作ります。
エンゼルフィッシュの雌雄の見分けは外見では困難なので、大きめの水槽で複数匹を飼育して、ペアが自然に形成されるのを待ちましょう。
そのため、繁殖を狙うのであれば90cm以上の水槽が必要です。
2匹が寄り添って泳ぎ、周囲の個体を追い払うような行動が見られれば、ペアが成立した確率が高いです。
繁殖期のエンゼルフィッシュは気性が荒くなるので、ペアが成立したら繁殖用の水槽を別に作り、ペアを移動させてください。
繁殖用の水槽は、60cm水槽で問題ありません。
産卵から孵化まで
エンゼルフィッシュは野生では水草などに卵を産み付けるので、繁殖用の水槽内にも産卵床を導入してください。
産卵床は葉がしっかりとしたアマゾンソードなどの水草や流木、パイプなどでも代用できます。
産卵後は、親魚が孵化まで面倒を見てくれるので、静かに見守りましょう。
しかし、若いペアなどでは食卵する場合があるので、その時は隔離してください。
隔離した卵は十分にエアレーションを効かせた環境で、弱い水流を当てるようにして水カビが生えるのを防止しつつ、孵化まで待ちましょう。
稚魚の世話
卵は2~3日で孵化して稚魚が誕生します。
稚魚はヨークサック(卵嚢)が付いた状態で生まれ、1週間ほどでヨークサックの栄養を吸収し終え、遊泳できるまでに成長します。
ヨークサックがある間は餌を与えても食べないので、餌を与える必要はありません。
餌を与えるタイミングとしては泳ぎ出してからで、餌はブラインシュリンプを与えます。
稚魚は成長のために養分をより多く必要とします。餌は1日に最低でも2回に分けて与えると、成長が促進されて死亡率が高い時期をより早く抜けられます。
生後1カ月も経過すれば体高も高くなり、親魚と同様の姿に成長するので、以降は通常の飼育法に切り替えても問題ありません。
まとめ:エンゼルフィッシュの飼育方法!品種や水槽、餌などから繁殖まで解説

エンゼルフィッシュは熱帯魚の代表種で、その独特のフォルムや模様から高い鑑賞性を持ち、長い間アクアリウムの世界で親しまれてきた魚種です。
原種の飼育難易度は高いものの、改良品種は飼育や繁殖も容易なことから、アクアリウム歴が長くない方にもおすすめです。
水槽にインパクトが欲しい場合など、是非、飼育を検討してみてください。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談フォーム
お悩み相談フォーム