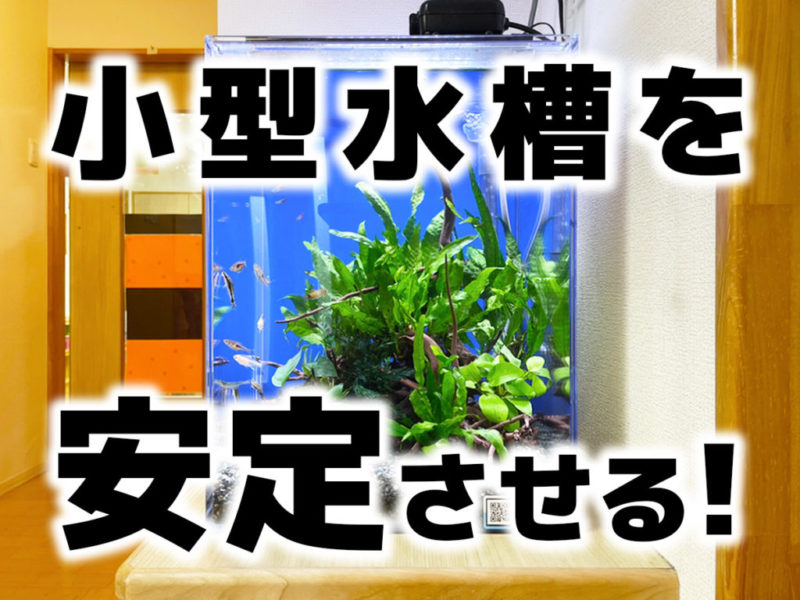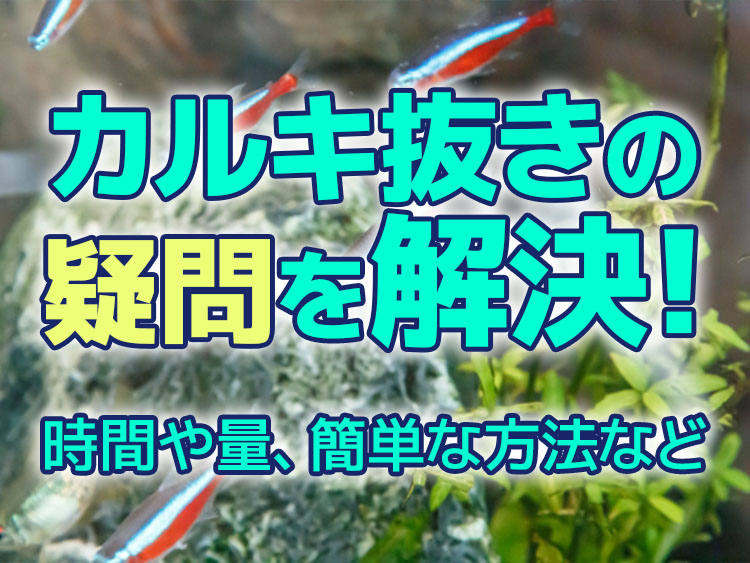コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
購入前はショップで元気に泳いでいたのに、「自宅の水槽に入れた途端に、熱帯魚が死んでしまった」という経験や、「水槽の水換え後に、急に死んでしまった」という経験をしたことのある方もいるのではないでしょうか。
このような場合は魚が『pHショック』を起こしてしまった可能性が高いです。
pHショックとは急激な水質の変化にさらされてしまい、魚の体が対応しきれずにショック症状を起こしてしまうことです。
今回はpHショックの原因や症状、対策などについて解説していきます。
目次
pHショックとは?

pHショックはメダカや金魚のような淡水魚、ディスカスやベタ・アロワナ・コリドラスのような熱帯魚や、海水魚など水中で生活する全ての生物におこりうる症状です。
ミナミヌマエビなどのエビ類もショック症状を見せることがあります。
pHとは?
pH(ピーエイチ、ペーハー)とは水中の水素イオン濃度を指す数値です。アクアリウムでは主に、飼育水の酸性~アルカリ性傾向を知るために確認します。
- pH7.0:中性
- pH:5.0~6.5:酸性~弱酸性傾向
- pH:7.5~8.5:弱アルカリ性~アルカリ性傾向
7.0を中間の基準として、数値の増減で水質の状態を知ることができます。
中性は金魚やメダカなどの観賞魚、弱酸性はネオンテトラなどの淡水熱帯魚、アルカリ傾向は海水魚に適しています。
生体に合った水質(pH)の状態では問題ありませんが、新しい水槽に移したり、水槽の水換えを行った際に急激にpHが変化してしまった場合には、生き物がショック症状を起こしてしまいます。
人間で例えるなら、平地から高山に行ったときの高山病や、真夏にキンキンに冷えたプールに飛び込んだり、冷水シャワーを浴びて手足がうまく動かなくなり脈が速くなる、というようなものです。
pHショックの症状は軽度~重度まであり、生体の体力や水質変化への適応力で受けるダメージが変わります。
pHショックになってしまう原因とは?

pHショックの原因は、主に以下の2点が考えられます。
- 購入してきた生き物に水合わせを行わず、すぐに飼育水槽へ入れた
- 水換え時の換水量が多く、急激に水質が変化した
基本的には生き物を新しい水槽に入れるときに、水合わせが不十分だったりすると起こりやすいです。
また、水換え頻度の少ない水槽だと、最初は弱アルカリ~中性のpHだった水質が時間をかけて酸性に傾いていることがあります。
ゆっくりとした水質変化だと魚も適応しやすく、得意な水質でない状態になっていても、馴染んで飼育できてしまうことも珍しくありません。
しかし、長期間水換えを行っていないと、水道から出した新しい水と、飼育水の水質に差が生まれます。
いつも通りに水換えをしたつもりが、新しい水を入れたことでpHが急変して、魚たちがダメージを受けてしまうこともあるため注意が必要です。
pHショックになったときの症状
pHショックになると以下のような症状が段階的に現れることが多いです。
- 投入直後にお腹を上にした状態で浮く
- 投入直後にクルクルと回転するように泳ぐ
- 急に動かなくなる、底に沈む
- エラの動きが激しく呼吸が荒くなる
- 目が白く濁る
- エラが充血する
- 泳ぎ方がふらふらしている
新しい環境に着て活発になっているように見えても、苦しんでいる場合があります。
そして、pHショックにかかると高確率で死んでしまいます。
魚やエビなどを水槽に入れてから3日間ほどは、このような動きを見せているものがいないかよく観察しましょう。
pHショックに陥ったときの対処法

pHショックが起きてしまった場合、対処してあげたいと思うのは誰もが思うことですが、残念ながら有効な治療法はありません。
すぐにphショックを起こす前の環境(飼育水)に戻すのが一番良い方法ですが、購入前の環境に戻したり、水換えをする前に戻すということは現実的に難しいでしょう。
水槽に入れた生き物に体力があったり、症状が軽い場合は様子をみていれば自然に回復していることがあります。
しかし、あまりに症状が重い場合は、一旦回復したように見えても体に大きなダメージが残り、しばらくして死んでしまうことがほとんどです。
pHショックの対策方法

pHショックを起こした場合、死んでしまうことがほとんどなので、未然に防ぐことが大切です。
水槽を移動する場合は必ず水合わせを行う

『水合わせと水温合わせ』はアクアリウムの基本です。
ショップで購入したり、知り合いから譲り受けた際など、魚を別の水槽・飼育環境へ移すときは必ず行いましょう。
移動先の水温や水質に慣れさせることで、pHショックを防ぎます。
具体的な方法としては、まずは袋のまま20分ほど飼育水に浮かべて水温を整えた後、袋の中に新しい飼育水を少しずつ添加していきます。
水合わせの詳細に関しては、こちらのコラムで詳しく解説しています。是非、ご一読ください。
水換え頻度、量に気を付ける
水槽の大きさや水槽内の生物の数にもよりますが、一般的に水換えは1~2週間に1度、水槽の3分の1~5分の1の量を水換えするのが通常の目安です。
また長期間水換えを行っておらず、水質が酸性に傾いた状態に魚が慣れている場合に、pH調整をせずに水換えを行うと、少量でもpHショックを起こしてしまうことがあります。
pHショックを防ぐためにも、pHを試験薬やメーターなどで確認し、こまめに少量ずつ行いましょう。
ただし、病気が発生したり、水槽内の環境が悪化している場合はその限りではありません。
改善できるようにメンテナンスを行いましょう。
水換えに関してはこちらのコラムで詳しく解説しています。
定期的に水質のチェックをしよう
水槽内に餌の食べ残しやフンなどの汚れがたまってくると、養分が水中に増えて水質の悪化・pHが傾く原因になってしまいます。
それ以外にも、水槽レイアウトで使用している岩や流木、底砂などの影響でゆっくりと水質が変化することあります。
- 岩:アルカリ傾向に傾く
- 流木:弱酸性傾向に傾く
- 底砂:サンゴ砂はアルカリ性、ソイルは弱酸性に傾く
水質は見ただけでは判断できないので、なるべく定期的に水質をチェックするようにしましょう。
市販されている、水質チェッカーで簡単に行うことができます。
水質チェックに関してはこちらのコラムで解説しています。
まとめ:pHショックを未然に防いで長期飼育を目指しましょう!

pHショックはある意味で、事故と考えることができます。
一度ショック症状に陥ってしまうと、回復しても数日後には死んでしまうことが多いため、未然に防ぐことが大切です。
新しく生体を追加するときは、必ず水合わせと水温合わせを行いましょう。
大事な熱帯魚、生体を長期飼育するためにも、普段から水質チェックや水換えの頻度なども適切なペースを見つけて管理できると良いです。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談フォーム
お悩み相談フォーム