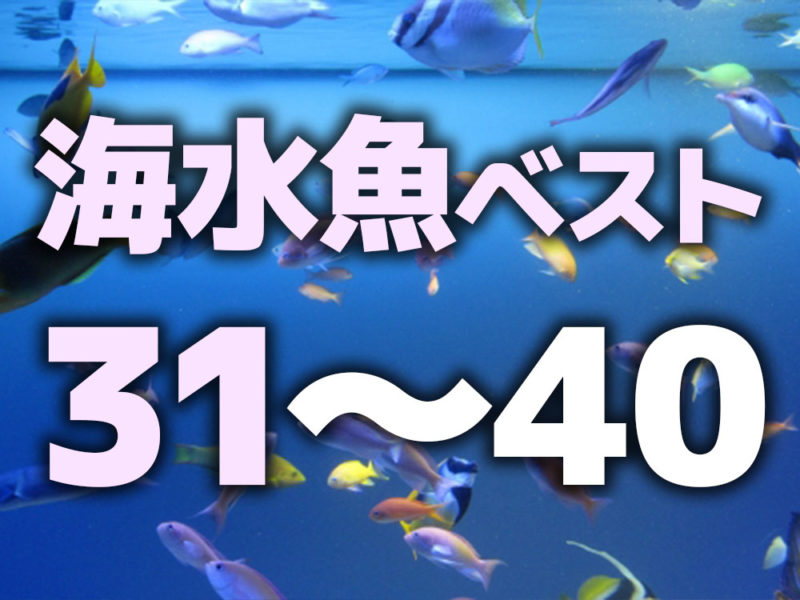ベラとは!海水魚の名脇役!ベラのおすすめ種類から飼育方法まで解説
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
チョウチョウオやカクレクマノミ、ナンヨウハギなど鑑賞魚として人気の海水魚は数多いです。
そんな主役級の海水魚たちに負けず劣らず、水槽を華やかに彩る魚がいます。
それがベラです。
カラフルな体色で程よい体長の種類が多いことと、比較的飼育しやすいこともあり、アクアリストたちに親しまれています。
今回はそんなベラにスポットを当てていきましょう。
海水魚界の名脇役ベラの種類や飼育方法を解説していきます。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに海水魚のベラをご紹介

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
ベラはポピュラーな海水魚で、アクアリウムで飼育できる種類も多くいます。
小型から大型種までいるので、お好みで選ぶのも楽しい魚種です。
ベラの特徴からおすすめ種類、飼育設備などをご紹介します。
ベラとは

ベラの仲間は日本の海でも容易に見つけることができる、なじみ深い海水魚です。
ここではベラの特徴から飼育におすすめの種類ご紹介します。
ベラの特徴
ベラは、スズキ目ベラ亜目ベラ科に属する海水魚の総称です。
世界中の温かい海に生息しており、その種類は約500種類、日本近海だけでも約130種類がいるといわれています。
ベラ科の海水魚は10~30cm程度の小さな種類のものが大半ですが、中にはナポレオンフィッシュのような体長2mを超えるものも含まれます。
そのため、飼育に必要な水槽や飼育方法も種類によって様々です。
ちなみに、ベラは食用としても漁獲されており、関西地方ではキュウセンベラの刺身や煮つけが好んで食されています。
飼育におすすめのベラ

では、観賞魚として飼育しやすい人気のベラをご紹介しましょう。
小型のベラ
小型のベラは色合いの美しい種類が多く、特にサンゴとの相性が抜群です。
中にはサンゴと飼育することで体色が鮮やかになる種類もいますので、ぜひサンゴと合わせて飼育することをおすすめします。
イエローコリス(コガネキュウセン)
黄色の体が美しいイエローコリスは、幼魚の頃からきれいな黄色をしているため、水槽を華やかにするのに最適の海水魚です。
また、底砂に潜って眠る習性から底砂を攪拌することができ、マガキ貝と組み合わせると底砂を美しく保ちやすくなります。
ホンソメワケベラ
ホンソメワケベラは、銀色に黒いラインと流線型の体が特徴の海水魚です。
他の魚についた寄生虫を『食べる』という変わった習性があることから、「掃除魚(クリーナーフィッシュ)」という愛称で親しまれています。
ナンヨウハギなど寄生虫に弱い魚種と一緒に飼育すると病気を防ぎやすくなるのでおすすめです。
ツユベラ
ツユベラは、赤い体に青い斑点と緑のライン、黄色の尾ひれという少々奇抜なカラーリングの派手な魚です。
実は幼魚の頃はまったく違う色合いをしており、大きくなるにつれて前述のカラーリングに変化していきます。
生長前と後、どちらも魅力的なベラでしょう。
ライムラス
珍しいライムグリーンをしたライムラスは、その色合いから観賞魚として大変人気の高い海水魚です。
しかし、成長するにつれてその特徴的な体色は薄れていってしまうことが多いです。
ラボックスラス
輝くようなオレンジ色の体色が美しいラボックスラスは、比較的飼育もしやすく人気の海水魚です。
飛び出し事故が多い魚なので、飼育の際は水槽の蓋が必須となります。
カーペンターズラス
カーペンターズラスは鮮やかな赤色の海水魚です。
大人しい性格の海水魚ですが興奮すると、体の赤色が一層鮮やかになり、背びれを広げて威嚇する特徴があります。
ニセモチノウオ
派手なボーダー柄が水槽の中でも際立つニセモチノウオ。
少々気が強い性格なので、大人しい種類の魚との混泳は避けましょう。
大型のベラ
大型のベラは大きいものだと1m近くまで成長する種類もいますので、飼育する際には大型の水槽を用意しましょう。
また、スズメダイなどの小型の海水魚を食べてしまう危険があるので、混泳の際には要注意です。
ヤマブキベラ

メスは山吹色、オスは青緑色の体色が特徴的なヤマブキベラ。
オスと別種のオトメベラはそっくりですが胸ヒレに赤紫色の模様を持つものがオトメベラと見分けることができます。
また、体長も倍近く差があります。
ちなみに、メスは黒い斑点が無いものの、イエローコリスによく似ています。
ナポレオンフィッシュ

頭部に大きなこぶを持つ青い海水魚ナポレオンフィッシュは、ベラの中で最も大きくなる魚として知られています。オスの中には2m程度まで大きくなる個体もいるそうです。
飼育していると人間に懐くこともあり、餌をねだる姿も見られます。
ニシキベラ

ニシキベラは、丈夫で飼育のしやすい初心者にもおすすめの海水魚です。
大きさは15cm程度とそこまで大きくなる種類ではありませんが、遊泳性が高いので飼育するときには大きな水槽を用意してあげるとよいでしょう。
ベラを飼育しよう!飼育に必要な器具

ベラを飼育するためには、主に以下のものを用意する必要があります。
- 水槽
- 水槽の蓋
- フィルター
- 底砂
- 餌
- カルキ抜き
- 人工海水のもと
- サンゴ
- 餌
- ライブロックなどのレイアウト用品
水槽/水槽の蓋

水槽の大きさはベラの種類によって異なります。
小型のベラならば45cm程度の小型水槽でも飼育が可能ですが、60cm以上の大きさがあれば飼育できる種類は格段に多くなります。
ナポレオンフィッシュなどの大型のベラの場合は、最終的に180cm以上の大型水槽が必要です。
また、ベラは水槽の外に飛び出してしまうことの多い魚なので、水槽には必ず蓋を付けて飛び出し事故防止に努めましょう。
ろ過フィルター
ろ過フィルターはパワーの高いものを選ぶのが望ましいです。
おすすめは上部フィルターか外部フィルターですが、大型の水槽の場合はオーバーフロー式の水槽の導入も検討しましょう。
底砂
ベラの多くは砂に潜る習性があるため、底砂には目の細かいサンゴ砂を使用するとよいです。
5~8cm程度の厚さで底砂を敷きましょう。
目の粗いものは、ベラが潜った時に体を傷つけてしまう恐れがあるので、おすすめできません。
サンゴ

ベラの中には、サンゴの隙間に隠れたり眠ったりする種類のものがいます。
飼育したい種類のベラとサンゴの相性を確認し、相性が良ければ一緒に飼育してみるとよいでしょう。
ただし、大型のベラの中にはサンゴをつついてしまう種類もいますので、相性の確認は必ず行ってください。
餌
ベラはなんでも食欲旺盛に食べるので、餌付けしやすい海水魚です。
人工飼料でも問題なく飼育できますが、人工餌の食べが悪い時には、エビなどの甲殻類が大好物なので、冷凍のシュリンプなどを与えてみましょう。
ベラの飼育方法について

種類にもよりますが、ベラの多くは丈夫で病気になりにくく、餌付けにもあまり苦労することはないので飼育のしやすいものが多いです。
前述した通り、底砂に潜る習性をもつ種類が多いので、飼育するときには必ず目の細かいサンゴ砂を敷いてあげる必要があります。
水温
水温は22℃~26℃ぐらいまでが適温です。
ただし、イエローコリスなど、種類によっては24℃くらいのやや低温を好む種もいるため、飼育する種類の適温を確認してください。
サンゴを一緒に飼育している場合は23℃~26℃程度が適温となります。
混泳について

ベラは多くの魚と混泳が可能な海水魚です。
ただし、種類によって相性がありますので、必ず相性を確認しましょう。
例えばライムラスは、気の強い海水魚と混泳させると怯えて砂の中から出てこなくなってしまうことがありますので、注意が必要です。
ナポレオンフィッシュについては、基本的に混泳を避け単独での飼育が推奨されています。
大きくなるため自宅で用意できる水槽の大きさでは単独飼育が限界というのが大きな理由です。
また、基本的に同種の混泳はケンカになってしまうことが多いので避けましょう。
まとめ:ベラとは!海水魚の名脇役!ベラのおすすめ種類から飼育方法まで解説

ベラはとても多くの種類がいますが、どれも大変魅力のある海水魚ばかりです。
小型のものであれば飼育がしやすいものが多く、見た目も華やかなので水槽を彩るのにはぴったりの海水魚です。
また、入手するのも飼育するのも大変ではありますが、ナポレオンフィッシュなどは一匹で十分水槽の主役になりえる魅力があります。
ぜひベラをご自宅で飼育してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談フォーム
お悩み相談フォーム