アンモニアは水生生物の代謝の結果必ず発生する、刺激臭を伴う強毒性の物質です。飼育水中のアンモニア濃度が高くなりすぎると、「アンモニア中毒」に陥り生体が死んでしまうので注意が必要です。
アクアリウムにおいてアンモニアを管理するには、それを養分に生きている硝化菌の存在が欠かせません。硝化菌はアンモニアを亜硝酸塩を経由して、比較的無毒な硝酸塩に変換してくれるので、この「硝化プロセス」をいち早く構築することがカギとなります。
ここでは、水槽内でのアンモニアによる悪影響や、アンモニア濃度が下がらない時の対処法などについて解説していきます。
アンモニアは水槽になぜ発生するのか

アンモニアの発生源は、生体の排せつ物や食べ残した餌、枯れた水草、死骸などで、それらの有機物が分解される過程で生じます。また、魚は代謝の結果生じたアンモニアをエラから排出しているので、生物が水槽内で活動していると必ず発生してしまいます。
自然界では通常、水中に発生したアンモニアはろ過バクテリアである硝化菌によって、亜硝酸塩を経て比較的無毒な硝酸塩へと変換されるため、生体に悪影響が出るほど濃度が高くなることはありません。
しかし、水槽という狭い環境ではそうはいかず、適切に管理を行わないと濃度が高くなり、詳しくは後述する様々な弊害をもたらします。
アンモニアの濃度は、このような試験紙や試験薬でわかります。
アクアリウムにおいてアンモニアの濃度を抑えるためには、先に述べた「アンモニア→亜硝酸塩→硝酸塩」の変換を行う「硝化プロセス」の構築が欠かせません。
硝化プロセスには硝化菌の存在が必要不可欠で、硝化菌はアンモニアを養分にして生きているため、生体から排出されるアンモニアの量と、硝化菌の数のバランスを上手く取ることが重要です。
また、硝化菌が少ない状態だと、水カビなどの雑菌が繁殖しやすい環境になってしまうので、アクアリウムとアンモニアは切っても切れない関係にあります。
アンモニアのアクアリウムへの影響

生体が死んでしまう
一番の問題になるのが生体への悪影響です。アンモニアは毒性が強い物質で、一定の濃度を超えると「アンモニア中毒」に陥って死んでしまいます。
水中のアンモニア濃度が0.25mg/L以上になると危険で、魚の場合この濃度に長期間晒されると、底の方で動かなくなったり、鼻上げをするなどの症状が現れ、やがて横になって死亡します。水質の悪化に敏感なエビ類はさらに危険で、魚よりも早期に死亡してしまうので注意してください。
水が白く濁る
水槽の水が白く濁る現象は、底砂などが舞い上がっている時や、バクテリアなど微生物の死骸が多く浮遊している時に発生しますが、アンモニア濃度が高くなることでも起こります。
水換えなどの水槽作業を行っていないにもかかわらず水が白く濁りだしたら、アンモニア濃度が上昇している可能性があるので、検査キットを用いて水質を調べてみてください。
水が臭う
中学校や高校の理科・化学の授業で、アンモニアを扱ったことがある方もいると思いますが、アンモニアは非常に強い刺激臭を持つ物質です。
そのため、飼育水中のアンモニア濃度が高くなると、単純に飼育水が悪臭を放つようになります。水槽の水が臭いと感じられるようでしたら、アンモニアが溜まっている可能性が高いので、やはり水質を調べておくと良いでしょう。
アンモニアを下げる方法・対策

水換え
アンモニア濃度を下げる方法で、最も簡単かつ手っ取り早いものが水換えです。即効性にも優れているので、アンモニアを検出したら速やかにいつもより多めの換水を行ってください。しかし、アンモニア濃度が高くなった原因を解消しなければ、すぐに元の木阿弥になってしまうので注意してください。
バクテリア(硝化菌)を繁殖させる
アンモニア濃度が高くなるということは、その水槽環境において硝化プロセスが出来上がっていないことを意味します。具体的には発生するアンモニアの量に対して、それを硝化するための硝化菌の数が足りていないことが考えられるので、ろ過バクテリアである硝化菌の増殖を目的とします。
硝化菌を増殖させるためには住処となるものが必要で、硝化菌は表面が凸凹したものに定着しやすいため、フィルター内のろ材や底床材について必要ならば見直してみてください。
また、硝化菌は好気性細菌であるので、溶存酸素が豊富な環境を好みます。そのため、エアレーションを強化し、水槽全体とフィルター内のろ材に酸素が行き渡るようにすると、繁殖も円滑に進行します。
さらに、硝化菌は水温が高い方が活性が高くなることが知られているので、水温を上げることも効果的です。しかし、水生生物がいる場合は、その生体に負担がかからない程度の水温に留めてください。
その他にも、市販のバクテリア材を使用することでも、硝化菌の定着を補助できますが、バクテリア材に含まれている硝化菌が必ずしも定着するわけではないので、過信は禁物です。
ろ過器の洗浄・見直し
ろ過器(フィルター)を正しく稼働させているのに、いつまでもアンモニアが検出される場合は、フィルターそのものを見直す必要があります。
まずは、フィルター内のろ材が目詰まりを起こしていないか確認しましょう。ろ材がゴミやバイオフィルムなどで目詰まりを起こすと、流量が低下すると共にろ過能力も低下してしまうからです。
ろ材が目詰まりしていた時は洗浄しますが、水道水をそのまま使用することは避けてください。含有されるカルキによって、せっかく定着した硝化菌が死滅してしまうためです。
ろ材を洗浄する際は基本的には飼育水を使用するようにして、十分な量の飼育水を確保できない時は、少なくともカルキ抜きをした水道水を使ってください。
ろ材に異常がない場合は、単純にフィルターの容量不足が考えられます。
フィルターのろ過能力は運用できるろ材の量に依存しているので、能力が不足しているようでしたらもうワンランク上の容量が大きいタイプを導入したり、多くのろ材を運用できる形式への変更を考慮してください。複数のフィルターを併用することも効果的です。
まとめ:アンモニアの影響とは!水槽内でのアンモニア被害や下がらないときの対策

アンモニアは水生生物の代謝の結果発生する毒性物質で、それと同時にろ過バクテリアである硝化菌の養分になるので、アクアリウムにおいては切っても切れない関係にあります。しかし、アンモニアは濃度が高くなりすぎると、アンモニア中毒を引き起こすので注意が必要です。
アンモニアを管理するためには硝化菌の数を増やすことが最優先で、そのためにはフィルター容量やろ材などの見直しが必要になる場合もあります。
発生するアンモニアに対して十分な数の硝化菌が居なければ、その水槽環境はいずれ崩壊してしまうので、硝化菌を繁殖させて硝化プロセスをきちんと構築しておきましょう。
水槽のプロが所属するサイト運営チームです。
淡水魚・海水魚・水槽設備やレイアウトのことまで、アクアリウムに関する情報を発信していきます!
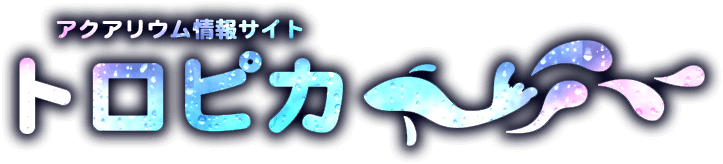
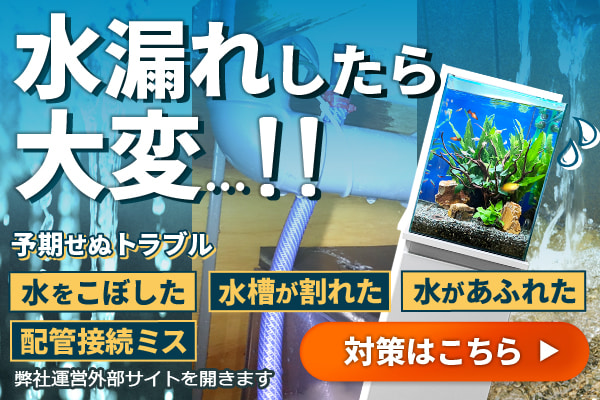







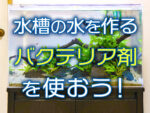






コメント
はじめまして。
アンモニアを減らす(増やさない)ために硝化菌が効果あるとのことですが、硝化剤の必要量などは水槽ごとに比率は決まっていますか?
バクテリア剤の厳密な量はメーカーに直接ご確認をお願いしています。
とはいえ、硝化菌はアンモニアが発生する環境(=生き物を飼育している水槽)では自然に繁殖していきます。
適度に水換えを行っていれば、添加量にかかわらず増えていくと考えています。
バクテリア剤は添加していくことで、水槽の立ち上がりが早まるアイテムです。
水換え時に規定量を添加することをおすすめします。
こちらのコラムもご参照ください。
・水槽用バクテリア剤の必要性・メリットやデメリットを解説します
https://t-aquagarden.com/column/bacterial_liquid
よろしくお願いいたします。