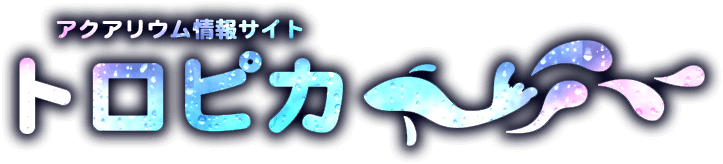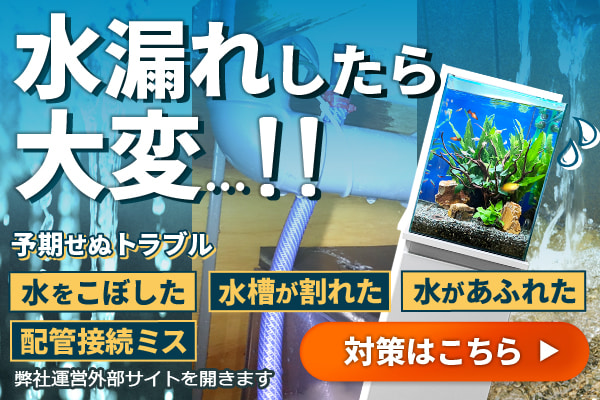海水魚の飼育って難しい、すぐに死んでしまうし、原因もよくわからないという初心者の方は多いですね。
原因がわからないとまた同じことを繰り返してしまう可能性もありますし、ここで「海水魚を上手に長生きさせるコツ」を5つ紹介します。
コツをつかめばうまくいくもの、ぜひ海水魚にチャレンジしてみませんか?
海水魚を長生きさせるコツ5選!

海水魚は飼育が難しいイメージがありますが、コツをしれば成功は近づきます。まずそのコツを5つご紹介します。
- 適したろ過フィルター選定
- 溶存酸素量を重視する
- ヒーター、クーラーを使っての水温管理
- バクテリアの活性を高める
- 白点病には殺菌灯を導入
この5点に注意をすると海水魚飼育のハードルは下がります。では1つずつ詳細にみていきましょう。
海水水槽はろ過フィルター選定が大切!

海水水槽はとてもゴミが生じやすいので、とにかくろ過フィルターの選定で水槽の環境が大きく左右します。
選定のコツは「オーバースペック気味のろ過フィルターを選ぶこと」です。
過剰な水流が生じるようでは困るのですが、そうならない範囲であれば強ければ強いほど、水槽内の環境が安定します。予算の関係もあると思いますが、できるだけハイパワーなろ過フィルターを選んでください。
それでもどんなものが良いのかわからないという方は下のリンクにまとめてありますので参考になさってください。
溶存酸素量を重視しよう

海水魚水槽では、溶存酸素量を保つこともとても重要です。
溶存酸素量とは、水槽内の水にどのくらいの酸素が溶け込んでいるかを示す数値です。溶存酸素量が保てている水槽は水質がとても安定しやすいです。理由は排泄物や餌の食べ残しから生じるアンモニアを比較的無害な硝酸塩に分解してくれる「硝化バクテリア」のはたらきが維持できるからです。
海水水槽において、硝化バクテリアの活性は非常に大きな影響を及ぼします。硝化バクテリアは好気性細菌(酸素を使って生きているバクテリア)なので、酸素の量が減るとうまくはたらいてくれません。そうすると水質は悪化する一方となってしまうのです。
溶存酸素量の数値を測定する器具はそこそこ高価なため、一般家庭で数値を具体的に測定する難しいです。そこで「とにかく多めに酸素を溶かし込もう」という気持ちでメンテナンスするように心がけてください。
具体的には、
- 水温を上げ過ぎない
- エアレーションやプロテインスキマーの稼働を行い、酸素を取り込む
- 適度な水換えを行う
などの手法がおすすめです。
水槽用クーラーや水温管理は必須

海水魚は水温の変化にも敏感で、ほとんどの海水魚は27℃以上になると弱ってしまいます。
逆に水温が下がりすぎても弱り、元気がなくなり、病気にもかかりやすくなります。
そういった事態を避けるため、ヒーターとクーラーを常設し、外気温に関わらず水温を一定に保てる工夫をすることが大切です。
下のようなアイテムを使えば1台で兼用も可能です。
このアイテム TEGARU については下のリンクでご説明しています。
外部フィルターと組み合わせることでクーラーを効率的に稼働させることもできますので下のリンクも参考にしてください。
硝化バクテリアの活性を高めよう
上の「溶存酸素量を重視しよう」の項目でもお話しした通りなのですが、海水水槽における硝化バクテリアの活性は大きなカギとなります。
硝化バクテリアの活性を高めるには、ろ材の目詰まりが生じないように気を付けてください。また、水流が強すぎると酸素が水の外へ逃げてしまいますので、強すぎる水流が発生しないようにしましょう。
ちなみに海水魚水槽ではあまりみられませんが、pHの低下は硝化バクテリアの活性を悪くしますので、pHの維持も大切なポイントです。
しつこい白点病には殺菌灯を導入する
しつこい白点病が発生してしまった場合は、殺菌灯を使うことが一番効果的です。
淡水魚水槽でも発生する白点病ですが、海水魚水槽でも厄介な存在です。白点キラーという薬剤で薬浴する手法でも良いですが、殺菌灯であれば今後の白点病も防止できますので、根本的な解決となります。ただし初期費用がかかってしまいますが…。
他の殺菌灯もこちらのリンク記事で紹介していますので、ご覧になってみてください。
海水魚が死んでしまうときは
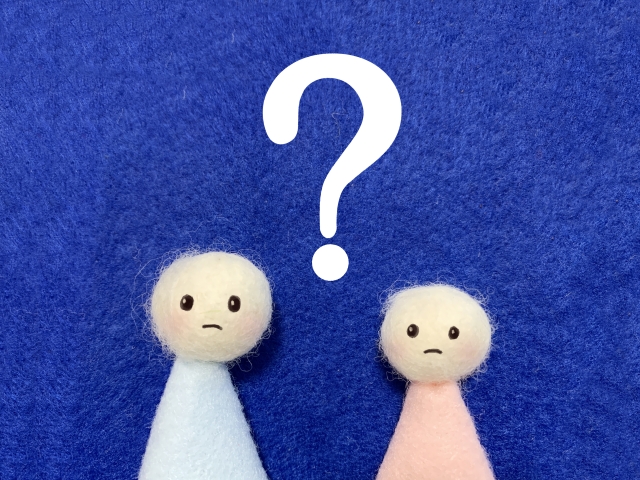
それでも海水魚が死んでしまう…という時にチェックすべき項目をあげてみました。
- 飼育環境の見直し
- 餌が食べられているかの確認
- 魚が死んでしまった場合の対処 の3点になります。
飼育環境を見直してみよう

海水魚が死ぬときは、環境に必ず何かしらの問題があると考えましょう。
上の項目でお話しした「長生きさせるコツ」を踏まえ、フィルターのパワーはどうか、水質はどうか、など1つずつチェックしてみてください。
餌が食べられているかを確認しよう

餌をきちんとあげているつもりでも、1匹ずつがきちんと餌を食べているか確認しましょう。
- 餌付けができておらず、餌を食べに出てこない
- 水槽内で下位のポジションとなってしまっているため、餌にありつけない
などの理由で餌が食べられていない個体が発生する場合もあります。
まんべんなくすべての個体が餌を食べているかしっかりチェックしましょう。
死んでしまったらすぐに掬おう
気を遣って飼育していても、やはり海水魚が死んでしまうことはあります。
そういった場合は、すぐに掬いだしましょう。水槽に入ったままになると遺骸が腐敗し、水質がどんどん悪化してしまいます。また、他の魚の餌となることもあり、そういった場面を見るのは悲しいものです。
毎日魚たちの顔を見て健康状態をチェックすることでこういった痛ましいケースを防ぐことができます。
まとめ:海水魚がすぐ死ぬ!海水魚を上手に長生きさせるコツ5選!焦らず育てよう

海水魚を長生きさせるための注意ポイントや、それでも死んでしまった場合の対処法についてお話しをしました。
何事も経験でうまくなっていくものですが、ポイントを抑えれば上達も早まります。
可愛くて色鮮やかな海水魚を上手に育ててあげましょう。
水槽のプロが所属するサイト運営チームです。
淡水魚・海水魚・水槽設備やレイアウトのことまで、アクアリウムに関する情報を発信していきます!