
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
ビオトープは家の軒先やベランダなど、屋外で魚や水草を育成する人気の飼育方法です。
居住スペースを圧迫することもなく、照明やろ過フィルターといった大掛かりな飼育設備も必要ないので、初心者の方でも簡単に始めることができます。
ただし、どんな生き物でも飼育できるわけではありません。
屋内飼育に比べて、季節や天候の影響を受けやすく水温や水質、日照時間などの変化が多いことから、ビオトープで飼育する生体には、環境変化に強く丈夫であることが求められます。
そこで、今回は飼いやすい魚やエビ、貝など、ビオトープにおすすめの生体を7種ご紹介します。
目次
プロのアクアリストたちの意見をもとにご紹介

このコラムは、東京アクアガーデンに在籍するプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
アクアリウム界の中でも根強い人気を誇るビオトープですが、飼育する生体は屋外飼育にも適した丈夫な生き物を選ぶことが大切です。
今回は水質や水温の変化に強い丈夫な小型魚や貝類などをご紹介していきますので、これからビオトープを始めようと考えている方はぜひ参考にしてください。
ビオトープとは?

ビオトープとはギリシャ語の『bios(生物)』と『topos(場所)』から作られた言葉で、水辺の生態系を人工的に再現し、生き物が自然に近い状態で生息している空間のことを指します。
本来は環境保全関連でよく使われる言葉でしたが、最近は屋外飼育を行うアクアリウムの一つのジャンルを指す言葉として定着しました。
日本では家の軒下やベランダなどにビオトープ用の水槽や睡蓮鉢を置いてビオトープを作ることが多く、和の趣を感じながら屋外で魚や水草を育成できるということで、アクアリウムの中でもかなりの人気を誇るジャンルとなっています。
屋外で電源の確保が難しいことから、ろ過フィルターや水槽用ヒーターなどの機材は基本的に使わずに、季節や天候に合わせて変化していく自然のままの様子を観察するのが、ビオトープならではの楽しみ方です。
ビオトープのメリット・デメリット
ビオトープは屋外での飼育が基本となるため、自然と調和した趣のある癒しの水景を再現することができるのが最大のメリットとなります。
四季によってさまざまな表情を見せる自然な姿は、都会ではなかなかお目にかかれない光景です。
冬になれば自然と生き物たちの活動が落ちメダカなどは冬眠をすることもあります。このような自然のサイクルを自宅で観賞できるのがビオトープの魅力です。

ビオトープには睡蓮などの水辺に咲く花を植えることもできます。それ以外にも、ビオトープの周りにプランターを置いて植物で飾るのも良いでしょう。
四季折々の植物と一緒に、水生生物を観賞できるのもビオトープならではです。
また、ビオトープは基本的に容器を用意して環境を整えれば初心者でも気軽に楽しむことができます。
屋内の水槽では水質を維持するために必須となるろ過フィルターも、屋外で飼育するビオトープでは自然に近い水質浄化サイクルが成り立つため必要ありません。
定期的な水槽の掃除や水換えは必要ですが、それも屋内飼育に比べると少ない頻度で済むことが多いです。
このように、メリットの多いビオトープですが、このあまり手を加えないスタイルから、飼育できる生き物や育成できる水草には制限があります。
飼育できるのは日本の四季に対応できる生き物で、環境の変化に強く丈夫であることが条件です。
一年を通して加温が必要な熱帯魚は飼育できないですが、メダカやドジョウなどの素朴な生き物たちとともに自然を感じられる、風情のある飼育法と言えるでしょう。
ビオトープの種類
ビオトープは使う容器の形状によって、いくつかの種類に分類されます。
ここでは、代表的な『睡蓮鉢タイプ』と『プラ舟タイプ』をご紹介します。
■睡蓮鉢タイプ
睡蓮鉢と呼ばれる陶器製の鉢を利用して作るビオトープです。
睡蓮鉢は形や色、柄が豊富なため、器を含めた一つのオシャレなインテリアとしてビオトープを作ることができます。

玄関先などの人目につきやすい場所に置く場合は、睡蓮鉢タイプがおすすめです。
■プラ舟(トロ舟)タイプ
プラ舟(トロ舟)と呼ばれる大きなプラスチック製の箱を使って作るビオトープです。

そのまま置いて使うこともできますし、地面に穴を掘って埋め込み池のように使うプラ舟もあります。
プラ舟は睡蓮鉢に比べるとかなり大きく、たくさんの水量が確保できるため、多くの生き物や水草を飼育育成することが可能です。
広いスペースを確保できることからレイアウトの幅も広がり、より本格的にビオトープを楽しみたい方にはこちらがおすすめです。
ビオトープにおすすめの生体7選

ビオトープには環境変化に強い丈夫な生体がおすすめです。
屋外ということもあって水温が変わりやすく、雨が降り注げば水質も変化します。
また、基本的にエアレーションなどを使わないので、酸欠のリスクも気に留めてかなければなりません。
これらの環境変化に強い『ビオトープ向き』の生体の中から、今回は以下の7種をご紹介します。
- メダカ
- アカヒレ
- ドジョウ
- ミナミヌマエビ
- ヤマトヌマエビ
- タニシ
- イシマキガイ
それぞれビオトープの主役だったり、コケや食べ残しを食べてくれるメンテナンスフィッシュとして優秀だったりと特徴があるので、役割に応じて選んでみてください。
生体と一緒に水草の育成を楽しみたい方は、以下の記事もおすすめです。
メダカ
■メダカのおすすめポイント
- 一年を通して屋外飼育ができる
- 環境が整えば容易に繁殖し殖やすことが可能
ビオトープにおすすめの生体としてまず挙げられるのがメダカです。
メダカはとても丈夫な魚で、四季を通じてビオトープで飼育することができます。
夏の高水温(30℃前後)や冬の低水温(10℃前後)でも問題ありません。
ただし極端な水温変化はメダカの負担になってしまうので、夏場はすだれをして直射日光を防いだり、移動可能な場合は、冬場は風が吹き込まない場所に飼育容器を置くなどの工夫をしましょう。
環境が整っていれば繁殖させることが難しくないのも、人気の理由のひとつです。
主役としてはもちろん、水草やヌマエビ類とも相性が良いので、緑いっぱいのビオトープに合わせる生体としてはかなりおすすめのお魚です。
アカヒレ
■アカヒレのおすすめポイント
- 10℃程度の低温に耐えることができる
- 酸欠に強い
続いてご紹介するのはアカヒレです。
アカヒレは冬場の低水温(10℃程度)に耐えることができるお魚で、水質の変化や酸欠といった環境変化にも強く、ビオトープに向いています。
温和な性格なのでメダカと混泳させることもできますが、遊泳層(泳ぐ水深)が同じなので、あまりたくさん入れるとお互いストレスになってしまうことも。
メダカとアカヒレの両種を混泳させる場合は、過密飼育は避けた方が無難です。
また、極端な寒さには弱いので、寒冷地の冬場は発泡スチロールの容器などで保温してやるのが良いです。
ドジョウ
■ドジョウのおすすめポイント
- 他の生体が食べ残した餌を食べてくれる
- どのような生体とも混泳可能
日本淡水魚のドジョウも、ビオトープに最適です。
丈夫なことはもちろん、他の魚の食べ残しを食べてくれるメンテナンスフィッシュとしても重宝されます。
ドジョウをビオトープに入れておくと、他の魚が食べ残して沈んだ餌を率先して食べてくれるので、水質の悪化を防ぐ役割を果たしてくれるのです。
ドジョウの中にも様々な種類がありますが、ビオトープで飼育するなら
- ドジョウ(マドジョウ)
- シマドジョウ
- ホトケドジョウ
といった、低温だけでなく高温にも耐性があるドジョウがおすすめです。
他の種類は高温に弱い傾向があるため、夏場の高水温に耐えられないことがあります。
性格が温和なので、基本的にどのような生体とも混泳させることができますが、上記の中ではホトケドジョウのみやや気性が荒く肉食傾向が強いため、混泳相手を食べてしまうなどのトラブルが起きる可能性があります。他の魚と混泳させるのであれば、ドジョウやシマドジョウがおすすめです。
また、ビオトープには底砂として赤玉土などを使用することが多いですが、ドジョウを飼育する場合はヒゲや体を傷つけないように、なるべく粒が細かく角が丸い底砂・田砂などを選びます。
底砂にヒゲを当てて餌を探したり潜ったりする習性があるためです。
田砂はその名の通り田んぼの砂として使われるような底砂で、粒子が細かくドジョウが潜りやすいのでおすすめです。
ミナミヌマエビ
■ミナミヌマエビのおすすめポイント
- コケや残り餌を食べてくれる
ミナミヌマエビはビオトープのコケ掃除役としておすすめの生体です。
飼育容器の壁面や底砂、水草に生えたコケや食べ残しを食べてくれるので、きれいな水景を保つことができます。
温和な性格のため、魚や水草に害を与えることもありません。
小型のエビなのでお掃除生体として効果を実感するには、それなりの数(20匹程度)を入れる必要があります。
飼育はとても簡単なので、繁殖させて殖やしてみても良いでしょう。
ただし、生まれたての稚エビは魚に食べられやすいです。
繁殖させる場合は抱卵した時点で隔離して育てましょう。
ヤマトヌマエビ
■ヤマトヌマエビのおすすめポイント
- コケ取り能力に優れている
ヤマトヌマエビは、ミナミヌマエビと並ぶお掃除生体として知られています。
4cm前後と比較的大きいこともあって、優れたコケ取り能力を誇ります。
ただし、少々存在感のあるエビなので、魚がメインのビオトープにしたい場合は数を控えましょう。
注意点として、ヤマトヌマエビは餌であるコケなどが足りなくなると、水草の新芽を食べてしまう事があります。食害を抑えるには、
- 飼育する数を抑えて、餌が行き渡るようにする
- ヤマトエビにもしっかり餌を与える
の2点を意識してみましょう。
また、ヤマトヌマエビは繁殖するのに汽水が必要なので、ミナミヌマエビのように簡単に殖やすことができない点も覚えておいてください。
タニシ
■タニシのおすすめポイント
- 水を浄化する能力がある
- コケや食べ残しを食べてくれる
一見、地味な貝のタニシですが、実は水を浄化する能力に優れています。
タニシは飼育容器の壁面や底砂の表面のコケ、食べ残しを食べてくれるだけでなく、『ろ過摂餌』という水をろ過しながら水中のプランクトンを摂取するという独特の捕食方法によって、飼育水をきれいに保つのに一役買ってくれます。
ろ過フィルターがないビオトープでは、水をろ過する能力のあるタニシはかなり重宝される存在です。
ただし、有益なグリーンウォーターも濾過摂食してしまうので、透明な水になってしまう点には注意しましょう。
イシマキガイ
■イシマキガイのおすすめポイント
- コケ取り能力が高い
- 適応できる水質や水温の幅が広い
アクアリウムでコケ掃除役として有名なイシマキガイは、ビオトープにもよく導入されます。
コケ取り能力が高く、メダカやエビといった生体と相性が良いのがその理由です。
弱酸性~弱アルカリ性、10~28℃と適応できる水質や水温の幅が広く、屋外に設置したビオトープでも通年飼育することができます。
また、石巻貝の卵は淡水では孵化しないため、過剰に殖えて困ることもありません。
ただし水槽の壁面や石の表面に卵を産み付けることがあるため、気になる場合は手やヘラで取り除きましょう。
日本の風土に合った生体を選ぼう

ビオトープに合わせる生体は、日本の風土に適応できる種類を選ぶことが大切です。
日本には四季があるため水温の変化が大きく、夏場の高水温から冬場の低水温まで耐えられる生体であることが選ぶ条件となります。
ビオトープにはろ過フィルターやエアレーションがないうえに、雨が吹き込めば水温だけでなく水質も変わります。
ヒーターやクーラーといった温度を調節する飼育器具も設置しないので、どうしても生体自身の適応能力に頼らざるを得ません。
屋外に設置したビオトープに生体を導入するのであれば、水温だけでなく水質の変化にも強い、丈夫な魚を選びましょう。
また、水草と一緒に飼育する場合は、生体が植物を食害しないかどうかという点も確認しておきたいポイントです。
まとめ:ビオトープにおすすめの生体7選!飼いやすい魚・エビ・貝をまとめました

ビオトープは『環境の変化が大きい』ということが特徴といえます。
そのため、ビオトープで飼育する生体は環境の変化に強い生き物であることが求められますが、今回ご紹介した魚たちはどれも丈夫なので、相性は抜群です。
ビオトープに入れる生体でお悩みのはこのコラムを参考にしつつ、主役や混泳相手、もしくはお掃除生体など、目的に合った生き物をじっくりと選んでみてください。
ビオトープについて良くあるご質問
ビオトープとはどんな飼育方法ですか?
メダカにとって最適な環境であり相性抜群ですし、同時に睡蓮やオモダカなどの水生植物や季節感も楽しめるため、自宅の彩りとしても人気です。
ビオトープで飼育できる生き物とは?
屋外に設置するため、温度変化や低水温に強い生き物であることが条件です。
- メダカ
- ヌマエビ
- ドジョウ
- 石巻貝・タニシ など
アカヒレも適していますが、寒さにはあまり強くないため、発泡スチロールの容器を使用するなど対策が必要です。
寒冷地や寒さが強い場合は、それ以外の生き物でも保温・凍結対策を行いましょう。
ビオトープ飼育で気を付けたいことは?
特に気を付けたいのは夏と冬です。外気温が厳しく、ビオトープは影響を受けやすいです。
- 夏:水温の上昇、蒸発
- 冬:凍結、雪
水温の上昇、凍結対策は共通して足し水とすだれの設置が有効です。
この他には通年で、ヤゴや猫・カラスなどの外敵にも気をつけましょう。
ビオトープの容器は何が良い?
しかし背の高い水生植物を楽しみたい場合は、睡蓮鉢のような深さのある頑丈な容器を使用します。
ビオトープの完成イメージに近い容器を選択するのも良いでしょう。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談フォーム
お悩み相談フォーム



















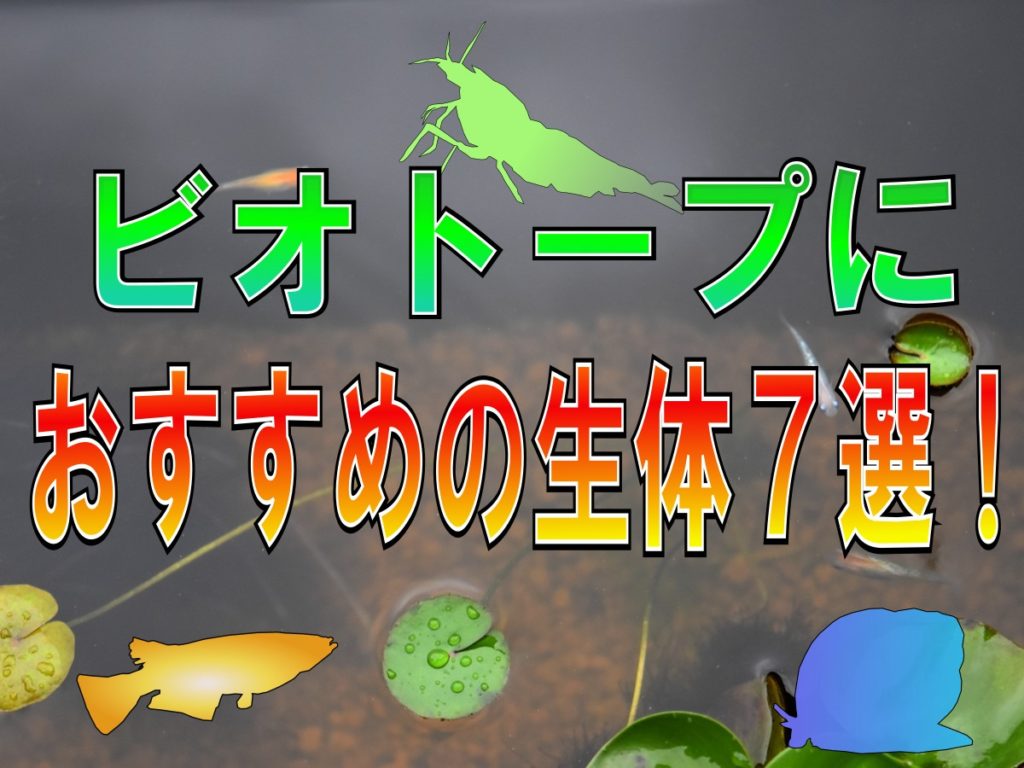












![【めだか物語】青みゆき(幹之)めだか 未選別 稚魚 SS~Sサイズ 20匹セット / 鉄仮面血統 [生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ANjUeP2KL._SL500_.jpg)
















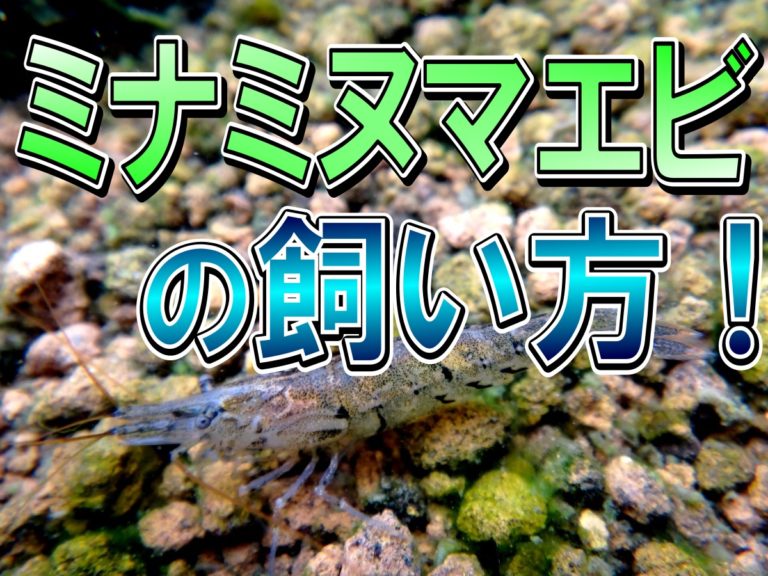







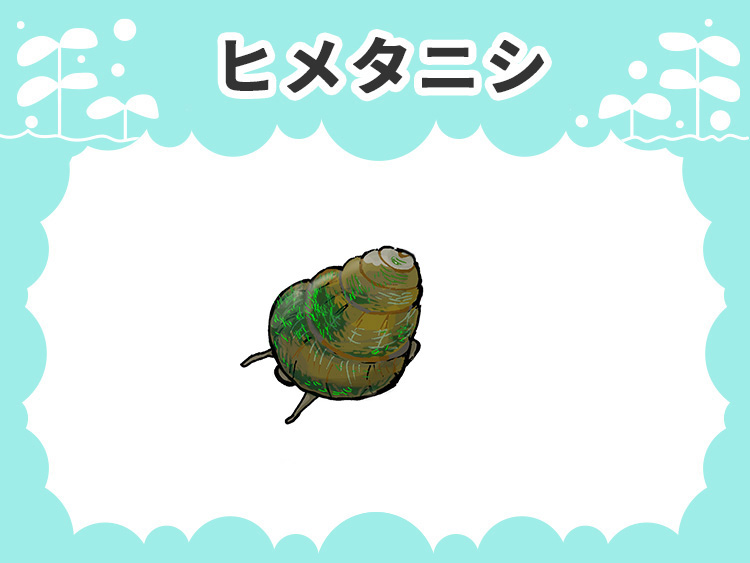


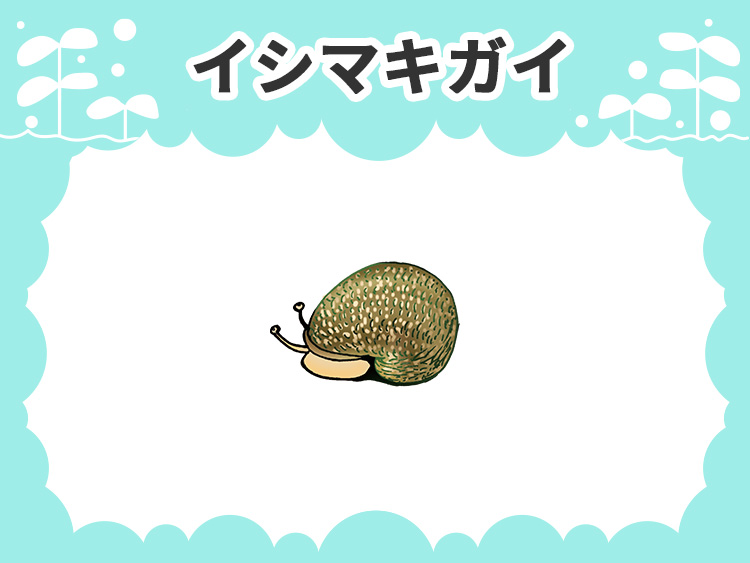

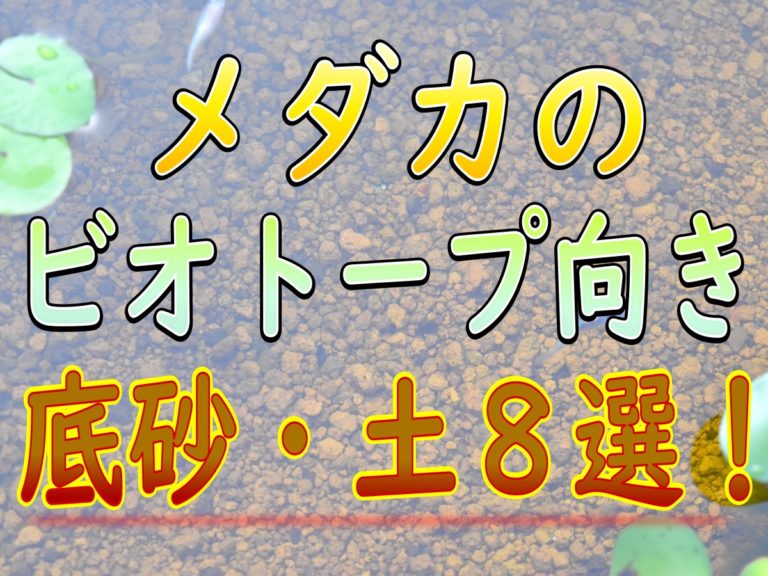
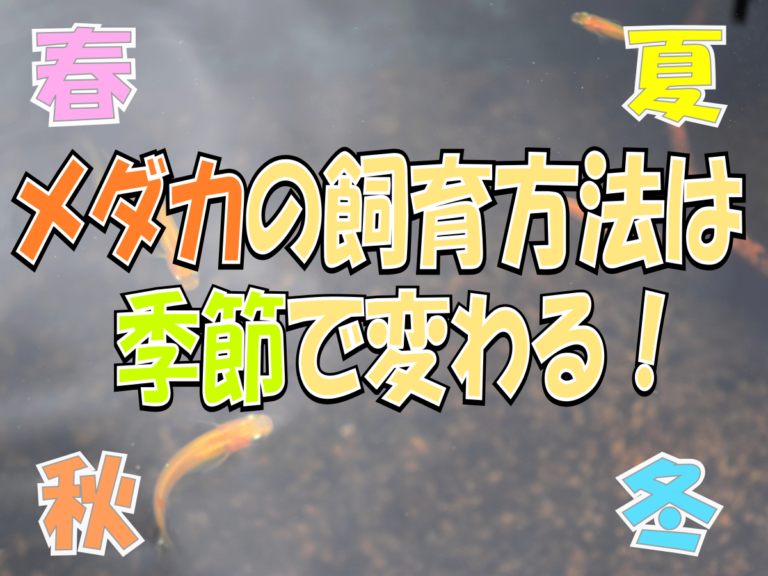
このコラムへのコメントやお悩み相談に届いた質問の回答
お世話になります。
屋外ビオトープでヌマエビを投入しようと考えていますが今現在のPHが9.0程のアルカリ性に寄った数値になっています。
PH値が高い要因でモルタルのアクの可能性もありそうです。
ヌマエビを投入するにあたりPH値はどれ位の値にすれば宜しいでしょうか?また、PH値を下げるにあたり赤玉土の投入を考えています。赤玉土はPH値を抑えるのに効果はありますでしょうか?
他に良い方法があればアドバイス頂けたら幸いです。
実際に拝見していないため、正確な回答ではないことをご了承ください。
モルタルのアクを抜いたほうが良いです。赤玉土では中和しきれないと考えています。
ヌマエビはpH7.0程度の中性がおすすめですので、9.0の状態で投入するとダメージを与えてしまいます。
数カ月間、天日や風雨にさらすのが一番良いですが、コンクリート用のアク抜き剤を使用する方法もあります。
ただ、モルタルの成分が溶け出してくるためこまめな水換えは必須です。
ヌマエビの飼い方については、こちらもご参照ください。
・ミナミヌマエビの飼い方!餌・水質・繁殖方法など飼育の基本を解説します
https://t-aquagarden.com/column/numaebi_minami
よろしくお願いいたします。