
子亀の飼い方!ミドリガメやゼニガメの赤ちゃんへ餌を与える方法など解説
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
昔から気軽に飼育することができることから、亀を飼育している一般家庭は比較的多いです。最近ではマンションなどでも、鳴かないなどの理由で一人暮らしの人が飼育することも珍しくありません。
しかし、飼い始めたものの、子亀を上手く育てられない・子亀が餌を食べてくれないと言った悩みを持つ飼い主が増えています。「水棲ガメ」と「リクガメ」に種類は分かれていますが、それぞれに適した環境や飼育方法があります。
今回は、日本でも昔から飼育されていることが多いミドリガメやゼニガメといった水ガメの子亀の飼育方法についてお話していきます。
目次
一般家庭でよく飼育されている亀の種類

ペットショップやアクアショップなどで、子亀をよく販売しているのを見ることがあると思います。子亀のうちはとても小さくて育てやすいと思いがちですが、大人になったときのサイズは約20~30cmとなかなかの体長に成長します。
一般家庭でよく飼育されている水亀にはミドリガメとゼニガメですが、どちらもそれなりに大きなサイズになります。
まずはそれぞれの特徴などについて見ていきましょう。
基本的な亀の飼育方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
ミドリガメ

ミドリガメという名称が広く知られていますが、「ミシシッピアカミミガメ」という種類です。子亀ならペットショップなどで1,000円以下で購入することができます。
頭の横に赤い色が入っているのが特徴ですが、成長すると30cm近くとかなり大きなサイズの亀なので、大きくなてからは90cm以上の水槽での飼育をおすすめします。きちんと育てれば10年~30年近く生きているカメです。
ミドリガメは特定外来種指定される可能性がある
販売目的ではない飼育や譲渡は認められます。
放流は絶対に行わないようにして、最後まで育てましょう。
残念ながら育てきれなくて近くの川や湖・池などに捨ててしまう無責任な人がいます。ミドリガメは適応力が強く丈夫なため、野生環境では在来種の生存を脅かすことが増えてしまいました。
そのため2023年現在、緊急対策外来種に指定されていますが、特定在来生物に指定される可能性があると言われています。
特定在来生物に指定されてしまうと、すでに飼育している人や、指定後に飼う場合は届け出を行わなければなりません。
また特定外来生物指定を受けた後にミドリガメを逃がしてしまったような場合は、飼い主が防除作業などの費用の一部や全額を負担するという法的な決まりがあります。
これらをご了承のうえで飼育を始めていただけると幸いです。
詳しいことが知りたい場合は、自治体や環境省などに直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
ゼニガメ

一般的にゼニガメと言われている亀は、昔は「イシガメの子亀」のことを言っていたようですが、最近は「クサガメの子亀」のことを指していることがほとんどす。
クサガメは昔元々韓国や中国などに生息していたものが、江戸時代以降に日本に持ち込まれて野生化したと言われており、現在も日本の一部地域で野生のものがいます。
最近ペットショップなどで販売されている子亀は、国内の個体数が減っているためか中国方面から輸入されたものが多いようです。
クサガメの特徴は成長するとオスは15cm~20cmほどの大きさになりますが、メスはオスよりも大きく30cm近くになるというのがまずひとつ。そして甲羅に3本の隆起(キール)があるという特徴があります。
オス・メスの違いですが、オスは成長すると体が黒くなって甲羅の模様が消えることが多いです。メスの場合も成長すると体が黒っぽくなってきますが、甲羅の模様は残っていることが多いという違いがあります。
日光浴が大好きで、自然環境では水中で餌を採っています。人間にとてもなつきやすいという特徴があるので、人気のある亀です。
子亀の飼育に必要な機材
子亀の飼育に必要なものは、飼育用のケースや脱走防止用のフタ、床材など熱帯魚飼育とほぼ同じようなものが必要となります。
飼育ケース
子亀の場合はそこまで大きな容器は必要ありませんが、大きくなたときのことも使い続けるつもりでいるなら、横幅90cm以上は必要です。
成長に合わせて容器を買い替えるつもりなら、子亀のうちは45cmくらいの水槽で構いません。しかし亀はああ見えて意外に脱走の名人なので、高さのある容器や水槽を選び、脱走脱走防止用の金網やフタを付ける必要があります。
水槽セットを購入するというのもありですが、費用を安く済ませたいのであれば衣装ケースやプラスチックの昆虫用の飼育ケースなどでも大丈夫です。
東京アクアガーデンではカメ用の水槽のオーダーメイド作成も受け付けています。
ほしいサイズのカメ用水槽がなければ、オーダーメイドで頼んでみてはいかがでしょうか。
陸地用の素材や隠れ場所
水亀は水中で生活しますが、陸上で甲羅干し(日光浴)を行うため、水場と陸地が必要になります。水で濡れている子亀が足をかけても安定できるもので、乾きやすいものを選びましょう。
市販されている砂利で高さを出して陸地を作るのもよいですが、あまり細かい素材だと子亀が誤飲してしまうので、使用する砂利は大粒のものを選びます。
市販されている園芸用の石・割れた素焼きの鉢、またペットショップで販売されている亀用の浮島などがおすすめです。
陸地のほかに隠れ場所があると、日向ぼっこをしながら調整がしやすく、人の視線でストレスを感じている時の子亀の逃げ場所にもなります。
ライト
亀は日光浴で身体を乾かし体温を上げ、日光に含まれている紫外線で体内で骨や甲羅を作るカルシウムを吸収するのに必要なビタミンD3を作ります。また日光浴をすることで、甲羅にコケが生えるのを防止したり、皮膚病の予防を行います。
そのため室内で太陽の光に当てることが難しい場合には「バスキングライト」などの保温ランプや紫外線ランプが必要となります。
この時気を付けたいのは、紫外線の中に含まれているUVBというものが必要なのですが、このUVBはガラスで阻まれてしまうという点です。
紫外線ランプを使用するときはガラスフタを外して直接当てる必要があります。しかし金網の場合は外す必要がなく、金網越しに当てることができます。
ヒーター
子亀は寒さに弱いため、春先や冬場は水温を調整してあげる必要があります。適温は20℃~25℃で、20℃以下になると食べた餌を消化できなくなってしまったり、冬眠してしまうことがあります。
成長すると地域にもよりますが、室内なら冬でもヒーターなしで飼育できる場合が多いです。
ヒーターについてはこちらの記事を参考にしてください。
カルキ抜き
水道水に含まれているカルキは、子亀に負担を与えてしまうことが多いので、水道水を使用する場合は市販のカルキ抜きでカルキを抜くか、数日汲み置きしてカルキを抜いた水を使います。
カルキ抜きについてはこちらの記事で詳しく書かれています。
カメを飼育していて水の臭いが気になるのであれば、亀用の臭いや雑菌を抑える製品が市販されているので、使用してみるのもよいでしょう。
子亀水槽の水深や水換えの頻度

子亀でも大人の亀でも水深は甲羅が十分に浸かる程度の深さで構いません。水換えですが、亀は水槽内の水を飲みますが、水槽内でおしっこなども行うので、できれば毎日、最低でも3日に1回くらいのペースで水換えを行います。
水槽内のコケやフン・餌の食べ残しなどのごみ掃除は最低でも週1回くらいのペースで取り除いてあげましょう。
子亀の餌や与え方
子亀の餌のあげ方ですが、暖かい日中に1日2~3回、大きくなったら1日~2日に1回与えます。カメ用の餌は市販品が多く、評判がよいのはテトラの「レプトミン」シリーズです。
レプトミンはミドリガメ・ゼニガメ用に作られた人工飼料で栄養バランスのよい配合となっています。こうした人工飼料をメインの餌にして、ときどきおやつ程度に次のような餌を上げると喜ぶようです。
- 動物質の餌…ゆでた鳥のささみ、レバー、刺身・コオロギやミルワームなどの爬虫類用の餌の昆虫・ミミズ・熱帯魚用の乾燥エビや生きたミナミヌマエビ・冷凍アカムシ・にぼしなど
- 植物質の餌…柔らかい水草、ゆでた小松菜やニンジン、リンゴやバナナなどの果物
ただし、パンなどの人間用に加工されたものや、他の動物用に加工されたものは与えてはいけません。加工品の中でも乳製品はカメが消化できないので要注意です。
子亀に与える餌の量
子亀は成長期なので食欲が旺盛で、1日に与える回数も多いです。1回にどれだけの量を与えるか悩む人もいますが、「数分で食べきれる量」というのが目安です。
餌の与えすぎは食べ残しが発生し、水を汚してしまいます。
- 「数分で食べ切れる量がわからない」
- 「人工飼料を何粒与えればよいかわからない」
というような場合は、カメ愛好家の間で言われている「カメの頭の大きさ1~3個分」を与えてみましょう。
一度この量で与えてみて、多いようなら少しずつ減らして適量を探してみましょう。
餌を食べないときは慌てずに様子を見よう
「子亀が餌を食べてくれない…」
初めてカメを飼育するときや、新しくお迎えした子亀でこのような悩みを抱える人がいます。
5cmくらいの小さな子亀の場合、人工飼料に慣れていないこともあるので、冷凍イトミミズや冷凍赤虫のような生餌だと食べてくれることが多いです。
様子を見ながら少しずつ生餌に細かく砕いた人工餌や他の餌を混ぜて、人工餌や植物性の餌などに慣れさせましょう。
ストレスが原因で食欲不振になることがある
カメは犬や猫のように人と慣れ親しむ生き物ではないので、必要以上にいじられると強いストレスを感じてしまい、餌を食べなくなることがあります。
ショップから購入直後は、飼育環境が変わったことでストレスを感じて食べなくなることもあるんです。
体調に問題がないのであれば、水温や気温を少し上げて1~2日そっとしておけば、餌を食べてくれるようになることが多いです。
また1匹ずつ餌の好みが異なることも多いので、餌の種類を変えてみると食べてくれるようになることもあります。
1週間くらい様子を見ても、餌を食べてくれないのであれば病気かもしれないので獣医さんに診てもらいましょう。
ペットの食欲不振問題に関してはこちらもご参考にしてください。
亀は冬眠する生き物

自然の中で生きている亀は20℃以下になると動きが鈍くなってきて、15℃以下で餌を食べなくなり、10℃以下になると冬眠します。
しかし子亀のうちは寒さに弱いため、しっかりとヒーターで適温を維持してあげましょう。
カメは脱皮する

甲羅干しを行い、しっかりと体内でカルシウムを吸収することができていると、カメは大きくなるために「脱皮」を行って、大きな甲羅を作ります。
脱皮が始まると、甲羅の見た目がボロボロになり痛々しいですが、病気ではないので自然に薄皮が剥がれていきます。剥がれ落ちた皮は水質悪化の原因にもなるので、見つけ次第取り除きましょう。
しかしカメの脱皮は、脱皮で剥がれ落ちた薄皮なのか、水カビ病なのかの判断が難しいことがあります。次のような症状がみられる場合は、獣医さんに判断してもらったほうがよいでしょう。
- 手足や首・甲羅などにある
- 水中で見ると白い綿のように見える
- 水から出てもなにかが付着している
- 付着している物の色が餌と同じ
脱皮の薄皮の場合は陸上に上がると付着しているのがわからないことが多く、水中に同じような膜が浮かんでいます。また水カビ病の場合は食欲が落ちてしまいますが、脱皮の場合は逆に元気がよく食欲が旺盛という特徴があります。
旅行に行くときはどうする?
健康で体力のある子亀なら出発前に餌を与えておけば3日くらいなら餌を食べなくても大丈夫です。
しかし気を付けたいのは餌よりも水温と水質です。夏なら日当たりがよい場所だと水温が上がりすぎ、冬は水温が下がるので水温や室温管理は、水槽用のヒーターやクーラ―を利用することをおすすめします。
さらに照明に関しては、タイマーを併用することで人がいなくても自動でオン・オフの切り替えを行うことができます。
照明用のタイマーについてはこちらの記事を参考にしてください。
亀飼育の注意点

子亀というよりは、カメの飼育全般で気を付けたいことがいくつかあります。
注意すべきことをしっかりと覚えて、カメの飼育を行いましょう。
亀の体にはサルモネラ菌がいる
子亀・大人の亀など問わずカメの体には食中毒を引き起こす「サルモネラ菌」がいます。そのためカメと遊んだり、カメを触った後は、しっかりと石けんで手を洗いましょう。
病気に注意
カメは水中で生活し、日光浴で体を殺菌します。しかし水質が悪化してしまったり、栄養状態が悪い・紫外線不足などが起きると、細菌やカビが原因で皮膚病などにかかってしまいます。
カルシウムを吸収できていないと歩けなくなったり、甲羅が柔らかくなる・脱皮に失敗するといった症状がでるのでおかしいと思ったら、動物病院で診察してもらいましょう。
まとめ:ミドリガメやゼニガメの子亀の飼育はとっても簡単!

今回ご紹介した種類意外にも水ガメの種類はありますが、一部ワニガメやカミツキガメなど飼育に向かない狂暴な種類もいる点は注意してください。
カメといっても小さな子亀のときは体がまだしっかりと出来上がっていないので、寒さに弱かったり水道水のカルキに弱いという特徴があります。
また亀は紫外線を浴びてカルシウムを吸収する栄養素と体内で作るため、照明など少し面倒と感じる人も多いでしょう。
飼育期間が長くなるにつれ、人に慣れてくれる種類もいるので、段々と愛情がわいてくる人は多いです。
しかし成長するとかなり大きくなるため、購入するときは死ぬまできちんと面倒を見て、飼いきる覚悟をする必要があります。
間違っても飼えなくなったからといって、その辺の河川や池などに放流しないで最後まで責任をもって飼育しましょう!
亀の飼育に関してはこちらもご参考にしてください。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談フォーム
お悩み相談フォーム































![GEX カメ元気 オートヒーター SH55 【ペット用品】 ホビー エトセトラ ペット その他のペット top1-ds-1482923-sd5-ah [独自簡易包装]](https://m.media-amazon.com/images/I/41JZpR8JnFL._SL500_.jpg)









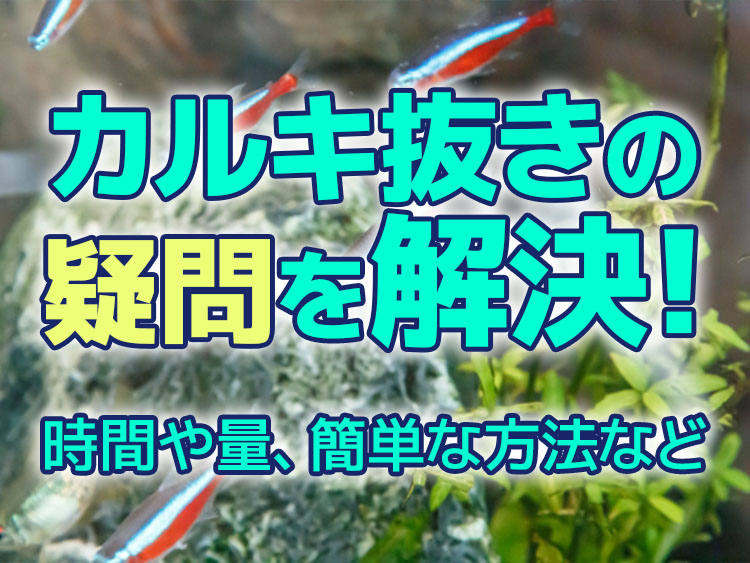

このコラムへのコメントやお悩み相談に届いた質問の回答
小さいゼニガメを2日前にもらったのですが、また我が家に来て3日目で冬眠モードに入っているのか寝てばかりいます。水温は28℃にしており、昨夜からuvライトを購入したので付けみました。本格的には今日から昼間に付けるつもりです。
5日前までは外で飼われてたカメなのですが、500円だまぐらいの子で飼育環境は浮島に人工芝でスロープを作って上がれるようにしてますが、陸の上でひたすら寝ます。まだ餌も一度もたべていません。夜はライトを消すので水槽の蓋はしめていて温度を保っています。このままの状態で飼育をしても問題ないでしょうか?冬眠モードでほとんど動かず寝てるのが心配です。冬眠モードに入っているのであればどうすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
実際に拝見しておりませんので正確な回答ではないことをご了承ください。
まだ飼育を開始されて間もないということですので、緊張しているのだと思います。
水温やライトなどの保温を行っているので、冬眠にはならないです。
餌は緊張が解けると食べ始めると思うのですが、最初はピンセットや割りばしなどを使い、目の前で揺らして興味を持たせるのが良いです。
ピンセットは長いものが良く、水草用のものでも構いません。
こちらはザリガニの記事ですが、与え方はの基本は同じなので、ご参考までにお読みください。
・ザリガニにおすすめの餌とは!与える量は?食べない場合は?疑問を解説!
https://t-aquagarden.com/column/crayfish_feed
よろしくお願いいたします。