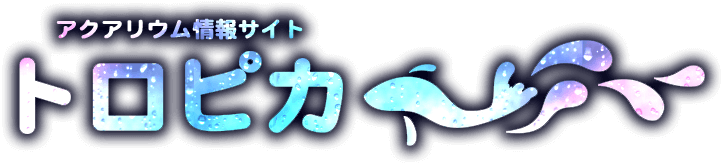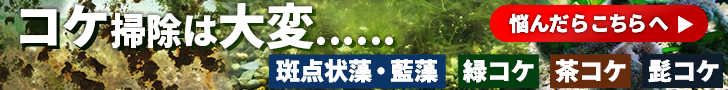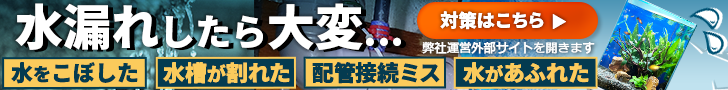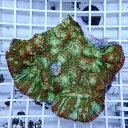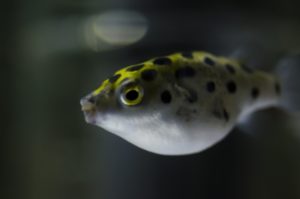アクアリウムに鮮やかな彩りを添えるサンゴは、アクアリストにとって憧れの存在の1つです。
近年では、照明や添加剤の発達によって家庭でも美しいサンゴを飼育できるようになり、多くの人が挑戦しています。
しかし、サンゴには実は毒を持つ種類がいるのです。毒性の強いサンゴは、人に健康被害を及ぼしたり、水槽内のほかのサンゴを攻撃したりすることがあります。
そのため、不用意にサンゴをレイアウトしたり、むやみにサンゴに触ったりすると、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことも。
この記事では、サンゴが持つ毒とその危険性について解説し、サンゴの毒性をランキング形式で紹介します。
また、サンゴの毒に気を付けながら安全に飼育するポイントもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
目次
実はサンゴには毒がある

独特な美しさが魅力のサンゴですが、生き物として過酷な自然界を生き抜いています。
外敵から身を守り、ほかのサンゴとスペースを奪い合うため、強力な毒を持つ種類も少なくありません。
サンゴの色彩や形に目を奪われがちですが、中には「隣のサンゴを溶かす」「人間が触れると皮膚炎や中毒を起こす」といった種類がいることも知っておきましょう。
種類ごとの毒性の種類や強さを知ることで、水槽内のトラブルを防ぎ、より安全にサンゴを飼育できるようになります。サンゴの毒についての知識を身に着け、アクアライフに役立てましょう。
サンゴが持つ毒とその危険性について

サンゴが持つ毒は、主にパリトキシンと刺胞毒の2つです。
細かな毒の種類はほかにもありますが、特にこの2つの毒に気を付けましょう。
ここでは、サンゴが持つ毒とその危険性について解説します。
パリトキシン
パリトキシンは非タンパク質性の毒素で、自然界で確認されている中でも最強クラスとも言われます。わずかな量で人体に重篤な症状を引き起こす可能性があり、加熱しても分解されません。
サンゴの中ではスナギンチャク目の一部、特にイワスナギンチャク属がこの毒を持つとされます。また、マメスナギンチャクはすべてが毒を持つわけではありませんが、外見からは判別できません。
宮崎県の研究では、有毒渦鞭毛藻と共生したスナギンチャクを魚が捕食し、その過程で毒が伝わる可能性が示唆されています。しかし、この研究は確定情報ではない点にご注意ください。
いずれにせよ、パリトキシンを含む可能性があるサンゴは、取り扱いに最大の注意が必要です。
刺胞毒
刺胞毒はタンパク質性の毒で、刺胞という特殊な細胞に蓄えられています。
刺胞は小さなバネ仕掛けのような構造をしており、触れると瞬時に毒針を発射して相手を攻撃する、という仕組みです。サンゴにとっては、防御や縄張り争いに欠かせない武器と言えるでしょう。
サンゴの持つものの中で、代表的なのが「隔膜糸」と「スイーパー触手」です。
隔膜糸は普段胃の中に収納されており、刺胞と消化酵素を持ちます。縄張り争いや防御、攻撃として使う際に伸ばされ、消化酵素を使って相手の組織を溶かしてしまうのです。
サンゴ同士の縄張り争いに使われるのが、スイーパー触手です。攻撃専用で、触手を伸ばして隣のサンゴを攻撃します。夜に出すことが多いですが、昼に出すことも。特に、ナガレハナサンゴ属やアザミサンゴ属でよく見られます。
レイアウト時などに素手で触れると、刺されて痛みや炎症を起こすことがあります。
応急処置としてはお酢で洗い流し、冷やすことが推奨されていますが、すぐに皮膚科などの医療機関を受診しましょう。
| 毒の種類 | 保有サンゴの例 | 症状 | チェックポイント |
| パリトキシン | スナギンチャク目、特にイワスナギンチャク | フグ毒よりも強い毒性、対人の場合経口摂取によって中毒症状が起きる | 購入後に水質チェック |
|---|---|---|---|
| 刺胞毒 | 多くのサンゴ 特にナガレハナサンゴ属やアザミサンゴ属 |
針入りの細胞付きの触手で攻撃。水中にこの細胞入り粘液がにじんでいる場合、水に触れただけで痛む | 素手で水に触れて痛みがあったらすぐに洗う(オスが応急処置) |
サンゴの毒性ランキングと安全な飼育ポイント

サンゴの毒性をランキング形式で紹介します。
それぞれ飼育をする際の注意点やポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
なお、入手のしやすさなどから初心者向けとして紹介されているサンゴも混じっています。
飼育しやすい=安全というわけではありませんので、十分に注意しましょう。
危険度★★★★★ マメスナギンチャクなどスナギンチャク目
スナギンチャク目の一部はパリトキシンを持ち、最も危険なサンゴの1つとされています。特にマウイイワスナギンチャクは学術的に毒性が確認されており、扱いには細心の注意が必要です。
マメスナギンチャクは改良品種として多く流通しているので、その個体が毒を持つかどうかは外見では判断できません。
そのため、「無毒かもしれないし危険かもしれない」という不確実さも手伝って、最も高い危険度に分類されているのです。
飼育の際は、強い毒を持っているつもりで飼育し、メンテナンスや株分けの際は必ず手袋を使用しましょう。
危険度 ★★★★☆ ナガレハナサンゴ属やアザミサンゴなど
ナガレハナサンゴ属(コエダナガレハナ、タコアシサンゴ、トランペットコーラルなど)やアザミサンゴは、刺胞毒の毒性が強いです。
スイーパー触手を伸ばして隣接するサンゴを攻撃しますが、特にオオナガレハナサンゴ(トランペットコーラル)は、毒性が強いサンゴとして知られています。これらを飼育する場合は、ほかのサンゴとの距離を十分に確保しましょう。
スイーパー触手は想像以上に長く伸び、さらに夜に攻撃することが多いので、気が付かないうちに隣のサンゴがダメージを負っていることも多いです。夜間にしっかり観察しつつ、攻撃が確認された場合はすぐに配置を変更しましょう。
危険度 ★★★☆☆ バブルコーラル、ハナガササンゴなど
バブルコーラルやハナガササンゴ、マルハナガタサンゴ、ディスクコーラルなどは、中程度の刺胞毒を持ちます。ナガレハナサンゴほど攻撃的ではありませんが、十分に危険なので注意しましょう。
バブルコーラルやハナガササンゴはバルーン状のポリプを持ち、柔らかい共肉は水流の影響を受けやすいため配置が難しい種類です。複数種類を同じ水槽に入れると、配置場所が重なり干渉しやすくなるので、飼育難易度はさらに高くなります
サンゴ初心者の方は、まずは一種に絞って飼育するのがおすすめです。
危険度 ★★☆☆☆ ウミキノコ、スターポリプなど
ウミキノコやスターポリプは毒性が比較的弱く、初心者にも人気がある種類です。
ウミキノコは水流と光を好むため、配置場所を工夫すれば丈夫に育ちます。
一方、スターポリプはマット状に広がって育つため、放置すると隣のサンゴを覆い尽くしてしまうことも。
状態が良いスターポリプはどんどん成長するので、配置の段階で十分な距離を取り、増えすぎた場合は定期的にトリミングしましょう。
ただし、毒性の弱いこれらのサンゴは、強いサンゴに攻撃されると負けてしまいます。そのため、強い毒性を持つサンゴの隣には置かないようにしましょう。
危険度 ★☆☆☆☆ キッカサンゴ
キッカサンゴは毒性そのものは強いものの、スイーパー触手が短く、ほかのサンゴを攻撃できる範囲が限られています。形状も平たい板状で接触事故が起きにくいことから、比較的安全に飼育できる種類と言えるでしょう。
配置の自由度が高いため、初心者が悩みやすいサンゴの配置がしやすく、かつ育てやすいメリットを持ちます。
ただし、攻撃される側としてのリスクはあるため、触手が長く伸びるほかの種類からは十分な距離をとってください。
毒に気を付けながら安全に飼育するポイント
毒に気を付けながら安全にサンゴを楽しむためには、以下の点を意識することが大切です。
- サンゴ同士を近づけすぎない
- なるべく直接触らない
- 株分けやカットの際は防護装備を使う
- 水質や水温を安定させる
- サンゴをつつく魚は避ける
まず、サンゴ同士は十分に距離を取ることが基本です。スイーパー触手は思った以上に長く伸びることがあり、気付かないうちに隣のサンゴを攻撃してしまうケースがあります。
また、なるべく直接触れないことも重要です。
手で動かすとサンゴにストレスを与えるだけでなく、毒性の強い種類では、飼育者自身が粘液や触手に触れてしまう危険があります。
掃除の際にはマグネットクリーナーやピンセット、ゴム手袋などを上手に活用しましょう。
成長して大きくなりすぎた場合には、接触を防ぐためトリミングや株分け(コーラルカッターでカット)をすることがあります。カットした際に毒を含む粘液や体液を分泌して危険なので、手袋をして作業しましょう。
水質や水温を安定させるのも、サンゴ飼育では重要なポイントです。水の蒸発を防ぐためにフタを使用し、水温管理を徹底するなど、サンゴにとってより良い環境を目指しましょう。
混泳させる魚種にも注意が必要です。つつくだけならまだしも、サンゴをひっくり返す種類もいるので、混泳相手は慎重に選びましょう。
まとめ:サンゴの毒性ランキング!実は注意が必要なサンゴと安全なサンゴ・それぞれの飼育ポイント

サンゴの毒性ランキングや、飼育ポイントなどについて解説しました。
サンゴの中には、人にとっても危険な毒を持つ種類が存在します。特にスナギンチャク目の一部は、最強クラスのパリトキシンを含む可能性があるため、注意しましょう。
一方で、毒性が弱く、配置にさえ気を付ければ比較的安全に飼育できるサンゴもいます。
大切なのは「サンゴ同士の距離を確保する」「素手で触らない」「適切なメンテナンスアイテムを使う」といった、飼育の基本を守ることです。
美しいサンゴの世界は、正しい知識があればより安心して楽しむことができます。
毒性を理解したうえで、あなただけの安全で華やかなサンゴ水槽を作り上げましょう。
| 名前(流通名) | 危険度 | 危険な理由 |
| マメスナギンチャク | ★★★★★MAX | パリトキシン保有個体が紛れている可能性があるから |
|---|---|---|
| コエダナガレハナ | ★★★★☆ | 刺胞毒の毒性が強く、スイーパー触手も長い |
| タコアシサンゴ | ||
| トランペットコーラル その他ナガレハナサンゴ属 |
||
| アザミサンゴ | ||
| バブルコーラル | ★★★☆☆ | 中程度の刺胞毒・特徴から配置が難しく他サンゴと接触リスクがある |
| ハナガササンゴ | ||
| マルハナガタサンゴ | ||
| ディスクコーラル | ||
| ウミキノコ | ★★☆☆☆ | 毒性が比較的弱い・配置場所チョイスに成功したら育てやすい |
| スターポリプ | ★★☆☆☆ | 毒性が比較的弱い・ただし繁殖力強めなので注意 |
| キッカサンゴ | ★☆☆☆☆ | 毒性そのものは強め・だけどスイーパー触手が短い |

幼少の頃より生き物が大好きです。身近な川魚から熱帯魚、両生・爬虫類までさまざまな生き物を飼育してきました。 大学で海洋生物学を学び、水族館で働いた経験も併せて、アクアリウムが楽しくなるようなコラムを紹介していきます