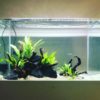水槽の掃除はおっくうなものですが、美しいアクアリウムを維持するためには、しっかりメンテナンスすることが大切です。
そんな時、水槽の内側がぬるぬるする・ろ過フィルターの電源を入れるとゴミのようなものが出てくることがあります。
この「ヌメリ・ゴミ」はバクテリアの『バイオフィルム』『コロニー』であることがほとんどです!
ぬめりを除去する方法・発生させないための対策について詳しくご紹介していきます。
水槽にできるぬめりの正体は
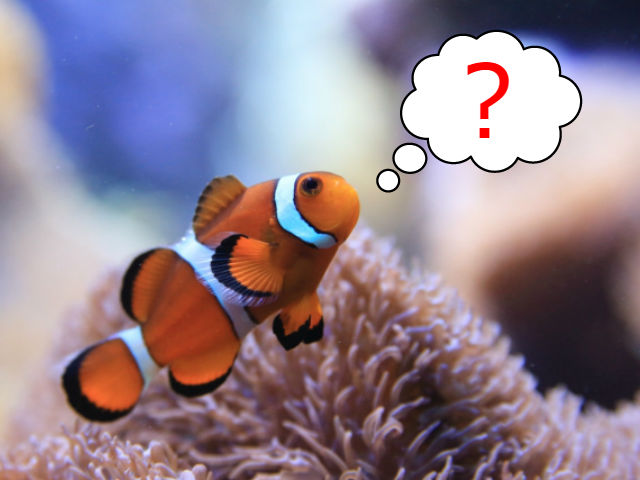
水槽の内側やパイプにつく、このヌルヌルは何なのかを解説します!
水槽のぬめりはバクテリアの集合体です
このヌルヌルは、水槽内のバクテリアが集まって出来たものです。バイオフィルムと呼ばれています。
水槽内のバクテリアは、魚やエビの排泄物や、食べ残した餌、水草の枯れたものなどを分解してくれる大切な存在です。
バクテリアたちは小さな菌類ですが、コロニーをつくって生活しています。
EPS(extracellular polysaccharide 細胞外多糖のこと・ヌルヌルする物質)という成分を分泌し、その中に集合して生活しているのです。
これが触るとヌメヌメする水槽に発生する「ぬめり」の正体です。
ぬめりが発生するメカニズム
バイオフィルム自体は水槽に無害ですし、飼育水にバクテリアが住み着いている証ですから、むしろ歓迎できる状態と言えます。
では、どういう時に、この「ぬめり」が気になってしまうほど発生するのでしょうか。
それは、水槽内の養分が増えすぎたときです。
- 魚の数を増やした
- 栄養の高い餌に変えた
- 餌の量を増やした
- 水換えをサボっている
- ろ過フィルターの掃除をサボっている
いずれも水槽内の養分を過剰に蓄積させてしまう原因になります。
養分が増える=バクテリアが増える=コロニーが増えるという具合に、連鎖的にぬめりは増えていきます。
やがて、パイプやホースのなかに塊として定着することがあります。
ろ過フィルターの電源をONにするとたまにゴミのようなものが噴き出すことがありますが、あれは水流の勢いで剥がれたバイオフィルムです。
水槽内の養分が過剰になると、コケや生体の病気が発生する場合がありますので、清潔な水槽環境を心がけましょう。
また、過剰な養分以外にも、水温の上昇によるバクテリアの活性でも厚めなバイオフィルムが発生する場合があります。
ぬめりは取り除くべき?
「水槽内のバクテリアは大事」ということは水槽運用の基本です!バクテリアのコロニーなら有益と言えます。
とはいえ、バイオフィルムが厚くなりすぎると水流にも若干影響は出ます。また、クリアタイプの配管やホースを使用していると、「汚れがついているみたいで嫌だ」と感じる方もいます。
では、ぬめり(バイオフィルム)を取り除くことについて、どう判断すればよいのか。
それは水槽全体を見ることでわかります。
魚も元気・水も透き通っているのであれば、今すぐに取り除かなければならない!という緊急事態ではないです。
適性な水質が保たれていて、それにはバイオフィルムも一役買っていると言えます。
ただ、あまりにもバイオフィルムが目立ち、「水流の勢いが落ちたような?」と感じたらパイプブラシなどで掃除しましょう。
水流が落ちると、コケの発生や生体の病気を引き起こす可能性が高まってしまいます。
ぬめりを除去する方法

ではどのようにしてバイオフィルムを取り除くかについてご説明します。
パイプブラシなどで清掃する
シンプルにホースなどは交換してしまってもいいです。
交換できない配管などは、ブラシで擦ればぬめりをスピーディに解決できます!
配管ブラシは100均でも購入できますが、できるだけ長いものがおすすめです。
東京アクアガーデンではパイプブラシでの清掃のほか、界面活性剤の入っていない衣類用ハイターやブリーチでまとめ洗いすることもあります。
スポンジで掃除する
水槽壁面などのぬめりはコケ由来のことも多いです。
そんな時はメラミンスポンジなどで擦り取ることになります。
もちろん、コケクリーナーも有効です。
余談ですが、水槽壁面にバイオフィルムができる前に水を注ぐと、気泡が付いたりします。
水換えをする
水槽の水換えをこまめに行えば、過剰な養分が溜まるのを防げます。
水換えはそれだけでなく、水槽の状態を整える基本にして最高の方法です。
水を換えれば、たまりすぎた栄養分(硝酸塩)を減らせることができますのでバイオフィルムの発生しずぎを防げます。
ぬめりを発生させないようにするには

バイオフィルムを掃除で取り除いた後には、今後は出来るだけバイオフィルムが発生しないように心がけていきましょう。そのための対策をこちらでご紹介します。
魚・餌の量の見直し
養分のもとである、魚のフンを減らすのも良い方法です。
かわいいのでついつい餌を与えがちですが、食べ残しなども水槽内の養分になってしまします!
一般に「魚の体長1cmあたり1リットルの水が必要」と言われるように、魚の体長に合った水量を準備するのは、アクアリウムを作る上では基礎的な考え方です。
過密飼育は魚同士のケンカ・魚のストレス・魚の病気の元になりますので、ほどほどの数で飼育しましょう。
金魚は非常に水を汚すので、1匹につき水10リットルとも言われています。
餌の量は魚の種類や状況によっても異なりますが、餌を与えたあとはしばらく見守り、餌を食べきっているかどうか観察しましょう。残すようなら多すぎです。
水が出来るまで様子を見る
水槽を立ち上げたばかりであれば、まだ水の状態が整っていないということも考えられます。
バランスが悪いためバクテリアの一部が死んでしまうこともあります。
そうすると起こるのが『飼育の白濁り』です。
こういった場合は水のコンディションが落ち着くまで、こまめな水換えをおこない様子を見ましょう!
また、水換えの頻度が適正か不安なときは水質検査をするのも1つの手です。
水槽内の水温を適正に保つ
夏場によく見られるのですが、水温が上がりすぎるとバクテリアが大繁殖し、バイオフィルムが形成されやすくなります。
飼育している魚の種類にもよりますが、一般的な熱帯魚に適正な水温は22~28℃と言われています。それを超えてしまうような場合は、エアコンを稼動させるか、水槽用クーラーなどを使用して水温を下げましょう。
まとめ:水槽のバイオフィルムについて!ぬめりや塊を除去する方法と発生させない対策

水槽のぬめり(バイオフィルム)の正体・原因・除去方法・発生防止方法についてご説明してきました。
バイオフィルムは有益なバクテリアの集合体とはいえ、やや見た目にも影響することから気にする方もいます。
とはいえ、「バクテリアがたっぷり育っているんだな」という温かい気持ちでそれほど気にする必要もないです。
しかし、放置するとそこにコケが生えるベースにもなりますから、目につく場所はしっかりと掃除しましょう!
きれいなアクアリウムを楽しんでくださいね。
トロピカプレゼンテーターのぶっちーです(。-`ω-)
この記事が、皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。
YouTubeトロピカチャンネルもご贔屓に!
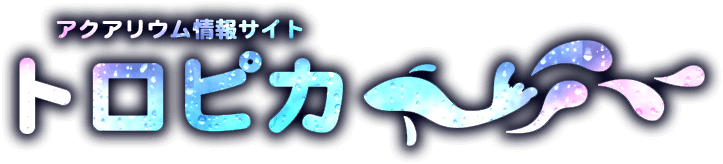
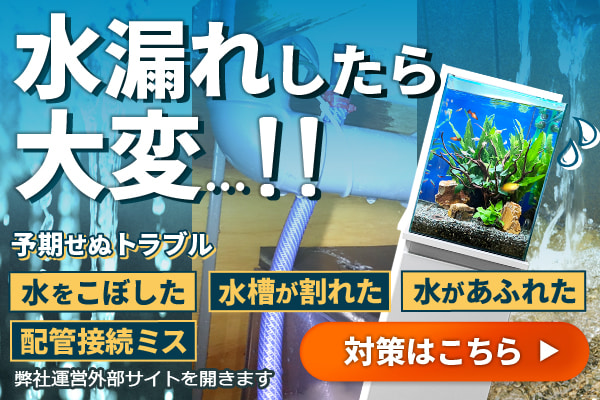



![[Yヤクニタツ] 2個セット パイプブラシ ホースクリーナー 水槽クリーナー 水族館ブラシ チューブブラシ ワイヤーブラシ ホースパイプブラシ ステンレス製 アクアリウム フィルタブラシ パイプ クリーナー 水槽 両頭 清掃 長さ155cm (ホワイト+ブルー)](https://m.media-amazon.com/images/I/41N8CqtnksL._SL500_.jpg)