カニは食用として広く流通しており、子ども向けの童話にも登場するなど、古くから私たちにとって身近な生物です。カニと聞くと深海にすむ食用の大型種を想起し、飼育する生物という発想を抱く人は少ないかもしれません。
しかし、近年では鮮やかな体色をした「ドワーフクラブ」などの小型種が知られるようになり、基本的に丈夫で飼育しやすいため、ペットとして注目を集めています。ここでは、カニについて自宅でも飼育が可能な種類や飼育方法についてご紹介します。
目次
飼育できるカニの種類と育て方を動画で解説
この記事の内容はYoutubeトロピカチャンネルでもご覧いただけます。
おすすめのカニの種類やカニの飼育方法を音声付きで解説しています。
YouTubeチャンネル『トロピカチャンネル』は水辺の生き物の飼育方法から、水槽レイアウトまで、アクアリウム情報を動画でわかりやすく解説しています。
チャンネル登録をぜひお願いします!
カニの飼育について

カニとは十脚目(エビ目)短尾下目(カニ下目)に属している甲殻類の総称で、現在のところ全世界で約7000種類が存在しています。深海から陸上までその生息範囲も多岐に渡るため、飼育するためにはその種類がどのような環境で生活していたか把握することが重要です。
さて、カニと聞くと「毛ガニ」や「タカアシガニ」など、食用として広く流通している中~大型の種類を思い浮かべる方も多いと思います。
しかし、これらのカニを飼育するとなると、水温や水質の変化にデリケートなために水族館並みの設備が要求されるので、家庭での飼育は現実的ではありません。
そのため、ここで紹介する種類は、ある程度の温度や水質の変化に耐え得る、陸生から半陸生、または海の浅場に生息する小型の品種がメインです。
比較的飼育しやすい小型のカニは、多くの場合ペットショップで購入することができますが、種類によっては川や海などで採取できるものもいます。
身近なフィールドで採取したカニを自宅の水槽で飼育するのは、とても楽しい経験になるはずです。
自宅で飼育できるカニの種類
自宅で飼育できるカニの種類とその飼育方法を、淡水と海水からそれぞれご紹介します。
飼育しやすいカニの特徴としては、以下の点が挙げられます。
・小型で大きなスペースを必要としない
・飼育用生体として流通量があり入手しやすい
・餌を選り好みせずに食べてくれる
自宅で飼育できるカニの種類は意外に多く、サイズや体色など飼育者の好みによって選ぶ楽しさがあります。
ぜひ、このコラムを参考にお好みのカニを探してみましょう。
淡水カニ
渓流や河川、河口付近に生息するのが淡水カニです。
日本に生息する淡水カニも多く、採取して自宅で飼育することもできます。
淡水カニは水槽で管理しやすい品種が多いので、初めてカニを飼育する方に特におすすめです。
淡水カニの入手方法と採取する際の注意点を以下の表にまとめました。
| 名前 | 採取 | 購入 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サワガニ | △ | ○ | 一部の自治体・一部の品種は採取が禁止されている。 |
| ドワーフクラブ | × | ○ | 東南アジアに生息するため、日本での採取は難しい。 |
| ハマベンケイガニ(レッドアップル・クラブ) | × | ○ | 日本にも生息しているが、レア種であり個人レベルで採取できる可能性はかなり低い。 |
| アカテガニ | ○ | ○ | 地域によっては絶滅危惧種に指定されているため、事前に確認が必要。 |
サワガニ
日本の固有種で、水質の良い小川や渓流などに住んでいて、冬から春にかけて冬眠します。
サイズは全長で5~7cm程度と、飼育しやすいサイズです。餌を比較的選ばずに食べてくれるのも飼育難易度を下げているポイントです。
水温は低めで飼育すると成功しやすいです。
日本の広い地域に生息しているため、最も身近で採取しやすい淡水カニと言えるでしょう。
しかし、一部の自治体ではサワガニの採取や持ち帰りが禁止されています。
また、私有地や国立公園などの保護区でないことを事前に確認しておくことが大切です。
沖縄県などには希少なサワガニの近縁種・個体群が生息しており、条例で採取が禁止されています。
ドワーフクラブ
インドネシアなど東南アジアの熱帯地域に生息しているカニで、陸生傾向が強くあまり水には入りません。甲幅2cmほどの小型の種類で、甲羅とハサミが紫色に染まる「ヴァンパイアクラブ」や、同じく赤色になる「レッドデビルクラブ」などの品種が人気です。
ハマベンケイガニ(レッドアップル・クラブ)
沖縄県から台湾、インドネシアなど西太平洋に分布しており、マングローブ林や海岸林に生息しています。甲幅3cm前後で、体色は黒色を基調にハサミが赤色になる個体が多いです。ショップなどでは、「レッドアップルクラブ」の名前で販売されていることもあります。
アカテガニ

国内では青森県から九州にかけての広範囲で分布しているカニです。海岸や河口から1Kmくらいの上流までの陸地に生息しており、巣穴をほって生活しています。
陸生が強く湿地にさえ居れば長期間水に入らなくても生きられます。甲幅は3.5cm程度で、体色は灰色を基調に甲羅の前縁からハサミにかけて橙色から赤色に染まり、爪先は白色になります。
国内でも一部の地域では絶滅危惧種や準絶滅危惧種に指定されており、採取が禁止されているため、事前に自治体のホームページを確認しましょう。
モクズガニ

日本全国に生息しており、毛の生えた大きなハサミが印象的な淡水カニです。
淡水と海水の両方を移動することができ、成体では甲幅が最大7〜8cm程度にまで成長します。国内に生息する淡水カニの中では迫力のあるサイズ感です。
採取することも可能ですが、食用としても流通しているため漁業権が設定されていて採取が禁止されている地域もあります。
海水カニ
海中や砂浜などを主な活動域としているのが、海水カニです。
海水を準備する必要があるため、飼育難易度は淡水カニに比べると上がります。
また、日本に生息する飼育可能な海水カニもいますが、漁業権が設定されている地域ではカニの採取が禁止されている場合もあります。
小型のカニであっても油断せずに、ルールに従って採取しましょう。
海水カニの入手方法と採取する際の注意点を以下の表にまとめました。
| 名前 | 採取 | 購入 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| スナガニ | ○ | ○ | 地域によっては希少野生動植物に指定されており、採取が禁止されている。 |
| イソクズガニ | ○ | ○ | 漁業権が設定されている場合は採取できない。 |
| カラッパ | ○ | ○ | 漁業権が設定されている場合は採取できない。 |
| エメラルドグリーンクラブ | × | ○ | カリブ海に生息するため、日本での採取は難しい。 |
| キンチャクガニ | △ | ○ | 沖縄にも生息しているが、レア種であり個人レベルで採取できる可能性はかなり低い。 |
スナガニ
神奈川県以南の太平洋側から台湾、東南アジアまで広く分布しており、砂浜に生息しています。潮干狩りの際に砂浜でよく見られるカニで、成体でも甲幅2~3cmほどの小型の種類です。
砂と似た色(保護色)をしていることから、ゴーストクラブという呼び名もあります。
イソクズガニ

千葉県から沖縄県、台湾から東南アジアにかけて分布しており、沿岸部にある岩礁帯の潮間帯に生息しています。甲幅は3~4cm程度で、甲羅は洋梨型をしており、体色は全身が褐色です。
体に海藻の切れ端などのゴミをたくさん付着させて、カモフラージュする性質を持ちます。
カラッパ
カラッパ科に属するカニの総称で、「ソデカラッパ」や「トラフカラッパ」、「メガネカラッパ」などの品種がいます。甲幅は5~15cmほどで、甲羅はドーム型をしており縁が張り出しているので、歩脚を折りたたんでうずくまることができます。
エメラルドグリーンクラブ
主に大西洋西部のカリブ海に生息している、甲幅3cm程度の小型のカニです。
名前の通り緑色の体色が美しく、植物食性が強いことが特徴です。
エサとなるコケや藻が十分なら他の生体に危害を加えることが少ないため、海水水槽のクリーナー生体として人気があります。
ただし、エサが不足している状態だとサンゴ等を害する可能性があるので、混泳させる場合は十分ご注意ください。
キンチャクガニ
西太平洋からインド洋などに広く分布しており、潮間帯から水深10m程度までのサンゴ礁に生息しています。
甲幅1~1.5cmほどの小型の種類で、両ハサミに「カサネイソギンチャク」を携行する独特の生態を持ったカニです。
体に入る幾何学的な模様が美しく、鑑賞性にも優れます。
自分で採取する場合の注意点
日本国内には様々な淡水カニ・海水カニが生息しており、採取したカニを自宅で飼育することも可能です。
しかし、採取する場合には、その地域で設定されている条例やルールに従うことが最重要です。
例えば、ある地域では自由に採取できるカニでも、別の地域では絶滅危惧種に指定されていて捕獲自体が禁止というケースがあります。
また、漁業権が設定されている場所もあるため、カニを採取する際には事前の十分な調査・確認が必要ということを覚えておきましょう。
さらに、採取したカニを別の場所に放流したり、自宅で飼育していたカニを川や海に放すことも避けるべきです。むやみな生体の放流は、生態系のバランスを崩したり、病気を拡大させてしまうなどの予期せぬ事態を招くことがあります。
カニに限らず、生体を採取・飼育する際には長期的な視点で責任を持って管理することが最も大切です。
カニの飼育に必要な道具

カニの飼育には、主に以下の道具類が必要です。
- 水槽
- 砂、砂利
- ろ過装置(フィルター)
- 流木、石、シェルターなど
- ヒーター、クーラー、冷却ファン
- フタ
- エサ、エサ入れ
- カルキ抜き剤
- 人工海水(海水カニのみ)
カニ飼育に必要となる代表的な道具について、さらに詳しく解説します。
水槽・フタ
水槽は昆虫飼育用のプラケースや衣装ケースなどでも代用が可能です。しかし、プラケースは傷がつきやすいことと、衣装ケースは表面のコーティング剤がカニに悪影響を与える恐れがあるので、ガラス水槽での飼育をおすすめします。
カニは縄張り意識が強い生物なので単独飼育が基本ですが、60cm水槽クラスの大きさであれば流木やシェルターなどで隠れ家をたくさん作ることで、2~3匹程度なら同時に飼育が可能です。
また、カニの飼育には床面積が広ければ高さはあまり必要ありませんが、あまり低いと脱走されやすくなるので注意してください。
特に陸生と半陸生のカニは意外と身軽で、水槽のレイアウトなどをよじ登って脱出を図ることがよくあります。カニの飼育にフタは必須で、簡単には外れないよう重りなどを載せてしっかりと固定してください。
砂・砂利
陸生と半陸生のカニは陸地が必要なので、底に敷く砂や砂利が必要です。また、海中に住むカニに関しても、種類によってはベアタンクでも飼育は可能ですが、底砂を敷いてあげた方がストレスを軽減できます。
底砂の材質は特に問いません。熱帯魚用に販売されている「大磯砂」や「サンゴ砂」を利用すると良いでしょう。
底砂の選び方としては、ろ過装置に底面式フィルターを用いる場合は、あまり細かい砂を導入するとフィルター内部に砂が侵入してろ過能力が低下するので注意してください。一方で、スナガニなど砂に潜る習性があるカニを飼育する場合は、潜りやすいように細かい砂を導入する必要があります。
ろ過装置(フィルター)
陸生と半陸生のカニの飼育に適したフィルターは、底面式フィルター・水中フィルター・投げ込み式フィルターなどです。
底面式フィルターや水中フィルターは水中ポンプで水を循環させるので、ポンプの熱が飼育水に伝搬して水温を上げることがあります。陸生と半陸生のカニは少ない水量で飼育するので、特に夏場の水温上昇には注意してください。
投げ込み式フィルターは手軽ですがろ過能力は低く、メンテナンスを怠ると簡単にろ過能力を失う点には留意してください。
海生のカニに適したフィルターは、外掛け式や底面式、上部式や外部式などです。それぞれにメリットとデメリットがあるので、飼育環境に適したものを選択してください。
また、ある程度の大きさに成長する力の強いカニは、フィルターのパイプやチューブを傷つけたり、接続部を外してしまう可能性があります。
ここで紹介した以外のカニを飼育する場合には、パイプ類を石などで固定するなど、レイアウトを工夫してトラブルを未然に防止しましょう。
カニの飼育方法

カニを健康的に飼育するために必要となる、基本的な設備や飼育水についてご紹介します。
淡水カニ・海水カニでは整えるべき飼育環境が多少異なりますが、特別な器具を用意する必要はありません。
カニの大きさに合った水槽を設置し、定期的にエサやりと水槽のメンテナンスを行いましょう。
それぞれの飼育ポイントについて、以下の項目で詳しく解説します。
水温・水質・水深
カニの飼育が可能な水温の範囲は5~28℃で、適した水温はカニの種類によって異なります。
日本の東北地方にも生息している種類は、5℃程度でも冬眠することでヒーターなしでも越冬が可能です。
しかし、亜熱帯と熱帯地域に生息しているカニは15~20℃が下限となるので、冬場はヒーターで加温しなければなりません。
陸生と半陸生カニの場合は、水槽全体を加温できるパネル式やフィルム式のヒーターを用意してください。局所的に加温する小動物用のシェルター式のものは、乾燥してしまうのでカニの飼育には利用できません。
海生カニの場合は熱帯魚用のヒーターで大丈夫です。また、一般的なカニは30℃を超えるような高温には弱く、特に海生カニは顕著なので、夏場は必要に応じてクーラーや冷却ファンで水槽の温度を管理してください。
カニが好む水質は一般的に中性~弱アルカリ性で、硬度も低いよりかは高めを好みます。飼育水は淡水生・海水生のいずれも水道水がベースで構いませんが、必ずカルキ抜きを行ってから使用してください。
汽水に生息する種類は、一部の種は慣らせば完全淡水でも飼育が可能ですが、やはりある程度の塩分濃度があった方が長生きする傾向にあります。生息地の環境に合わせることが大切です。
汽水を再現するのであれば、人工海水を薄めに作ると良いでしょう。人工海水と塩水(しおみず)は全くの別物なので、間違っても水道水に食塩を溶かした水で飼育しないようにしてください。
ベストな水深は飼育するカニの種類や大きさによって異なります。
水深の設定目安としては、甲幅3cm程度の小型のカニでは体高の3~5倍、モクズガニなどの少し大きめのカニは15~20cm、完全水棲で泳ぎ回るタイプのカニは30cm以上です。
水深は画一的に設定するのではなく、飼育匹数やエサの取りやすさなどを観察しながら、最適な水深を見極めましょう。
エサについて
カニは雑食性なので基本的に選り好みせずに何でも食べてくれます。ただし、同じものばかりを与えていると、本能的に栄養バランスの偏りを避けようとするためか、食べなくなることがあります。
単一のエサを与え続けるのではなく、様々な種類のエサを用意しておくことが大切です。
種類
エサは動物質のものと植物質のものをバランスよく与えましょう。
動物質のエサとしては、魚やイカの切り身、乾燥エビ、シラスなどが候補として挙げられます。また、植物質のエサは野菜や果物の端材で賄うことが可能で、淡水カニであれば金魚藻などの水草、海水カニならワカメなどの海藻も食べます。
ただし、アクや匂いが強い野菜と柑橘類は与えない方が無難です。それから、市販されている「ザリガニのエサ」はカニにとっても総合栄養食となるので、たまに与えると良いでしょう。
エサの与え方
底砂に直接置くと汚れの原因になりやすいので、エサ入れに入れて与えましょう。頻度としては種類にもよりますが、1~2日に1回程度を目安にしてください。食べ残しは底砂や水の汚れの原因になるので、発見次第取り除いておくと水換えや底砂の洗浄などのメンテナンスの頻度を抑えられます。
レイアウト・飼育環境について
カニの生息範囲は広く、種類によって好みの飼育環境も様々です。また、レイアウトで高さを出し過ぎると、石や流木をよじ登って脱走するリスクが高まります。さらに、カニは薬剤を使いにくい生体のため、病気やケガの発生リスクが低い環境を整えることも大切です。
まずは飼育するカニの性質をよく調査し、最適な環境を知るところから始めましょう。
陸生・半陸生カニ
陸生と半陸生のカニは陸地と水場が必要なので、底砂を厚く敷いて陸地にする部分と、薄く敷いて水場にする部分を作ってください。砂に潜るスナガニなどの種類は、陸地部分は少なくとも20cm程度の厚さを持たせると良いでしょう。
それから、流木やシェルターなどを設置して隠れ家を作ります。同一水槽内で複数匹を飼育する場合は多めに入れてください。
飼育水はカニの全身が浸かる程度の量があれば十分ですが、水量が少ないと水質の悪化が早く、頻繁なメンテナンスが必要となります。カニが自力で陸地に上がれるようになってさえいれば、水深が深い分には構いません。
これらの点を踏まえて、陸生・半陸生カニの飼育におすすめなのが「アクアテラリウム」です。アクアテラリウムは陸地と水辺の両方を備えたレイアウト水槽で、より自然に近い状態でカニの様子を観察することができます。
初心者の方でもチャレンジしやすい、アクアテラリウムの簡単な作り方・始め方についてはこちらの記事をご覧ください。
海生カニ
海中に住むカニの場合は、海水魚を飼育する場合と環境はあまり変わりません。底に何も敷かないベアタンクでも種類によっては飼育は可能ですが、サンゴ砂などを敷いてあげるとカニがより落ち着けます。
また、ライブロックやシェルター、石組みなどで隠れ家も用意してください。特に混泳させる場合は多少の隠れ家は必須です。
さらに、海生カニの場合は水位に注意してください。水が蒸発して塩分濃度が高くなるとカニに悪影響を与えてしまいます。水位が低くなってきたら、カルキ抜きをした水道水を追加する「足し水」を行ってください。
メンテナンスについて
カニを飼育していると、フィルターでろ過を効かせていても水は徐々に汚れていきます。水中の有害物質の量が、カニの成育における許容量を超過してしまうとカニは死んでしまいます。そのため、定期的に「水換え」や底砂の洗浄を行わなければなりません。
水換えの頻度は飼育環境に大きく左右されますが、目安としては上述した陸生・半陸生カニの場合で1~2週間に1回程度、海生カニで1カ月に1回程度です。カニは基本的には丈夫ですが、水質の急変には弱い面があります。
換える水の量は飼育水の全量に対して1/3~1/5程度の量に留めてください。もし何らかの理由で水換えの頻度を増やしている場合は全量の1/10程度に抑えるなど、水槽の状態に合わせて適宜調整しましょう。
底砂の洗浄を行うときは洗剤などは使用せずに水道水でよく洗い、天日干しをして殺菌・消毒をしてから再利用すると良いでしょう。
カニ飼育のよくあるトラブルと対処方法
カニを飼育していると他の生体を飼育している時とは異なる、カニ特有のトラブルが生じることがあります。
カニ飼育のよくあるトラブルとその対処法・予防法について詳しく解説します。
共食い
雑食傾向の強いカニは、複数匹を同じ水槽で飼育していると共食いのリスクが高まります。特に、脱皮直後の甲羅が柔らかいタイミングや活力が低下する夏場には、共食いが起こりやすく危険です。
共食いを避けるためには、動物性のエサを定期的に与えて栄養バランスを保ち、飼育数よりも多い隠れ家を用意しましょう。また、脱皮直後のカニはパーテーションや別容器で隔離すると安心です。
水草を食べてしまう
カニの多くは雑食性で、水槽に植える水草を食べてしまいます。また、カニはハサミの力が強いために、しっかりと根を張っていない水草は簡単に引き抜かれてしまいます。
カニ水槽に水草をレイアウトしたい場合は、人工水草で対応するか、多少は食べられることを前提としてアヌビアス・ナナやミクロソリウムなど、根を伸ばしてしっかりと活着する水草を選びましょう。
病気と体調不良
水質悪化や水温変化などの原因によってカニが病気になってしまうこともあります。特にカニ飼育で発生しやすいのは、白い綿のようなものが体表に付着する「水カビ病」です。
水カビ病は水質が悪化することで発生リスクが高まるため、エサの食べ残しをこまめに取り除き、定期的な水換えを欠かさないことが重要です。
もし水カビ病が発生してしまったならば、脱皮するまで水カビ部分を優しく取り除いて様子を見るか、どうしても治らない場合はシュリンプ類に使用可能な薬剤を薄めて使い、治療しましょう。
多くの魚用薬、特に銅が入った薬は甲殻類に悪影響があるため、隔離水槽に移動させて体力回復を目指すのが無難です。
塩水浴による治療も効果がありますが、回数が多い・時間が長いと脱皮不全などの別のトラブルが起きることもあります。
塩水浴は1日1回、10〜15分程度に留めるのがベストです。
においがする
定期的な水換えを怠っていると、カニ特有のにおいが発生することがあります。特に、水槽の水深が浅いと飼育水が悪化しやすいため、陸生・半陸生のカニであってもある程度の水量を確保することが重要です。
エサの食べ残しをこまめに取り除き、底砂掃除を行ってメンテナンスしていれば、においの発生を抑えることができます。
カニ飼育経験者の声
トロピカ運営陣の中に、サワガニを飼育した経験がある方に話を聞きました。
「(淡水)カニは水合わせと水温合わせさえできてればだいたい平気だった」という第一声に、『あっそうなんだ、飼いやすそう』と思ってしまいますが、逆に水合わせと水温管理に問題があるとすぐに調子を崩してしまうのだそうです。
飼育されていたのは小学生低学年、クーラーにヒーターにと機器をそろえることは難しかったそうですが、以下のポイントに気を付けたことで、そのサワガニは4年も生きたのだとか。
- 水合わせ(水槽に投入する際に時間をかけて飼育水の水質や水温に慣れさせること)を入念に
- 意外と水を汚しやすいので水槽投入後は、水換えをこまめに行う
- 水質管理をしっかりめに行う
- 水合わせができない時は、最初の3日は霧吹きで飼育して、餌を食べて万全になってもらう
霧吹きの水は、飼育水と同じくカルキ抜きした水を使いましょう。
この経験を活かしたサワガニの飼育記事もありますので、ぜひご覧ください!
まとめ・カニの飼育方法について

カニは様々な種類が存在し、その生息環境や好みのエサは多岐に渡ります。カニを飼育するためには、ご自身が飼育したい種類が本来はどのような環境で生活していたかを把握することが重要です。
カニは基本的には丈夫で飼育しやすい生物ですが、本来の生息環境とかけ離れた飼育環境では長生きできません。カニにとって最も快適な環境を用意してあげられるように、事前によく調査してからカニ飼育を始めましょう。
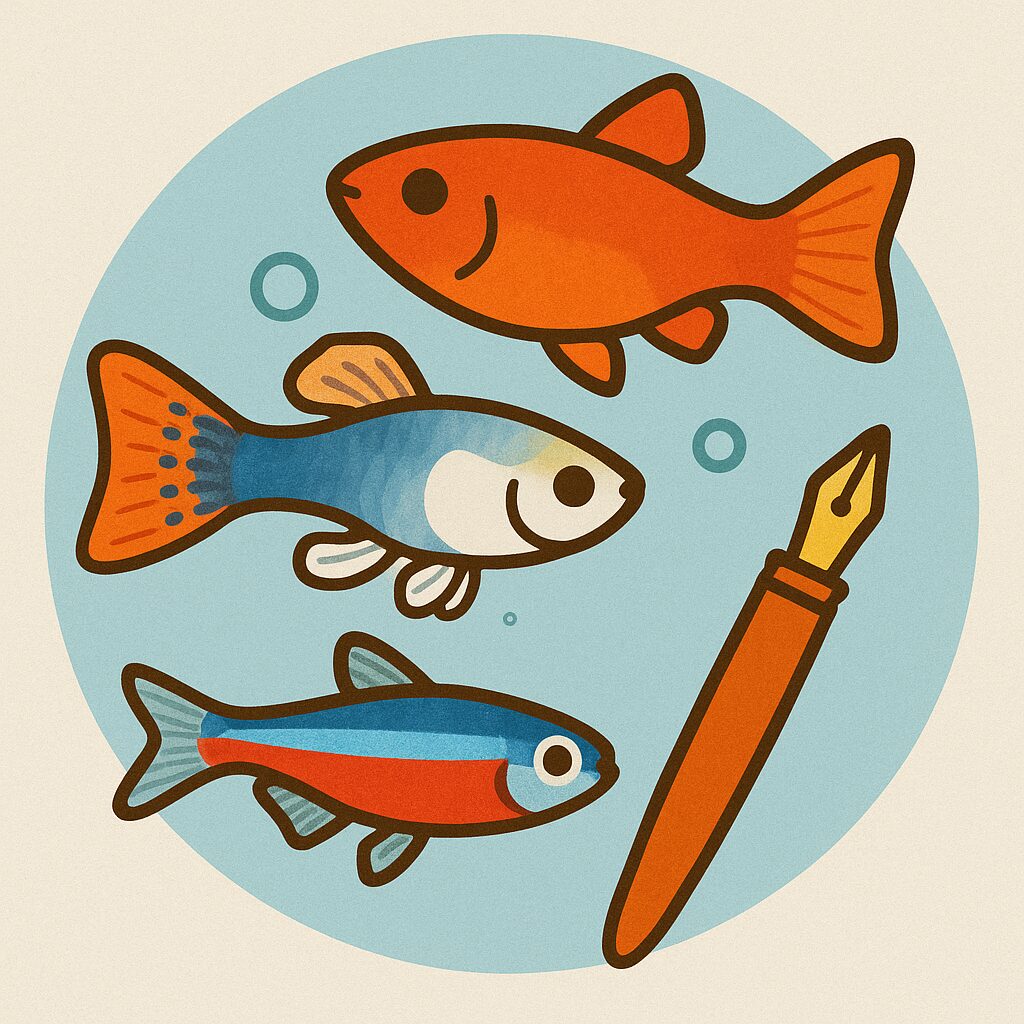
子どもの頃から魚や昆虫を飼育し、アクアリウム歴は約30年になります。 グッピーやプラティ、ネオンテトラなどの入門魚飼育から始まり、シクリッドのブリーディングなどを経て、最近ではアクアテラリウムのレイアウトを楽しんでいます。
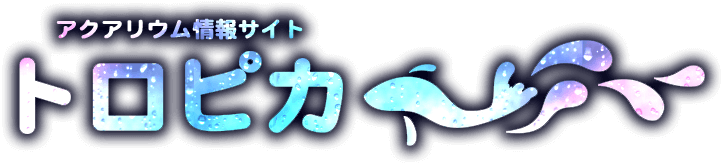


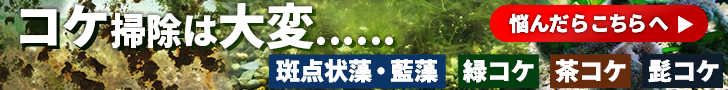


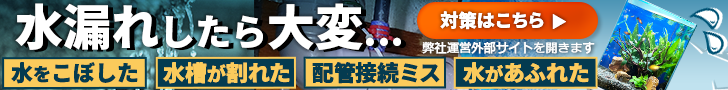






![(カニ)レッドアップルクラブ (約2cm)<1匹>[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51-PwERZXWL._SL500_.jpg)



























