水槽の魚を観察していて、体表の“できもの”が気になったことはありませんか?
なくなるだろうと放っておいたら、次第に大きくなり「気が付いた頃には魚が衰弱していた」ということもあります。これらの正体の多くは「病気」や「寄生虫」で、もちろん適切な治療も大切ですが、できものの症状を観察して“早期発見”することがとても重要です。
そこで、今回は魚の体にできるイボや皮膚炎などを症状別に解説します。大切に飼育している魚にできものがあったら、似たような症状が出ていないかチェックしてみてください。
熱帯魚・観賞魚の体のできもの
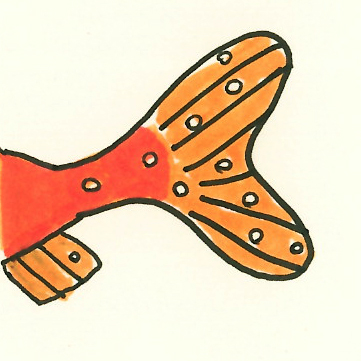
熱帯魚や観賞魚の体にできものが現われるのは珍しいことではなく、飼育していれば1度は経験する問題です。
できものの正体を大きく分けると、
- 病気
- 寄生虫
この2つです。症状によって治療方法が異なるため、しっかり観察して早期発見につなげましょう。
白点病
「白点病」は、多くの魚がかかる病気で「ウオノカイセンチュウ」という寄生虫が原因です。
体表に寄生すると白い斑点として現れ、症状が進むにつれて衰弱し死んでしまうことも。尾びれなどの末端部から次第にエラの方へ移動して、朝に1度離れて夜になると再度吸着する傾向があります。
初期症状であれば塩浴も効果的ですが、重篤化しているようであれば薬浴をおすすめします。
白点病については、上記の動画とこちらの記事を参考にしてみてください。
口ぐされ病
「口ぐされ病」になると口の周りが白く膨れ、進行するとボロボロになってしまいます。
ひどい場合は、餌が食べられず弱ってしまうことも珍しくありません。「カラムナリス菌」という細菌に感染することで発症しますが、珍しい菌ではなくどのような水槽にもいて、魚が体調をくずして免疫力が低下したときにかかります。
塩浴、もしくは薬浴が効果的ですが、「尾ぐされ病」と原因菌が一緒なので、治療法も同じです。口ぐされ病の疑いがある場合は、上記の動画を参考にしてみてください。
ツリガネムシ
「ツリガネムシ(エピスティリス症)」に寄生されると、体表やひれに白点として現れます。
初期は白点病と間違えやすいものの、点が大きく高さがあり、鱗を持ち上げたり充血させたりなどするのが特徴です。中期以降は尾ぐされや穴あき病と症状が似ています。
ツリガネムシには、「アグテン」や「グリーンFリキッド」といった魚病薬が効果的です。
ウオジラミ
「ウオジラミ」は、魚につくダニのような存在で、丸い甲虫のような見た目をしています。
魚に付着して吸血するので、患部が炎症を起こし重篤化すると衰弱死することもあります。
成虫であれば、ピンセットを使って目視で取り除くこともできますが、魚の体表がすれたりストレスになったりするうえに、肉眼で見えない幼虫を除去できないため、「レスバーミン」や「ムシクリア液」、水量が多い場合は「デミリン」を使った薬浴が良いでしょう。

イカリムシ
灰色をした5mm程度のトゲのような寄生虫で、体表に刺さって吸血したり炎症を起こしたりします。
目視で確認できるものは毛抜きで対処しますが、深く刺さっていると抜いたことで魚に大きなダメージを与えてしまうため、より安全な治療法としては薬浴がおすすめです。
魚病薬は、「リフィッシュ」もしくは「デミリン」がよく用いられます。

エロモナスの体内感染
「エロモナス」は、珍しくない常在菌ですが、水質の悪化や魚の体調不良の際に感染・発症します。
筋肉感染して悪化すると、体内で膿が発生して症状が進むとニキビの様な腫瘍になります。腫瘍が潰れて膿が出てくることがありますが、それだけで改善することはありません。
エロモナスの体内感染が疑われる場合は、「パラザンD」や「グリーンFゴールド」による薬浴が一般的ではあるものの、完治が難しいケースも多いです。金魚に関しては、延命措置として低温飼育(15度程度)で菌を不活性化することで完治しないまでも腫瘍が小さくなることもあります。
ただ、水温の上昇とともに菌が活性化し症状が悪化するため、根本的な解決にはいたりません。その他にも患部に血が滲みがけがをしたように見える赤斑病も、エロモナス感染です。
ポックス病
「ポックス病」は、乳頭腫症とも呼ばれ、金魚やコイなどに発症する珍しい病気です。
白い腫瘍が体にでき巨大化すると泳ぎにくくなりますが、すぐに死んでしまうことはありません。ただし、長期化することでストレスがたまり健康に悪影響をおよぼすことがあります。
自然に小さくなることがあるものの、再発しやすいうえに効果的な治療法がない厄介な病気です。致死率は高くありませんが、魚の観賞性を下げてしまうので、金魚やコイ(錦鯉)には大きな問題といえます。
できものを見つけたら

魚の体表にできものが現れたら病状を確認した後、
- 隔離や薬浴
- 現状維持
といった方法をとります。
改善の見込みがあるものは治療を進め、難しいものは重篤化させないよう水質や給餌量に気を配ることが大切です。
隔離や薬浴を行おう

症状から病名が判明したら、隔離や薬浴を行いましょう。
感染力が高い病気を放置すると二次感染につながるので、違う飼育容器に隔離して適宜治療します。また、同じ水槽の魚に初期症状が出ていないか入念にチェックすることも重要です。
早期発見できれば治りも早いうえに、水質改善や塩浴といった魚にかける負担が小さい方法で完治させられる場合もあります。
難治性のものは現状維持が大切
エロモナスの体内感染やポックス病など、難治性のものは現状維持が大切です。
無理に処置すると、かえって体力を奪ってしまうこともあるため、清潔な環境を整えて様子を見ましょう。
焦らず、水換えをして良い水質を保ち餌を少なめに与えて長期療養します。また、塩浴には治療の他にも“浸透圧調整を楽にして魚の負担を減らす”効果も期待できるので、この場合にも有効です。
まとめ:魚の体にできる、できモノは何?イボ・皮膚炎など症状別に解説します!

魚の体にできものが現れたら、症状を確認していち早く病気を特定することが重要です。
- 大きさや色
- 形
- 発症した部位
といった情報を元に判断して、早期治療に努めましょう。
ときには、長期化したり治療が難しかったりすることもありますが、愛情を持って治療・療養させてあげることが1番大切です。
トロピカライターの高橋風帆です。
アクアリウム歴20年以上。飼育しているアーモンドスネークヘッドは10年来の相棒です。
魚類の生息環境調査をしておりまして、仕事で魚類調査、プライべートでアクアリウム&生き物探しと生き物中心の毎日を送っています。
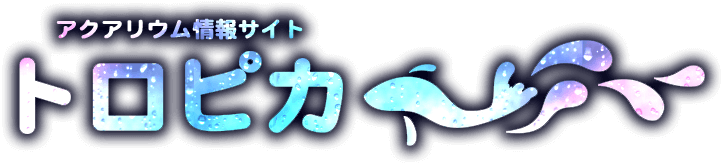
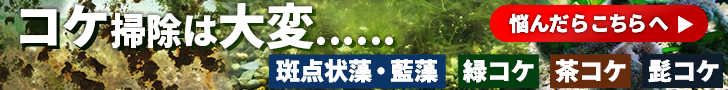


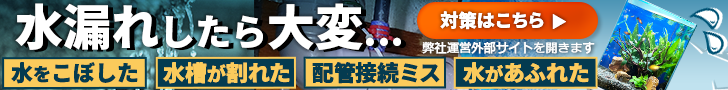

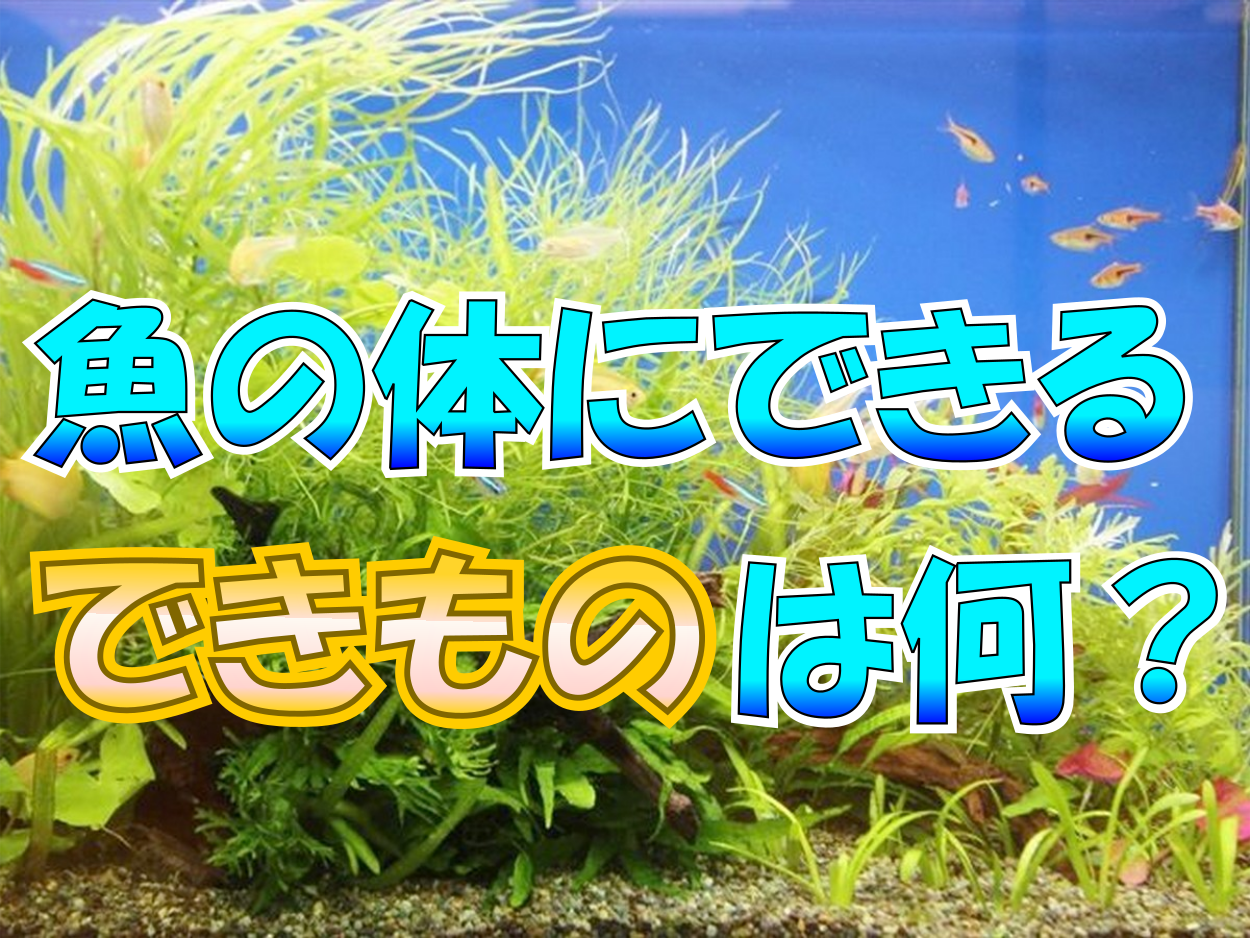













金魚の左目の近くにイボのようなものがあります
初めはとても小さくて色も金魚の色と同じだったのですが今は7ミリほどです色わ薄い黄色のような色です
いったいなんなのでしょうか
実際に拝見していないため、正確な回答ではないことをご了承ください。
ポックス病の可能性があります。
しかし、現時点ではまだ判別が難しいです。
赤くなるなら穴あき病の可能性もあるので、様子を見つつ治療薬を決めるのが良いでしょう。
穴あき病についてはこちらのコラムもご参照ください。
https://t-aquagarden.com/column/ulcer_disease
※東京アクアガーデンのサイトが開きます。
よろしくお願いいたします。
金魚の背びれに白い丸い点があるのですか
これは病気でしょうか BB弾より少し小さいくらいです
実際に拝見していないため、正確な回答ではないことをご了承ください。
寄生虫か細菌感染症と考えています。
移動したり増える場合は寄生虫、移動せず徐々に大きくなる場合は細菌感染症です。
様子を見つつ、薬浴をおすすめします。
こちらのコラムもご参照ください。
・金魚の寄生虫と対処法!種類と対策を解説!季節の変わり目は特に注意!
https://t-aquagarden.com/column/goldfish_parasite
※弊社運営の外部サイトが開きます。
よろしくお願いいたします。
はじめまして
メダカの体に二ヶ所 メダカの粉エサに似たできもの皮膚病があります どのような薬が効果的でしょうか?
実際に拝見していないため、効果的な治療方法はお伝え出来ませんが、皮膚病の場合は薬浴がおすすめです。
メダカの病気については、こちらのコラムをご参照ください。
・メダカの病気!かかりやすい尾ぐされ病など7種の症状と対処法を解説
https://t-aquagarden.com/column/disease_medaka
※弊社運営の外部サイトが開きます。
よろしくお願いいたします。
初めまして、
らんちゅうの顎の下に突起物が1週間前からできています。少しずつ大きくなってます。元気なので様子を見ていますが、寄生虫の様には見えないし、何かした方が良いのでしょうか?
実際に拝見していないため正確な回答ではないことをご了承ください。
考えられるのは、穴あき病・細菌感染か腫瘍です。1週間で大きくなってきているのですと病気の可能性が高いので薬浴をおすすめしています。
こちらのコラムもご参照ください。
・熱帯魚の病気を症状別に解説!魚の泳ぎ方・体表の変化と治療・対処法
https://t-aquagarden.com/column/tropical_fish_treatment
※外部サイトが開きます
何卒よろしくお願いいたします。
返信ありがとうございました。
薬浴、試してみます。
琉金の尾びれに赤い斑点が1つあります。特に金魚は元気そうなのですが、怪我なのか寄生虫なの
か分かりません。対策などございませんか。
実際に拝見しておりませんので、正確な回答でないことをご了承ください。
3~7日ほどしても、変化が無ければ問題ないと考えています。
赤斑病の可能性もありますが、多めの水換えをおこなえば回復することが多いです。
まずは、しっかりめの水換えや掃除を行い、様子を見るのがおすすめです。
こちらのコラムもご参照ください。
・金魚の水槽掃除方法!フィルターや砂利など、清潔な水槽で病気を防ごう!
https://t-aquagarden.com/column/goldfish_cleaning_method
※外部サイトが開きます。
よろしくお願いいたします。
金魚のおでこ辺りに 8ミリほどの黒い出来物があります。
初めは 皮膚の色と同じでした。
実際に拝見していないため、正確な回答ではないことをご了承ください。
『黒ソブ』と呼ばれるが状態と考えています。
原因はストレスなどで、回復すると元の体色に戻っていきます。
もし、できものが膨らんだり大きくなる場合は穴あき病の可能性もありますので、水換えや掃除を行って様子を見てください。
こちらのコラムもご参照ください。
・金魚の鱗がはがれる!穴あき病の治療方法!感染原因を知って対策しよう
https://t-aquagarden.com/column/ulcer_disease
よろしくお願いいたします。