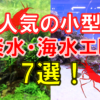日本人に馴染みの深い金魚。学校やご家庭で、皆さんも一度は飼育の経験があるのではないでしょうか?
ひとことで「金魚」といっても体色やヒレの形などによって何通りもの種類に分けられ、同じ色柄・体型を持つ個体は一匹として存在しないといわれています。
「和金」「琉金」「東錦」など金魚にはさまざまな品種がありますが、同じ品種でも模様や体型が少しずつ異なり、それぞれの個性を楽しむことができるのです。
今回はそんな奥深い金魚の種類について、体色や模様・尾ヒレの形・頭の形という3つのポイントに着目してご紹介していきます!
金魚の体色・模様の種類
ショップやご自宅の金魚をよく観察してみましょう。
金魚には通常の鱗(うろこ)以外に、色素がない透明鱗、キラキラと光を反射するメタリックな銀鱗などが存在します。
金魚はこれらの鱗の発現具合によって、色や模様など体色のバリエーションが決まってくるのです。
まずは金魚の体色・模様の種類ということで、
- 1色タイプ
- 2色タイプ
- 3色タイプ
- 特殊タイプ
こちらの4タイプに分けて解説していきます。
1色:赤(素赤・猩々)・白・黒・黄色・茶
単色のバリエーションとして挙げられるのが、赤・白・黒・黄色・茶の5種類です。
「赤」は金魚の中でもっとも多い体色ですが、ヒレの部分が白く他全体が赤いものを素赤(すあか)、ヒレまで赤いものを猩々(しょうじょう)と呼びます。
「白」は以前と比較するとかなり人気が高くなってきました。頭部に少し赤色を残していても、白と区別されることが多いです。
「黒」といえば出目金が代表種ですね。やはり漆黒に近い濃い色の個体は高値で取り引きされます。
「黄色」はゴールデンコメットなど鮮やかな黄色に発色するものから、オレンジ色に近い発色になるものまでを指します。
「茶」は紫が混ざったような小豆色の体色で、茶金(茶色の和金)が有名です。
2色:更紗・青・パンダ
2色のバリエーションとして挙げられるのが、更紗(さらさ)・青・パンダの3種類です。
「更紗」は紅白の体色のことで、体の一部が赤、他の部分が白色の金魚のことを指します。
紅白の色合いは縁起が良いため、とても人気のある体色です。
「青」は一見単色に見えますが、黒と乳白色に透ける透明鱗が重ならなければ成り立たないため2色のバリエーションに分類しました。
紺や銀色とも捉えられるような深みのある色合いで、青文魚(青のオランダ獅子頭)などが代表的です。
「パンダ」はその名の通り白黒の体色で、出目金やオランダ獅子頭に多く見られます。
3色:キャリコ・桜
3色のバリエーションにはキャリコ・桜などが挙げられます。
「キャリコ」は白の真皮に赤・黒・浅葱(青)が入り混じった体色です。
単にキャリコというと「キャリコ琉金」のことを指しますが、キャリコのランチュウは「江戸錦」、キャリコのオランダ獅子頭は「東錦」など品種の呼び名そのものが変わる場合もあります。
「桜」は紅白の模様の入った真皮に透明の鱗がかぶさったもので、同じ紅白でも透明が入っている分、更紗より柔らかく淡い色合いに見えます。
特殊:六鱗・緑・パールスケール
特殊な体色として挙げられるのが、六鱗・緑・パールスケールです。
「六鱗」とはエラ蓋・背ヒレ・腹ビレ・胸ビレ・尻ビレ・尾ヒレの6ヶ所に赤色が入り、他が白色のものを指します。六鱗は金魚の鱗が生え変わるときに白色になることを利用し、作為的に鱗を剥いだ人工調色のため、近年は減少傾向にあります。
「緑」は最近登場した新色で、青(黒+乳白色)と黄色がうまい具合に混ざり合った金魚です。
緑の金魚と言えば金魚仙人こと故・川原やどるさんが生み出した「はるやどる」が有名ですね。
「パールスケール」は珍珠鱗(ちんしゅりん)とも呼ばれ真珠のような光沢をもつ鱗のことを指し、「ピンポンパール」や「浜錦」などが代表的です。
パールスケールは鱗が少し出っ張っている上に、剥がれると元の鱗には戻りません。慎重に扱いましょう。
ちなみに、ヒレのがフナ尾タイプのものをちょうちんパール(提灯ピンポン)と呼びます。
尾ヒレの形
続いては尾ヒレの形ということで、
- フナ尾
- 三ツ尾・四ツ尾・桜尾
- ふきながし
- 特殊な尾ヒレ
こちらの4つの項目に分けて解説していきます。
フナ尾
金魚の祖先であるフナの形を受け継いだのが「フナ尾」です。
もっとも一般的で、和金の標準体型でもあります。
三ツ尾・四ツ尾・桜尾
「三ツ尾」はフナ尾の突然変異を定着させたもので、金魚を上から見るとアヒルの足のように三つ叉に分かれています。ほぼすべての品種に現れる形状です。
「四ツ尾」は三ツ尾の真ん中部分に根本まで切れ込みが入り、四つ叉に見える形状の尾ヒレのことを指します。
「桜尾」は四ツ尾と似ていますが、真ん中の切れ込みが浅く桜の花びらのように見えます。
ふきながし
フナ尾の形状をやや細長くした尾ヒレを「ふきながし」といいます。
通常はコメットや朱文金など細身で泳ぎの速い金魚が持つことの多い尾ヒレですが、琉金や出目金にもふきながし尾が出現する場合があり、それらを「柳琉金」や「柳出目金」と呼びます。
特殊な尾鰭:そり尾・孔雀尾・ハートテール
「反り尾」は土佐金に見られる尾の形状で、上から見ると扇を広げたように半円形をかたどります。
「孔雀尾」は金魚の伝統的な品種である地金が持つ尾の形状で、少し前にご紹介した「四ツ尾」がさらに変形した形をしています。
後ろから見るとX字状に広がり、孔雀の尾を連想させることから孔雀尾と呼ばれているようです。
「ハートテール」はイギリスのブリストル地方で作出されたブリストル朱文金の持つ尾ヒレで、横から見ると可愛らしいハート型をしていることからその名が付きました。
頭の形(肉瘤)の種類
肉瘤とは金魚の頭部に発達する脂肪の塊のことで、オランダ系やランチュウ系に見られます。
ここでは肉瘤の形状ということで、
- フンタン
- 高頭
この2種類についてご紹介していきます。
フンタン
頬の部分につく肉瘤のことを「フンタン」と呼びます。
発達すると目の下がせり上がり、頬を膨らましているような表情見えてとても可愛らしいです。
高頭
通常よりも頭部の肉瘤が大きく成長した(または成長する予定の)ものを「高頭」と呼びます。
丹頂や高頭パールなどが有名です。
金魚は成長で体色・模様が変わる!

金魚の模様は遺伝の影響が強いため種類ごとに素質は決まっているものの、発色具合や模様の出方は成長とともに変化していきます。
ヒレの広がりや垂れ具合なども飼育環境により変化するため、育て方によって個性の違いを楽しめるという点は金魚飼育の醍醐味ともいえるでしょう。
まとめ:金魚の体色・模様の種類!更紗・三色から頭の形まで!成長で体色は変わる?

今回は金魚の体色や模様・尾ヒレの形・頭の形という3つのポイントに着目して解説してきました。
金魚にはさまざまな品種が存在し、体色やヒレの形状などによってさらに多くの種類に分けることができます。
飼育環境や成長に応じて色味や形の変化が楽しめるという点も、金魚飼育の魅力のひとつですよね。
金魚は愛情を注げば注ぐほど、魅力を出してくれる生き物です。
皆さんもお気に入りの金魚を見付けて、好みの姿・形に育ててみてはいかがでしょうか?
トロピカライターの井上あゆみです。
金魚から熱帯魚・海水魚まで、全部で20種類程度のお魚を飼育してきました。
お気に入りはイエローヘッド・ジョーフィッシュ。怒ったような顔をしているのに、実はかなり臆病というなかなか憎めない海水魚です。アクアリウム初心者の方でも楽しく読めるような記事を書いていくので、よろしくお願い致します!
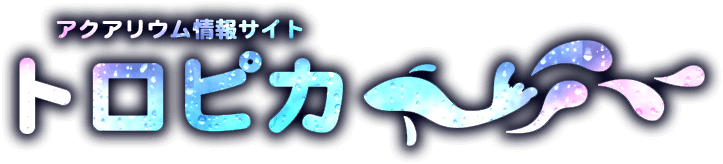
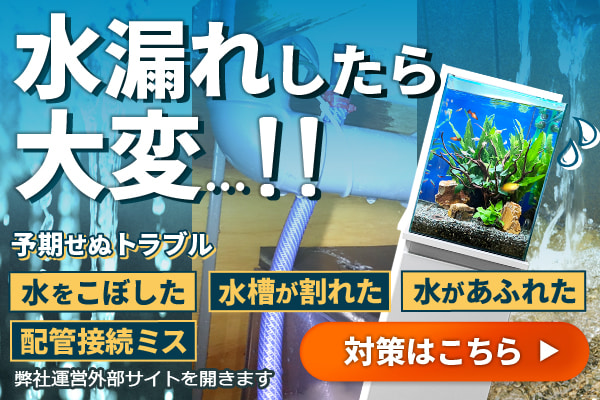

















![国産 らんちゅうМ 宇野系(全長約5cm) [生体] 創業35年 八仁堂](https://m.media-amazon.com/images/I/416Uc8VgoLL._SL500_.jpg)